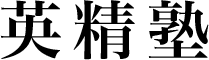コラム
遅まきながらの読書人の宿命
これは、弊著『英語教師は<英語>ができなくてもよい!』の中で用いた表現なのだが、英語教師には、12才から英語を始めてなった者、それに対して、幼少期から小学校時代にかけて、また、小学校時代に数年間、シンガポールやアメリカなどの英語圏で過ごした経験を持つ英語教師、この二タイプがあると語ったことがある。前者の英語を宿命の英語(準ジャパの英語)、後者のそれは、運命の英語(ネイティブ・帰国子女の英語)と命名した。この場では、割愛するが、前者の宿命の英語教師族は、その後、生徒の目線で、より良い授業、よりよい教材をつくり上げてゆくことが、最優先で、自己が、TOEIC900点以上を、また、英検1級をと、猛勉強するのは、二の次でもいい、その余力があれば、様々な古今東西の名籍を読み、教養を積み、その“知”を英語の授業に取りいれることが、第一の原理原則とすべし、そういった内容の主旨で、弊著を書いたわけでもある。この言説、逆説的ながら、世の教師にご理解できない者も多い。文科省寄り、自身が英語が好きで面白く、それを生徒に押し付けようとする教師に多い。因みに、意外と思われるが、夏目漱石は、宿命の英語族の典型でもあった。これが、どれほど、彼の個性・気質に影響を与えたことか!
この宿命の英語族、この運命の英語族、これを捩って、宿命の読書人、そして、運命の読書人、こういった区分けができるという視点で語られた書物、新書であれ、専門書であれ、皆無とさえ言ってもいい。大方の、読書論なるものは、知識人(小泉信三・渡部昇一)から教育者(斉藤孝)にいたるまで、自らが読書好き、それも、楽しさをべースに、子どものころから行ってきて知的営みを語っているものに過ぎないのである。いわば、運命の読書である。私が脚光を浴びせたいのは、宿命の読書なのである。それについての随想のようなことを語ってみたい。
世の中の、そこそこ裕福なご家庭では、我が子を、幼少期から低学年にかけて、水泳かピアノを習わせる“エリート的教育神話”が有名である。勿論、文化資本がある程度ある、若干教育熱心なご父兄でもあろうか。その理由の一つは、「幼少期から水泳やピアノをやると東大へ行く可能性がある」「子供時代にそうしたものをやっておくと、小学校の勉強の成績が伸びる」「そうした体育系や音楽系をやっておくと身体上、情操上、何かと良き効果がある」などなど、そした教育的通説を信奉して、我が子に習い事をさせているといったものである。当然、結果論から逆照射すれば、東大生は、幼少期に、スイミングスクールに通っていただの、ピアノの稽古をしていたなどといった因果関係が、裕福度の文脈から、当然高い確率であり得ることでもあろう。
以上の、勉学と<水泳とピアノ>といた因果関係とも比類するが、それ以上に、根拠が確からしい説として、勉学と読書の因果関係というものがある。これは、その後、初等・中等教育と日本語、いや、母国語の豊饒さに起因してもくる。この事実は、世の中の有名人{林修・三浦瑠璃・茂木健一郎・山口真由:みな東大卒でもある!}などを概観すれば、大方、なるほど!と納得せざるをえない真実でもあろう。運命の読書人である。
こうした、教育上の仮説、真実に近い神話とやらに、気づいて、いや、“信仰”したのが、我が思春期の、高校中退から中学浪人の、これまでの、たがだか17年弱の自身の人生行路を顧みた時に、悟った<考え>でもあった。
それは、自身の国語の成績の悪さである。英数理社に比較して断然点数が悪い国語という教科、この弱点克服を、中学浪人という自由なる時間で、どうにかできないものか、その達観、覚悟といった動機で、<読書という宗門>をくぐった口でもある。
ちょうど、野菜(活字の本)が嫌いな子どもが、ある日、「野菜も食べなければ身体に良くない!」という決意をして、いやいやながらでも野菜を食べる始める行為にも似ていよう。しかし、こうした子供は、稀なケースでもあろう。本心では、やはり、肉類(アニメやマンガ)のほうが断然うまい(面白い)という<味覚経験>が先行してもいるのは確かである。
やはり、ここ数回語ってもきたことだが、幼少期から、親の絵本などの読み聞かせ習慣の第二段階で、ルビ付きでもいい、活字オンリーの物語や小説を小学校低学年までに、その読書の愉楽を味わった部族、そして、真の読書が、高学年から中学校の後半にかけて始まった部族には、<言葉の貴族>として、私のような<言葉の庶民>との違い位に、隔世の文化的層の厚みみたいなものが存在するとも言えようか。これは、私がよくする比喩なのだが、小学1年生から始めた水泳の能力と中学から始めたそれとの違いともいえるものである。前者は、名優に朗読してもらっているかのように、活字の世界を苦もなく、むしろ楽しく泳げる。一方、後者は、少々の苦痛を伴いながらも、必死に泳ぐ、そのファームにも表れる。とにかく、泳ぐスピードが違うように、速読の出来不出来にも類するのである。後者は、一般的に遅読族にありがちな気質である。作家の平野啓一郎などもその部族でもあり、高校の頃から三島などの小説にはまり込んでいったとも言う。
本来、読書というものは、国語の成績をあげるためにあるものではない。楽しみ、知識、また、教養などを主眼として、一生涯にわたり行う、知的な営為なのである。こうした動機は、典型的ながら、我が子4人に意図的に行ってもきたのが、あの佐藤亮子(佐藤ママ)で実証済みでもある。この流儀を、私自身、17才で自覚して、自身に“修行”のように行っても、高校における現代文の成績には、余りマッチングしなかった。因に、古典を除く、現代文の高校での成績(通知表)は、高一は3、高二は4、そして、高三の最後には5とついたものの、その後の、予備校模試や、国公立の二次の現代文などは、苦戦したものである。学校の定期試験は、やったものの(既知の)ちっとした応用程度である、期末中間など楽でもあった。それに対して、模試などは、初見の文を時間内で読み込んで(速読と深い読みが必要)出題者の意図に応じなければならない暗黙の流儀といったものが必要だっだからだ。この出題者の意図と作者の意図とは、ズレが生じる場合もあれば、ズレない場合もあった。ここに、私自身の独特の読み{これが厄介で、後日語るとしよう}という行為とも意識ともいいえる魔物が介在し、評論文や小説を自己流に読み込んでしまう習癖があったことが最大の要因でもあった。読解上の類推の魔という魔物、厄介者が、客観性を最優先する現代文という読解問題を処理する際の、最大の障害物ともなっていたからである。どうして、こうした、我流の読みとなる、読解の陥穽にはまってしまう高校生だったかを次回語ってみたいと思う。
」
この宿命の英語族、この運命の英語族、これを捩って、宿命の読書人、そして、運命の読書人、こういった区分けができるという視点で語られた書物、新書であれ、専門書であれ、皆無とさえ言ってもいい。大方の、読書論なるものは、知識人(小泉信三・渡部昇一)から教育者(斉藤孝)にいたるまで、自らが読書好き、それも、楽しさをべースに、子どものころから行ってきて知的営みを語っているものに過ぎないのである。いわば、運命の読書である。私が脚光を浴びせたいのは、宿命の読書なのである。それについての随想のようなことを語ってみたい。
世の中の、そこそこ裕福なご家庭では、我が子を、幼少期から低学年にかけて、水泳かピアノを習わせる“エリート的教育神話”が有名である。勿論、文化資本がある程度ある、若干教育熱心なご父兄でもあろうか。その理由の一つは、「幼少期から水泳やピアノをやると東大へ行く可能性がある」「子供時代にそうしたものをやっておくと、小学校の勉強の成績が伸びる」「そうした体育系や音楽系をやっておくと身体上、情操上、何かと良き効果がある」などなど、そした教育的通説を信奉して、我が子に習い事をさせているといったものである。当然、結果論から逆照射すれば、東大生は、幼少期に、スイミングスクールに通っていただの、ピアノの稽古をしていたなどといった因果関係が、裕福度の文脈から、当然高い確率であり得ることでもあろう。
以上の、勉学と<水泳とピアノ>といた因果関係とも比類するが、それ以上に、根拠が確からしい説として、勉学と読書の因果関係というものがある。これは、その後、初等・中等教育と日本語、いや、母国語の豊饒さに起因してもくる。この事実は、世の中の有名人{林修・三浦瑠璃・茂木健一郎・山口真由:みな東大卒でもある!}などを概観すれば、大方、なるほど!と納得せざるをえない真実でもあろう。運命の読書人である。
こうした、教育上の仮説、真実に近い神話とやらに、気づいて、いや、“信仰”したのが、我が思春期の、高校中退から中学浪人の、これまでの、たがだか17年弱の自身の人生行路を顧みた時に、悟った<考え>でもあった。
それは、自身の国語の成績の悪さである。英数理社に比較して断然点数が悪い国語という教科、この弱点克服を、中学浪人という自由なる時間で、どうにかできないものか、その達観、覚悟といった動機で、<読書という宗門>をくぐった口でもある。
ちょうど、野菜(活字の本)が嫌いな子どもが、ある日、「野菜も食べなければ身体に良くない!」という決意をして、いやいやながらでも野菜を食べる始める行為にも似ていよう。しかし、こうした子供は、稀なケースでもあろう。本心では、やはり、肉類(アニメやマンガ)のほうが断然うまい(面白い)という<味覚経験>が先行してもいるのは確かである。
やはり、ここ数回語ってもきたことだが、幼少期から、親の絵本などの読み聞かせ習慣の第二段階で、ルビ付きでもいい、活字オンリーの物語や小説を小学校低学年までに、その読書の愉楽を味わった部族、そして、真の読書が、高学年から中学校の後半にかけて始まった部族には、<言葉の貴族>として、私のような<言葉の庶民>との違い位に、隔世の文化的層の厚みみたいなものが存在するとも言えようか。これは、私がよくする比喩なのだが、小学1年生から始めた水泳の能力と中学から始めたそれとの違いともいえるものである。前者は、名優に朗読してもらっているかのように、活字の世界を苦もなく、むしろ楽しく泳げる。一方、後者は、少々の苦痛を伴いながらも、必死に泳ぐ、そのファームにも表れる。とにかく、泳ぐスピードが違うように、速読の出来不出来にも類するのである。後者は、一般的に遅読族にありがちな気質である。作家の平野啓一郎などもその部族でもあり、高校の頃から三島などの小説にはまり込んでいったとも言う。
本来、読書というものは、国語の成績をあげるためにあるものではない。楽しみ、知識、また、教養などを主眼として、一生涯にわたり行う、知的な営為なのである。こうした動機は、典型的ながら、我が子4人に意図的に行ってもきたのが、あの佐藤亮子(佐藤ママ)で実証済みでもある。この流儀を、私自身、17才で自覚して、自身に“修行”のように行っても、高校における現代文の成績には、余りマッチングしなかった。因に、古典を除く、現代文の高校での成績(通知表)は、高一は3、高二は4、そして、高三の最後には5とついたものの、その後の、予備校模試や、国公立の二次の現代文などは、苦戦したものである。学校の定期試験は、やったものの(既知の)ちっとした応用程度である、期末中間など楽でもあった。それに対して、模試などは、初見の文を時間内で読み込んで(速読と深い読みが必要)出題者の意図に応じなければならない暗黙の流儀といったものが必要だっだからだ。この出題者の意図と作者の意図とは、ズレが生じる場合もあれば、ズレない場合もあった。ここに、私自身の独特の読み{これが厄介で、後日語るとしよう}という行為とも意識ともいいえる魔物が介在し、評論文や小説を自己流に読み込んでしまう習癖があったことが最大の要因でもあった。読解上の類推の魔という魔物、厄介者が、客観性を最優先する現代文という読解問題を処理する際の、最大の障害物ともなっていたからである。どうして、こうした、我流の読みとなる、読解の陥穽にはまってしまう高校生だったかを次回語ってみたいと思う。
」