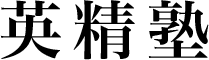コラム
宿命の読書人、それもその異端派の動機とやら
「子供のころは『真田幸村』に打ち震え、『三国志物語』を読んで血沸き肉躍る思いをし、大人になってからはMarjorie Morningstarを読んで初めて英語の小説に感激することができました。こうした一連の感動はいうまでもなく文字の力によって引き起こされたものですが、これは人間にしか味わうことのできない楽しみです。人間しか言語を操ることができないからです。」
『本を読まないとバカになる! 知的読書の技術』(渡部昇一)~ビジネス社~
こうした渡部氏のような人を、運命の読書人というのです。
人は、なぜ読書をするのでありましょうか?それは、正統派は、親の絵本などの読み聞かせから始まり、小学校低学年で、童話や伝記などの物語の世界へスライドしてゆきます。そして、少々オマセの高学年なら、世界の名作といわれる小説などを読み始めてもゆくでしょう。この十歳前後は、濫読期、いわゆる、子どもの読書であります。これが、中学から高校生ともなると、プレ大人の読書ともいい、知的なる本、例えば、哲学書・思想書・ノンフィクションのジャンルへ踏み込んでもゆく、また、司馬遼太郎などの歴史小説へと食指がのびる少年もおりましょう。このようにして、読書という自らの荘園を広めてゆくのが、前回でも触れた、運命の読書人ともいえる人々でもあります。こうした、種族は、昭和から平成、そして令和にかけて、マンガ、アニメ―ション、テレビもですが、そうした娯楽的非活字世界の台頭で、絶滅危惧種にもなりかけている趨勢は、街中の書店の激減、また、スマホの日常化が、原因ともされています。
私は、こうした正統的読書人ではありませんでした。そもそもが、アニメ、マンガ、そうしたサブカルの世界を放棄して、敢えて、出家した僧の如く、活字オンリーの、言葉による喚起イメージを主力とする、読書という世界に踏み入った、宿命の読書人でもあるからです。
では、私の読書をする、脳内の動き、活字を追う作業、その真意、深層というものを語ってみたいと思います。
そもそも、純粋に読書をする、その目的とは、その物語の世界に浸り、面白いとか、わくわくするとか、様々な感動を期待し、表紙をめくり、ページを一枚一枚心躍らせながら開いてもゆく、また、様々な情報や知識の習得など、時に、知恵や教養を目的に、仕事、プラーベートなどで役立たせようといった大人の読書もありましょう。そうした人々は、その内容に自己の人格を浸らせるというものでもあります。私の読書は、そうしたものとは少々、いや、大分、肌色、毛色といった、読書の赴きが違っていたのであります。
以前にも語ったことでありますが、そもそも、私の読書のきっかけは、国語の成績の悪さ、そして、高校中退、中学浪人、いい意味での疎外感、<前向きなる孤独:青年は荒野(読書)をめざす>とも申せましょうか、17歳で、本しか、娯楽として友になる存在がなかったこと、そして、自らの不運また、不幸ともいえる、家庭と自己との蹉跌ともいいうるものが、少々語弊がありますが、<マイナスの勲章>として、様々な作家の評伝を読み進む上で、その負の経験を、いつの日か、プラスに転じたい、何らかの小説ともいえるものを、将来書いてみたい、そういた様々なコンプレスを作品にしてみたい、あの桑田佳祐が、モテない男のコンプレックス、失恋の体験、そうした自身のマイナス経験を名曲に投与したような、芸術的営みを意識して、本の世界を、その修練場とする目的でもありました。ミュージシャンが、ビートルズやバート・バカラックに名曲のヒント、作曲の秘儀を盗もうとする心根とも近いものであったようです。
洋楽から影響を受け、その音楽がどうしてこんな構造で、こういう編曲をしているのか、その楽興を知的に分析するように、その小説家の作品の内部構造というもの、それを、鳥の眼、俯瞰的、一種、冷めた心で、作品を読み始めたというのが、動機のひとつでもありました。
当然ながら、宿命の読書人の悲しい性、気質でもありましょうか、私は遅読派でもあり、そんなに、速く読めない少年でもあることが、幸いしてか、その文章を読む際に、まるで、芥川賞の選考委員、また、出版社の名編集者のように、心ではなく、その作品を醒めた眼、客観的な頭で読むことが、高校2年あたりから始まりした。それは、高校1年の終わりころであります、谷崎・川端・三島といった文豪の『文章読本』を読んでしまってからでもあります。
それ以降、その作品、巨視的には、プロットやあらすじの巧みさ、微視的には、文章の巧みさ、文体や語彙といった次元を強烈に意識して、名作を読み進んでもいったわけです。超異色の、異端の読み手になってしまた。そのページ、その行、その文章で鉛筆で線を引き引き、「うん~!」「さずが~!」「なるほどね!」などと、その内容以前に、文体に唸っては、国語の先生が生徒の小論文を添削するメンタルに似たような気持ちで読書をしていったものです。まるで、映画評論家蓮見重彦が小津安二郎の映画を緻密に分析して、批評する目線とも似ていると言えましょうか。勿論、速読など意識にもない、また、感動や関心は二の次でもあったでありましょう、ある意味、邪道の読書人でもあったと言えましょうか。高校生が、小論文をうまくなりたい、上達させたい、そうした心理とも似てもいたことでしょう。
ですから、森鴎外や三島由紀夫、芥川龍之介などの文章を読んでは、高度の漢字表現、語彙ですが、鉛筆では〇で囲んでは、英単語のフラシュカードか小ノートにメモして、いつか使ってやろうとか、目論んでもいた、事実、学校の日直当番の日誌に、実際に使ってもみて、担任の体育教師Fから、「この言葉は何だ!」と問い詰められた、一種、衒学的な悪趣味の生徒でもあった。これも、16才までの自己へのリベンジ、反逆のようなもので、「コンプレックの強い人間に限り、プライドが高い」その深層心理の顕れでもあったことでしょう。これは、現代文の漢字テストへの復讐心もあったやもしれません。
次に、文章表現というものです。レトリック、隠喩や暗喩などの多彩さ、また、逆説なもの言い、描写の巧みさ、まるで、文章を読んでいながらも、映像が浮かびあがってくる表現力といったもの、この延長線に、フランスの作家フローベールに行き着いたわけでもあります。彼の、客観描写の極北、超絶のレアリズムといったものに仏文科で目覚めたわけでもあります。内容よりその表現、一種、文芸の芸術至上主義でもあります。その点で、やはり、フィクションというジャンルでは、平野啓一郎氏が語ってもいますが、日本文学では、その点では、三島由紀夫に並ぶものはいないと思います。
このように、ふしだら、非正統的、悪趣味、衒学的など、将来の、自己の負の経験をいかに、巧みに、表出できる武器を手に入れたい、それを磨きたいの一心で、語彙力と表現力、それの<農場・畑>、それが私の十代後半の読書の試みの修練場所でもありました。従って、そこには、読解力というものは、二の次、付帯的なものに成り下がってもいた、それが、現代文読解能力に結びついてもいなかった原因でもあった。
とりわけ、私は、当時から、そして今でも、ある名文、それは、小説にしろ、評論にしろ、それに遭遇すると、先に進む読みの動作の足を止め、そこから、派生する、様々な自己の経験やら、思想やら人物やらを夢想する気質がどうもあり、それが、読解上、類推の魔として、大学受験時代に、どれだけ足かせとなったことでありましょうか。そういった意味でも、本来の遅読とダブる障壁ともなり、現代文の模試などの点数が伸び悩んだ記憶があります。これも、宿命の読書人の中の、それも異端派のおくれてきた読書人の一つの定めと割りきってもいます。
『本を読まないとバカになる! 知的読書の技術』(渡部昇一)~ビジネス社~
こうした渡部氏のような人を、運命の読書人というのです。
人は、なぜ読書をするのでありましょうか?それは、正統派は、親の絵本などの読み聞かせから始まり、小学校低学年で、童話や伝記などの物語の世界へスライドしてゆきます。そして、少々オマセの高学年なら、世界の名作といわれる小説などを読み始めてもゆくでしょう。この十歳前後は、濫読期、いわゆる、子どもの読書であります。これが、中学から高校生ともなると、プレ大人の読書ともいい、知的なる本、例えば、哲学書・思想書・ノンフィクションのジャンルへ踏み込んでもゆく、また、司馬遼太郎などの歴史小説へと食指がのびる少年もおりましょう。このようにして、読書という自らの荘園を広めてゆくのが、前回でも触れた、運命の読書人ともいえる人々でもあります。こうした、種族は、昭和から平成、そして令和にかけて、マンガ、アニメ―ション、テレビもですが、そうした娯楽的非活字世界の台頭で、絶滅危惧種にもなりかけている趨勢は、街中の書店の激減、また、スマホの日常化が、原因ともされています。
私は、こうした正統的読書人ではありませんでした。そもそもが、アニメ、マンガ、そうしたサブカルの世界を放棄して、敢えて、出家した僧の如く、活字オンリーの、言葉による喚起イメージを主力とする、読書という世界に踏み入った、宿命の読書人でもあるからです。
では、私の読書をする、脳内の動き、活字を追う作業、その真意、深層というものを語ってみたいと思います。
そもそも、純粋に読書をする、その目的とは、その物語の世界に浸り、面白いとか、わくわくするとか、様々な感動を期待し、表紙をめくり、ページを一枚一枚心躍らせながら開いてもゆく、また、様々な情報や知識の習得など、時に、知恵や教養を目的に、仕事、プラーベートなどで役立たせようといった大人の読書もありましょう。そうした人々は、その内容に自己の人格を浸らせるというものでもあります。私の読書は、そうしたものとは少々、いや、大分、肌色、毛色といった、読書の赴きが違っていたのであります。
以前にも語ったことでありますが、そもそも、私の読書のきっかけは、国語の成績の悪さ、そして、高校中退、中学浪人、いい意味での疎外感、<前向きなる孤独:青年は荒野(読書)をめざす>とも申せましょうか、17歳で、本しか、娯楽として友になる存在がなかったこと、そして、自らの不運また、不幸ともいえる、家庭と自己との蹉跌ともいいうるものが、少々語弊がありますが、<マイナスの勲章>として、様々な作家の評伝を読み進む上で、その負の経験を、いつの日か、プラスに転じたい、何らかの小説ともいえるものを、将来書いてみたい、そういた様々なコンプレスを作品にしてみたい、あの桑田佳祐が、モテない男のコンプレックス、失恋の体験、そうした自身のマイナス経験を名曲に投与したような、芸術的営みを意識して、本の世界を、その修練場とする目的でもありました。ミュージシャンが、ビートルズやバート・バカラックに名曲のヒント、作曲の秘儀を盗もうとする心根とも近いものであったようです。
洋楽から影響を受け、その音楽がどうしてこんな構造で、こういう編曲をしているのか、その楽興を知的に分析するように、その小説家の作品の内部構造というもの、それを、鳥の眼、俯瞰的、一種、冷めた心で、作品を読み始めたというのが、動機のひとつでもありました。
当然ながら、宿命の読書人の悲しい性、気質でもありましょうか、私は遅読派でもあり、そんなに、速く読めない少年でもあることが、幸いしてか、その文章を読む際に、まるで、芥川賞の選考委員、また、出版社の名編集者のように、心ではなく、その作品を醒めた眼、客観的な頭で読むことが、高校2年あたりから始まりした。それは、高校1年の終わりころであります、谷崎・川端・三島といった文豪の『文章読本』を読んでしまってからでもあります。
それ以降、その作品、巨視的には、プロットやあらすじの巧みさ、微視的には、文章の巧みさ、文体や語彙といった次元を強烈に意識して、名作を読み進んでもいったわけです。超異色の、異端の読み手になってしまた。そのページ、その行、その文章で鉛筆で線を引き引き、「うん~!」「さずが~!」「なるほどね!」などと、その内容以前に、文体に唸っては、国語の先生が生徒の小論文を添削するメンタルに似たような気持ちで読書をしていったものです。まるで、映画評論家蓮見重彦が小津安二郎の映画を緻密に分析して、批評する目線とも似ていると言えましょうか。勿論、速読など意識にもない、また、感動や関心は二の次でもあったでありましょう、ある意味、邪道の読書人でもあったと言えましょうか。高校生が、小論文をうまくなりたい、上達させたい、そうした心理とも似てもいたことでしょう。
ですから、森鴎外や三島由紀夫、芥川龍之介などの文章を読んでは、高度の漢字表現、語彙ですが、鉛筆では〇で囲んでは、英単語のフラシュカードか小ノートにメモして、いつか使ってやろうとか、目論んでもいた、事実、学校の日直当番の日誌に、実際に使ってもみて、担任の体育教師Fから、「この言葉は何だ!」と問い詰められた、一種、衒学的な悪趣味の生徒でもあった。これも、16才までの自己へのリベンジ、反逆のようなもので、「コンプレックの強い人間に限り、プライドが高い」その深層心理の顕れでもあったことでしょう。これは、現代文の漢字テストへの復讐心もあったやもしれません。
次に、文章表現というものです。レトリック、隠喩や暗喩などの多彩さ、また、逆説なもの言い、描写の巧みさ、まるで、文章を読んでいながらも、映像が浮かびあがってくる表現力といったもの、この延長線に、フランスの作家フローベールに行き着いたわけでもあります。彼の、客観描写の極北、超絶のレアリズムといったものに仏文科で目覚めたわけでもあります。内容よりその表現、一種、文芸の芸術至上主義でもあります。その点で、やはり、フィクションというジャンルでは、平野啓一郎氏が語ってもいますが、日本文学では、その点では、三島由紀夫に並ぶものはいないと思います。
このように、ふしだら、非正統的、悪趣味、衒学的など、将来の、自己の負の経験をいかに、巧みに、表出できる武器を手に入れたい、それを磨きたいの一心で、語彙力と表現力、それの<農場・畑>、それが私の十代後半の読書の試みの修練場所でもありました。従って、そこには、読解力というものは、二の次、付帯的なものに成り下がってもいた、それが、現代文読解能力に結びついてもいなかった原因でもあった。
とりわけ、私は、当時から、そして今でも、ある名文、それは、小説にしろ、評論にしろ、それに遭遇すると、先に進む読みの動作の足を止め、そこから、派生する、様々な自己の経験やら、思想やら人物やらを夢想する気質がどうもあり、それが、読解上、類推の魔として、大学受験時代に、どれだけ足かせとなったことでありましょうか。そういった意味でも、本来の遅読とダブる障壁ともなり、現代文の模試などの点数が伸び悩んだ記憶があります。これも、宿命の読書人の中の、それも異端派のおくれてきた読書人の一つの定めと割りきってもいます。