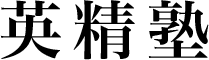コラム
私における第二外国語(フランス語)
「梯子の頂上に登る勇気は貴い、さらにそこから降りて来て再び登り返す勇気は更に貴い」(速水御舟)
「狭き門より入れ。滅びにいたる門は大きくその路は広く、これより入る者多し。」(マタイの福音書)
慶應大学文学部というところは、私大でもユニーク、1年から2年に進むとき初めて専攻学科が選べる仕組みになっていました。今でもそうです。英文・独文・仏文・中文・国文や社会学・心理学・美学・哲学・図書館情報・人間科学と様々なコースが選択できました。初め、英文科を意識してもいましたが、1年の終わりの頃から、仏文科に意識が変わってもきました。それは、大学一年から、海外文学を読み始め、特に、小説ですが、英米仏独露とメジャーな海外文学でも、英米圏よりもフランス文学に取りわけ惹かれるものが多かったこと。そして、もうその頃は一大ブームが去ったあとの現代思想というもの、その総本山がフランスでもあったことがあったでありましょう。サルトル・カミュの実存主義ブームは、とうの昔に過ぎ去った、時代遅れの時代でもありました。でも、私には、「近代日本文学の故郷はフランス文学とロシア文学だ」(横光利一)この言葉が、心に引っかかってもいた頃であります。また、それまで、私が経てきた作家、小林秀雄、森有正、マチネポエティック(加藤周一・福永武彦・中村真一郎)、大江健三郎、辻邦生など、みなフランス系でもありました。また、芸術に代表される、映画・絵画・ファッション・料理など、そうしたジャンルで、将来の仕事柄、また、教養全般を吸収するには、フランス語かな!そういった直感といったものが私の背を押しもしたのだと思います。それにもう一つ、自身の語学という観点からの<かすかな動機>とやらもあったに思われます。
曲がりなりにも、1年近く、この第二外国語をやってもきた。英語は、大学入学時点で、あと独学で何とかなるであろう。このフランス語を、英語レベルまで引き上げた方が賢明なのではないか?
その当時住んでいた横浜市南区内で、英検1級保持者は、100人はいるだろうか、しかし、英検準1級と仏検2級(準1級はなかった)のダブル保持者は、どれほどいようか?10名、いや、数名もいないのではないか?そうです。<語学の二刀流>を意識したのであります。将来の就職という段になった時、就活生の希少価値といいますか、武器といますか、旅行代理店にしろ、商社にしろ、メーカーにしろ、何かと、目立った資格ともなるのではないか、そうしたかすかな目論見といった考えが頭をもたげてきたのです。
それに、慶應の仏文科は、フランス文学、フランス語、フランス文化、こうしたものすべが、バックグラウンドにあり、斜陽にはなりかかってもいても、東大仏文科に行きそびれた(文Ⅲ不合格)者からすれば、やはり、東大・京大の仏文科に継ぐ、私学の看板仏文科の、先頭を走ってもいるという意識もあったやに思われるのです。
60年代の世界的“知”のスターでもあった、実存主義者サルトルが来日した際、権威の象徴東大での講演断り、わざわざ、私学の慶應大学で講演をしたエピソード、また、劇団四季の創設者(浅利慶太・日下武史)、遠藤周作など著名人を輩出し、60年代は、内進で、一番人気があった仏文科、劇作家つかこうへいが、仏文科ヘ進めなかった悔しさで、中退したというエピソードまである、さまざまな伝説を有する仏文科、日が暮れかかる斜陽期ではありましたが、やはり、こうしたものにも惹かれた新人類世代でもあります。
語学の観点に戻りましょう。よく高3年生の勉強の仕方で有名な事例ではありますが、センター試験(共通テスト)の理科の科目で、物理は90点の域に届いている、しかし、化学は、まだ、50点そこそこ、こうしたケースでは、物理の勉強をゼロにしても、化学に時間を費やし、80点、いや、90点をめざす勉強をすべきだというものがあります。そうです、私の語学観とは、これに似てもいると思います。英語は、まずまず、大学受験を契機として、そこそこの域まで来れた、それじゃあ今度は、フランス語を、その域まで数年でレベルアップしてやろう、そうした気概もあったでありましょう。
実は、世にいる、弁護士で公認会計士でもある人、行政書士で司法書士でもある人、様々な資格を有する人というのものは、こうしたメンタルに近いやに思われるのです。こうした実務型の資格を取る人のメンタルは分かりませが、語学の勉強といったもの、これに近いやに思われるのです。
語学に関してですが、高校から大学の第二外国語をものにするか否かの分岐点は、私の考えではありますが、真の英文法というものが身について、それが英語力となった者、いわば、文法というものの大切を痛感し、それを、第二外国語へドッキングしたもの、それにプラスして、動機、目的、興味などが、推進力となり、第二外国語の仏文法なり独文法なりを真摯に学ぼうとする気概が芽生えたものだけでありましょう。今の大学における第二外国語とは、書店で販売されている紙の辞書の如き存在に成り果てもいる。中学や高校で購入しても、すぐ使わなくなってしまう存在に似ています。大方の、大学の第二外国語が1年でオサラバ、挫折する理由は、高校まではガチガチの英文法をやってはきても、大学の第二外国語が、文法より、会話主義、朝日カルチャースクールなどでやる、なんちゃってフランス語やなんちゃって中国語でもあるから、まして、時代は、合理主義・効率主義・GAFA帝国の公用語、英語至上主義の潮流もあり、マイナー言語になれ下がったフランス語・ドイツ語・スペイン語など令和の大学生には魅力の“み”の字も感じない、見向きもされないのは必定でもありましょう。これは、大学で文学部という名称の学部がどんどん姿を消してもいる状況が証明してもいましょう。これは、日本的レベルでは、全国の都市化、東京化であり、グローバル的次元では、世界のアメリカ化、ニューヨーク化でもありましょうか?文化の差異・豊饒なる文化・文化の多様性の消滅の表徴でもありましょう。文学部廃止は、書店廃業とパラレルの関係なのです。これは、2007年に、早稲田大学文学部から派生して生まれた文化構想学部の偏差値が、今や、文学部を凌ぐ昨今の現象が証明済である。イトーヨーカ堂の子会社から生まれたセブイレブンのようなものです。
恐らく、この令和の時代に、私が高校生であれば、正直申して、仏文科へは進ではいないやもしれません。
それと、私の昭和の末に仏文科へ進んだ状況は違うのであります。江戸の終わり、天保頃までは、オランダ語を学んだように、維新前後(平成)、明治(令和)には英語を学んだ開花期の人々と同じでもありましょう。だが、福澤諭吉が、適塾でオランダ語を習得し、幕末の横浜でその語が一切通用せず、時代は、世界は英語の時代だと瞠目しながも、20代で再度英語を学び直した福澤諭吉の語学取得へのambitionというものは、時空を超えて学ぶに値する心持というものである。
「狭き門より入れ。滅びにいたる門は大きくその路は広く、これより入る者多し。」(マタイの福音書)
慶應大学文学部というところは、私大でもユニーク、1年から2年に進むとき初めて専攻学科が選べる仕組みになっていました。今でもそうです。英文・独文・仏文・中文・国文や社会学・心理学・美学・哲学・図書館情報・人間科学と様々なコースが選択できました。初め、英文科を意識してもいましたが、1年の終わりの頃から、仏文科に意識が変わってもきました。それは、大学一年から、海外文学を読み始め、特に、小説ですが、英米仏独露とメジャーな海外文学でも、英米圏よりもフランス文学に取りわけ惹かれるものが多かったこと。そして、もうその頃は一大ブームが去ったあとの現代思想というもの、その総本山がフランスでもあったことがあったでありましょう。サルトル・カミュの実存主義ブームは、とうの昔に過ぎ去った、時代遅れの時代でもありました。でも、私には、「近代日本文学の故郷はフランス文学とロシア文学だ」(横光利一)この言葉が、心に引っかかってもいた頃であります。また、それまで、私が経てきた作家、小林秀雄、森有正、マチネポエティック(加藤周一・福永武彦・中村真一郎)、大江健三郎、辻邦生など、みなフランス系でもありました。また、芸術に代表される、映画・絵画・ファッション・料理など、そうしたジャンルで、将来の仕事柄、また、教養全般を吸収するには、フランス語かな!そういった直感といったものが私の背を押しもしたのだと思います。それにもう一つ、自身の語学という観点からの<かすかな動機>とやらもあったに思われます。
曲がりなりにも、1年近く、この第二外国語をやってもきた。英語は、大学入学時点で、あと独学で何とかなるであろう。このフランス語を、英語レベルまで引き上げた方が賢明なのではないか?
その当時住んでいた横浜市南区内で、英検1級保持者は、100人はいるだろうか、しかし、英検準1級と仏検2級(準1級はなかった)のダブル保持者は、どれほどいようか?10名、いや、数名もいないのではないか?そうです。<語学の二刀流>を意識したのであります。将来の就職という段になった時、就活生の希少価値といいますか、武器といますか、旅行代理店にしろ、商社にしろ、メーカーにしろ、何かと、目立った資格ともなるのではないか、そうしたかすかな目論見といった考えが頭をもたげてきたのです。
それに、慶應の仏文科は、フランス文学、フランス語、フランス文化、こうしたものすべが、バックグラウンドにあり、斜陽にはなりかかってもいても、東大仏文科に行きそびれた(文Ⅲ不合格)者からすれば、やはり、東大・京大の仏文科に継ぐ、私学の看板仏文科の、先頭を走ってもいるという意識もあったやに思われるのです。
60年代の世界的“知”のスターでもあった、実存主義者サルトルが来日した際、権威の象徴東大での講演断り、わざわざ、私学の慶應大学で講演をしたエピソード、また、劇団四季の創設者(浅利慶太・日下武史)、遠藤周作など著名人を輩出し、60年代は、内進で、一番人気があった仏文科、劇作家つかこうへいが、仏文科ヘ進めなかった悔しさで、中退したというエピソードまである、さまざまな伝説を有する仏文科、日が暮れかかる斜陽期ではありましたが、やはり、こうしたものにも惹かれた新人類世代でもあります。
語学の観点に戻りましょう。よく高3年生の勉強の仕方で有名な事例ではありますが、センター試験(共通テスト)の理科の科目で、物理は90点の域に届いている、しかし、化学は、まだ、50点そこそこ、こうしたケースでは、物理の勉強をゼロにしても、化学に時間を費やし、80点、いや、90点をめざす勉強をすべきだというものがあります。そうです、私の語学観とは、これに似てもいると思います。英語は、まずまず、大学受験を契機として、そこそこの域まで来れた、それじゃあ今度は、フランス語を、その域まで数年でレベルアップしてやろう、そうした気概もあったでありましょう。
実は、世にいる、弁護士で公認会計士でもある人、行政書士で司法書士でもある人、様々な資格を有する人というのものは、こうしたメンタルに近いやに思われるのです。こうした実務型の資格を取る人のメンタルは分かりませが、語学の勉強といったもの、これに近いやに思われるのです。
語学に関してですが、高校から大学の第二外国語をものにするか否かの分岐点は、私の考えではありますが、真の英文法というものが身について、それが英語力となった者、いわば、文法というものの大切を痛感し、それを、第二外国語へドッキングしたもの、それにプラスして、動機、目的、興味などが、推進力となり、第二外国語の仏文法なり独文法なりを真摯に学ぼうとする気概が芽生えたものだけでありましょう。今の大学における第二外国語とは、書店で販売されている紙の辞書の如き存在に成り果てもいる。中学や高校で購入しても、すぐ使わなくなってしまう存在に似ています。大方の、大学の第二外国語が1年でオサラバ、挫折する理由は、高校まではガチガチの英文法をやってはきても、大学の第二外国語が、文法より、会話主義、朝日カルチャースクールなどでやる、なんちゃってフランス語やなんちゃって中国語でもあるから、まして、時代は、合理主義・効率主義・GAFA帝国の公用語、英語至上主義の潮流もあり、マイナー言語になれ下がったフランス語・ドイツ語・スペイン語など令和の大学生には魅力の“み”の字も感じない、見向きもされないのは必定でもありましょう。これは、大学で文学部という名称の学部がどんどん姿を消してもいる状況が証明してもいましょう。これは、日本的レベルでは、全国の都市化、東京化であり、グローバル的次元では、世界のアメリカ化、ニューヨーク化でもありましょうか?文化の差異・豊饒なる文化・文化の多様性の消滅の表徴でもありましょう。文学部廃止は、書店廃業とパラレルの関係なのです。これは、2007年に、早稲田大学文学部から派生して生まれた文化構想学部の偏差値が、今や、文学部を凌ぐ昨今の現象が証明済である。イトーヨーカ堂の子会社から生まれたセブイレブンのようなものです。
恐らく、この令和の時代に、私が高校生であれば、正直申して、仏文科へは進ではいないやもしれません。
それと、私の昭和の末に仏文科へ進んだ状況は違うのであります。江戸の終わり、天保頃までは、オランダ語を学んだように、維新前後(平成)、明治(令和)には英語を学んだ開花期の人々と同じでもありましょう。だが、福澤諭吉が、適塾でオランダ語を習得し、幕末の横浜でその語が一切通用せず、時代は、世界は英語の時代だと瞠目しながも、20代で再度英語を学び直した福澤諭吉の語学取得へのambitionというものは、時空を超えて学ぶに値する心持というものである。