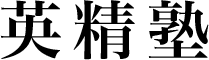コラム
①質か量か?~努力を介して~
前回に言及した心臓内科医三角和雄の「量のないところに質はない」という言葉、これは、熟考に値する命題を秘めてもいると感じ入って、私の思考は、この<質と量>というテーマに向けて展開し始めた。
まず、質と量、それは、勉強であれ仕事であれ、その師弟関係でよく議論されるものである。
昭和の学校における部活の練習であれば、スポ根アニメに代表れるように、まず、練習の量が第一でもあった。質は、ある意味、二の次、三の次とも思われていた節がある。一方、平成を経て、令和の部活の練習であれば、まず、体罰や暴言が厳禁なように、まず、練習の質が最優先されもする。これは、科学の進歩、スポーツ科学の進展、それは、早稲田の人間科学部というアスリートに代表される学部の登場にも象徴されようが、まず、科学的根拠、エヴィデンスなど、まず行動する前に考えるという心構えが第一ともされる趨勢からも読み取れよう。Z世代が、内向き、管理職になりたがらない、「行動する前に考えよ」という情報過多社会により生じた慎重派気質にも反映されているようだ。まず、先が見えてしまうメンタルが特徴でもあろうか。令和、21世紀は、あらゆる領域で、科学に裏打ちされた質というものがまずありきというのが、大前提、原則ともなっている時代ではある。この新しい気質が、タイパ、コスパ、サブスクなどの流行に証明されてもいよう。その奥底に見え隠れす“質”の優先メンタルは、実は、薄っぺらい“質”のものに過ぎない。
これは、スポーツだけではなく、料理の世界を見渡してもそうである。『堀江貴文VS鮨職人 鮨屋に修業は必要か?』(ぴあ)という興味深い本があるが、そこで、ホリエモンこと、堀江貴文は、学びにおける質と量という、悩ましい問いを投げかけてもいる。
現代では、寿司学校なるものがあり、6カ月の授業料80万円で、従来の寿司職人が、3年から10年近く修業して身に付ける、魚の見極め方、魚のさばき方、シャリの扱い方、寿司の握り方など、全ての技能がマスターできるルートがあるそうである。こうした学校で、半年近く学び、後の半年で、店を開店させる準備をしたり、海外の寿司レストランに就職する、脱サラ組が少なくないそうである。この職人世界にも、修業の質と量のテーマが浮かびあがってもくる。
しかし、この寿司職人の質か量かの線引きは、<場数を踏む>という言葉からもわかるように、心臓外科医・内科医には、どうも当てはまりそうもない。また、学校の教師に関しても、新米の教師と中堅の教師の違いでは、量という経験がなければ、一人前とはなれない世界である。私の好きな言葉、「医師は患者によって作られる、教師もまた生徒によって作られる」(伊藤和夫)これは、食べ物、食材を扱う、料理人やパティシエと生の人間と対峙する医師・教師との違いでもあろう。但し、サービス業に携わる者は、「お客様に学ぶ」(伊藤雅俊)という名言もあることを忘れてはいけない。この真意、寿司学校出身の新米寿司職人は、肝に銘ずべき言葉でもあろう。
ここで、元巨人軍監督原辰徳の言葉、「多摩川グラウンドの1000本ノックよりも、日本シリーズでさばく一球のゴロがどれほど私を成長させてくれたことだろうか!」これが、大いに、その分岐点、分水嶺ともなる真実を言い表している言葉ともなろう。
量であれ、質であれ、まず頭で考えながら、その学びの過程へ、強烈なる意識を持ち、その意識のレールを邁進することが肝要ということでもある。
ここで、質と量という命題を意識する時、まず、もう一つの概念でもある、努力という角度から、質と量を照射する視点も必要となってこよう。その二つの背後、根底には努力という自我意識があるからである。
これは、アスリートなどが、よく口にすることばであるが、「努力は報われる」というものがある。これなどは、金メダル、優勝、世界記録・日本記録など、成功者が吐く場合が多い。敗者は、この言葉に、難癖などをつけたり、また、口になどしない。
「努力に勝る天才なし」というもの、「天才とは努力する才のことだ」というもの、こうした人口に膾炙した名言を聞いて、一般人は、努力を“量”と勘違いしやすい。確かに、凡人には努力は、月並みな意味で、量と同義に映る。その成功した者の背後に潜む、素質、環境、運などが介在している真理を忘れがちでもある。これらの名言をフォローする、補う、異議申し立てする弁として、林修氏などが口にする「努力とは、適切な量を、適切な方向へ、適切な方法で行った時に、報われる」というものがある。これは、ある意味、質と量というものの弁証法的帰結点としての、正確な意味で、努力の定義ではある。いや、上記の二つの言葉への方便でもあろう。ここにも、やはり、ものごとの<質か量か>という天秤的裁量などの判定は難しい。では、次回、この自身を成長させてもくれる<父と母>とも喩えられる<質と量>との関係を深堀してゆきたいと思う。
まず、質と量、それは、勉強であれ仕事であれ、その師弟関係でよく議論されるものである。
昭和の学校における部活の練習であれば、スポ根アニメに代表れるように、まず、練習の量が第一でもあった。質は、ある意味、二の次、三の次とも思われていた節がある。一方、平成を経て、令和の部活の練習であれば、まず、体罰や暴言が厳禁なように、まず、練習の質が最優先されもする。これは、科学の進歩、スポーツ科学の進展、それは、早稲田の人間科学部というアスリートに代表される学部の登場にも象徴されようが、まず、科学的根拠、エヴィデンスなど、まず行動する前に考えるという心構えが第一ともされる趨勢からも読み取れよう。Z世代が、内向き、管理職になりたがらない、「行動する前に考えよ」という情報過多社会により生じた慎重派気質にも反映されているようだ。まず、先が見えてしまうメンタルが特徴でもあろうか。令和、21世紀は、あらゆる領域で、科学に裏打ちされた質というものがまずありきというのが、大前提、原則ともなっている時代ではある。この新しい気質が、タイパ、コスパ、サブスクなどの流行に証明されてもいよう。その奥底に見え隠れす“質”の優先メンタルは、実は、薄っぺらい“質”のものに過ぎない。
これは、スポーツだけではなく、料理の世界を見渡してもそうである。『堀江貴文VS鮨職人 鮨屋に修業は必要か?』(ぴあ)という興味深い本があるが、そこで、ホリエモンこと、堀江貴文は、学びにおける質と量という、悩ましい問いを投げかけてもいる。
現代では、寿司学校なるものがあり、6カ月の授業料80万円で、従来の寿司職人が、3年から10年近く修業して身に付ける、魚の見極め方、魚のさばき方、シャリの扱い方、寿司の握り方など、全ての技能がマスターできるルートがあるそうである。こうした学校で、半年近く学び、後の半年で、店を開店させる準備をしたり、海外の寿司レストランに就職する、脱サラ組が少なくないそうである。この職人世界にも、修業の質と量のテーマが浮かびあがってもくる。
しかし、この寿司職人の質か量かの線引きは、<場数を踏む>という言葉からもわかるように、心臓外科医・内科医には、どうも当てはまりそうもない。また、学校の教師に関しても、新米の教師と中堅の教師の違いでは、量という経験がなければ、一人前とはなれない世界である。私の好きな言葉、「医師は患者によって作られる、教師もまた生徒によって作られる」(伊藤和夫)これは、食べ物、食材を扱う、料理人やパティシエと生の人間と対峙する医師・教師との違いでもあろう。但し、サービス業に携わる者は、「お客様に学ぶ」(伊藤雅俊)という名言もあることを忘れてはいけない。この真意、寿司学校出身の新米寿司職人は、肝に銘ずべき言葉でもあろう。
ここで、元巨人軍監督原辰徳の言葉、「多摩川グラウンドの1000本ノックよりも、日本シリーズでさばく一球のゴロがどれほど私を成長させてくれたことだろうか!」これが、大いに、その分岐点、分水嶺ともなる真実を言い表している言葉ともなろう。
量であれ、質であれ、まず頭で考えながら、その学びの過程へ、強烈なる意識を持ち、その意識のレールを邁進することが肝要ということでもある。
ここで、質と量という命題を意識する時、まず、もう一つの概念でもある、努力という角度から、質と量を照射する視点も必要となってこよう。その二つの背後、根底には努力という自我意識があるからである。
これは、アスリートなどが、よく口にすることばであるが、「努力は報われる」というものがある。これなどは、金メダル、優勝、世界記録・日本記録など、成功者が吐く場合が多い。敗者は、この言葉に、難癖などをつけたり、また、口になどしない。
「努力に勝る天才なし」というもの、「天才とは努力する才のことだ」というもの、こうした人口に膾炙した名言を聞いて、一般人は、努力を“量”と勘違いしやすい。確かに、凡人には努力は、月並みな意味で、量と同義に映る。その成功した者の背後に潜む、素質、環境、運などが介在している真理を忘れがちでもある。これらの名言をフォローする、補う、異議申し立てする弁として、林修氏などが口にする「努力とは、適切な量を、適切な方向へ、適切な方法で行った時に、報われる」というものがある。これは、ある意味、質と量というものの弁証法的帰結点としての、正確な意味で、努力の定義ではある。いや、上記の二つの言葉への方便でもあろう。ここにも、やはり、ものごとの<質か量か>という天秤的裁量などの判定は難しい。では、次回、この自身を成長させてもくれる<父と母>とも喩えられる<質と量>との関係を深堀してゆきたいと思う。