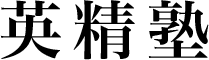コラム
➁質か量か?~食を介して~
質と量、これを食事という観点から述べるとします。
典型的な例は、一人前4万円もする、銀座の名店すきやばし次郎の鮨とグルメ回転寿司銚子丸とを同じネタ12貫8000円を食したとしよう。このケース、前者は、後者の5倍うまいか、これは個人それぞれでもあろうが、せいぜい2倍強といったところだろうか。10代の若者には、5回銚子丸でごちそうになった方がいいという者が9割以上、50代以上でも、5割前後は5回がいいと応じるのではないでしょうか。すきやばし次郎の方を選んだ高校生でも、その父親でも、一回はその高級寿司とやらを食してみたいといった体験的欲望がそう返答させてもいよう、それに、自腹で食うとなれば、グルメ回転寿司を次回から選ぶことは、資産家やセレブでもない限り、自明である。
実は、この食による、質か量といった判断目分量といったものは、学びにおいても根底では、つながってもいるような気がしてならない。その教科のカリスマ予備校講師から、200人教室、また、ネットで授業を受ける方が伸びるか、また、親切にして、しかも教えることに情熱を持つ大学生から、マンツーマンの個別授業を受けるか、その関係のケースに似てなくもない。前者は、知力を“持っている生徒”ならOK,後者は、“持っていない生徒”向けとされる所以でもある。あの、ビリギャルは、集団で、あの坪田先生の授業を受けていたらどうであったことだろうか?興味深い問いではある。
個人観なのだが、食に関しては、金を出せば、高額ならば、うまいのは当然ともいえるが、真の意味で、うまいという私的基準は、味と量と値段という、レーダーチャート的図形で、綺麗な正三角形を描くものである。
では、この質と量という観点から学びというものを考えてみよう。
まず、質は微分のベクトルで、量は積分のベクトルで、それぞれ、満足という、主観的結節点に帰着する。それの満足感は、食に対する、個人の旨いか・不味いか、味覚の感性の基準にも依る。
超一流講師に、英語を学ぶ、わかった!一方、二流講師や凡庸な教師に、英語を学ぶ、自身で、自習室や図書館などで、授業の不明な箇所を演習につぐ演習をする。これで、定着したような気分になる!これ、教えない塾で有名な武田塾に該当する。指定参考書を与え、習熟(?)するまで、個別の机に向かわせる方式である。
大方、カリスマ英語講師関正生のネットなどの授業を観ても、その項目を深く理解する生徒は、参考書や学校のテキストで、その内容を思い出したり、自己学習を欠かさないがゆえ、英語が伸びる。その“質”とも言えるすばらしい講義を聴いても、やはり、量へと踏み出さない者は、たいてい伸び悩む。ここにも、「予備校に頼る者は失敗する。予備校を利用する者は成功する。」(飯田康夫)の真理が該当する。
その項目の本質を、そのコアにまで、多くの演習などをして、到達する者は、視力でいう、1.5から1.2までの視力には及ばす、せいぜい、1.0くらいにしかその単元・内容が見えてもこない。いくら量を積んでも、準秀才(MARCHレベル)は、その本質がつかめない。これと比類するものは、歴史教科の暗記主義派と因果関係派(ながれで理解する派)の違いにおおいに現れる傾向である。実は、令和の現代、英検第一主義の英語学習の風潮は、まさしく、その英語の単元が、“視力1.0”にも満たない中高生がザラにいる元凶の最大の責任者でもある。分かった気になって、X級合格が、恐らく7~8割以上と推察される。上っ面だけの量をこなす努力、いや、自己満足で、それを努力と思い込んでいる、過信ともいっていい空疎なる努力と言える。こうした行為などは、量も質も両面で超不足してもいる学習態度というものである。
歴史教科に見受けられる学習、一問一答を、英単語集を暗記するが如く、丸覚えする量派は、永遠に、カリスマ日本史講師伊藤賀一などの授業をネットで勉強し、流れのなかで知識を覚えてゆく派には断然叶わない。
ここでどういう命題が浮上するのか?
凡人向けの定理である。ある一点、何らかのコア、それを質とでもいっていいが、それがなければ、いくら量を積んだところで、成績や実力など向上しないという真実である。
私から言わせてもらえば、心臓内科医三角和雄氏の「量がなければ質もない」という発言は、ギフティッドの者、秀才以上の部族の教訓でもある。
量を積めば積むほど、一般的には、その学びの知識や技能は向上するというのが、月並みな域での該当法則でもある。凡夫は、いくら量を積んでもある次元以上には到達もしない。三角氏のように、医師のスタートラインに、自己流の、確信的な質というものが、まず、あれば、ちょうど、真珠の養殖における、アコウ貝の殻内に、“核”をまず入れるように、貝の内部に種漬けする、その種を有していれば、年月とともに見事な真珠となる。問題なのが、その種ともなる核、いわゆる、質が問題なのだ。これなくして、学びの大成はない。この質ともいえる、種付けの役割が、良き教師・講師であり、良き授業であり、良き参考書でもある。生の人間、映像授業、本というように、その順序でリアル度が薄れるにつれて、その本質は伝わりにくくなるものである。今や、SNSのYouTube授業やオンライン授業が花盛りなのだが、その学びの死角・盲点に、世の中高生や親御さんたちは、気づかないものだ。ここに、禅でいう、面授面受という秘儀が、その意義というものが、想起できる者は、まだましである。この観点から弊著『反デジタル考』をしたためた次第でもある。
子どもの食に関する、好き嫌いという次元で申し上げれば、野菜や生魚などが嫌いな子どもは、大方、質の悪い、鮮度の劣る、それに付随して不味いものをあてがわれた傾向が高い。質は二流以下、しかも、味も二流以下のものが大量に毎日、毎週あてがわれる。旨さの分からぬ料理の<量の雨嵐攻撃>でもある。嫌いになるも無理はない。その食が嫌いな子どもに、超1流の“トマトや鮨”などを経験させれば、即、舌は贅沢になるにしろ、その食い物を進んで食するようになるはずである。質を知らない者は、量だけでは、その対象の本質はわからない。その、一流の質を経験したものは、その対象へ前向きに踏み出す、もうしめたものだ、量に量を重ねる鍛錬を、鍛錬とも思わずに、量という経験を積んでもゆく。野球にしろ、サッカーにしろ、プロになって大成するアスリートは、高校生の頃に、名監督、即ち、質というものを経験しているものである。その、また逆も同義であろう。
以上の、質と量の切り口は、実は、演繹法と帰納法に収斂してくるというのが、日ごろの、私なりの、<学びと教え>における仮説でもある。次回は、この<質と量=演繹法と帰納法>という観点から考えてみたい。
典型的な例は、一人前4万円もする、銀座の名店すきやばし次郎の鮨とグルメ回転寿司銚子丸とを同じネタ12貫8000円を食したとしよう。このケース、前者は、後者の5倍うまいか、これは個人それぞれでもあろうが、せいぜい2倍強といったところだろうか。10代の若者には、5回銚子丸でごちそうになった方がいいという者が9割以上、50代以上でも、5割前後は5回がいいと応じるのではないでしょうか。すきやばし次郎の方を選んだ高校生でも、その父親でも、一回はその高級寿司とやらを食してみたいといった体験的欲望がそう返答させてもいよう、それに、自腹で食うとなれば、グルメ回転寿司を次回から選ぶことは、資産家やセレブでもない限り、自明である。
実は、この食による、質か量といった判断目分量といったものは、学びにおいても根底では、つながってもいるような気がしてならない。その教科のカリスマ予備校講師から、200人教室、また、ネットで授業を受ける方が伸びるか、また、親切にして、しかも教えることに情熱を持つ大学生から、マンツーマンの個別授業を受けるか、その関係のケースに似てなくもない。前者は、知力を“持っている生徒”ならOK,後者は、“持っていない生徒”向けとされる所以でもある。あの、ビリギャルは、集団で、あの坪田先生の授業を受けていたらどうであったことだろうか?興味深い問いではある。
個人観なのだが、食に関しては、金を出せば、高額ならば、うまいのは当然ともいえるが、真の意味で、うまいという私的基準は、味と量と値段という、レーダーチャート的図形で、綺麗な正三角形を描くものである。
では、この質と量という観点から学びというものを考えてみよう。
まず、質は微分のベクトルで、量は積分のベクトルで、それぞれ、満足という、主観的結節点に帰着する。それの満足感は、食に対する、個人の旨いか・不味いか、味覚の感性の基準にも依る。
超一流講師に、英語を学ぶ、わかった!一方、二流講師や凡庸な教師に、英語を学ぶ、自身で、自習室や図書館などで、授業の不明な箇所を演習につぐ演習をする。これで、定着したような気分になる!これ、教えない塾で有名な武田塾に該当する。指定参考書を与え、習熟(?)するまで、個別の机に向かわせる方式である。
大方、カリスマ英語講師関正生のネットなどの授業を観ても、その項目を深く理解する生徒は、参考書や学校のテキストで、その内容を思い出したり、自己学習を欠かさないがゆえ、英語が伸びる。その“質”とも言えるすばらしい講義を聴いても、やはり、量へと踏み出さない者は、たいてい伸び悩む。ここにも、「予備校に頼る者は失敗する。予備校を利用する者は成功する。」(飯田康夫)の真理が該当する。
その項目の本質を、そのコアにまで、多くの演習などをして、到達する者は、視力でいう、1.5から1.2までの視力には及ばす、せいぜい、1.0くらいにしかその単元・内容が見えてもこない。いくら量を積んでも、準秀才(MARCHレベル)は、その本質がつかめない。これと比類するものは、歴史教科の暗記主義派と因果関係派(ながれで理解する派)の違いにおおいに現れる傾向である。実は、令和の現代、英検第一主義の英語学習の風潮は、まさしく、その英語の単元が、“視力1.0”にも満たない中高生がザラにいる元凶の最大の責任者でもある。分かった気になって、X級合格が、恐らく7~8割以上と推察される。上っ面だけの量をこなす努力、いや、自己満足で、それを努力と思い込んでいる、過信ともいっていい空疎なる努力と言える。こうした行為などは、量も質も両面で超不足してもいる学習態度というものである。
歴史教科に見受けられる学習、一問一答を、英単語集を暗記するが如く、丸覚えする量派は、永遠に、カリスマ日本史講師伊藤賀一などの授業をネットで勉強し、流れのなかで知識を覚えてゆく派には断然叶わない。
ここでどういう命題が浮上するのか?
凡人向けの定理である。ある一点、何らかのコア、それを質とでもいっていいが、それがなければ、いくら量を積んだところで、成績や実力など向上しないという真実である。
私から言わせてもらえば、心臓内科医三角和雄氏の「量がなければ質もない」という発言は、ギフティッドの者、秀才以上の部族の教訓でもある。
量を積めば積むほど、一般的には、その学びの知識や技能は向上するというのが、月並みな域での該当法則でもある。凡夫は、いくら量を積んでもある次元以上には到達もしない。三角氏のように、医師のスタートラインに、自己流の、確信的な質というものが、まず、あれば、ちょうど、真珠の養殖における、アコウ貝の殻内に、“核”をまず入れるように、貝の内部に種漬けする、その種を有していれば、年月とともに見事な真珠となる。問題なのが、その種ともなる核、いわゆる、質が問題なのだ。これなくして、学びの大成はない。この質ともいえる、種付けの役割が、良き教師・講師であり、良き授業であり、良き参考書でもある。生の人間、映像授業、本というように、その順序でリアル度が薄れるにつれて、その本質は伝わりにくくなるものである。今や、SNSのYouTube授業やオンライン授業が花盛りなのだが、その学びの死角・盲点に、世の中高生や親御さんたちは、気づかないものだ。ここに、禅でいう、面授面受という秘儀が、その意義というものが、想起できる者は、まだましである。この観点から弊著『反デジタル考』をしたためた次第でもある。
子どもの食に関する、好き嫌いという次元で申し上げれば、野菜や生魚などが嫌いな子どもは、大方、質の悪い、鮮度の劣る、それに付随して不味いものをあてがわれた傾向が高い。質は二流以下、しかも、味も二流以下のものが大量に毎日、毎週あてがわれる。旨さの分からぬ料理の<量の雨嵐攻撃>でもある。嫌いになるも無理はない。その食が嫌いな子どもに、超1流の“トマトや鮨”などを経験させれば、即、舌は贅沢になるにしろ、その食い物を進んで食するようになるはずである。質を知らない者は、量だけでは、その対象の本質はわからない。その、一流の質を経験したものは、その対象へ前向きに踏み出す、もうしめたものだ、量に量を重ねる鍛錬を、鍛錬とも思わずに、量という経験を積んでもゆく。野球にしろ、サッカーにしろ、プロになって大成するアスリートは、高校生の頃に、名監督、即ち、質というものを経験しているものである。その、また逆も同義であろう。
以上の、質と量の切り口は、実は、演繹法と帰納法に収斂してくるというのが、日ごろの、私なりの、<学びと教え>における仮説でもある。次回は、この<質と量=演繹法と帰納法>という観点から考えてみたい。