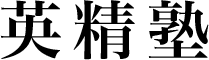コラム
⑧質か量か?~桐蔭学園とダイエー~
昭和50年代から平成10年代にかけて、東大合格者が、全国ベスト10~20に入っていた、神奈川のマンモス進学校桐蔭学園を例に挙げよう。
この、過去において、一学年1500名も抱えた進学校は、そもそも分母が巨大、分子の東大合格者が100名近くであっても、内実、優秀な進学校とも敢えていえない体質があった。因に、弊塾の創設年、1997年から1998年は、100名近くあった桐蔭は、1999年以降、50名前後に激減し、その後右下がりとなってゆく。この頃の弊塾の桐蔭生は、出来がよかった。皆、栄光や浅野を落ちた、桐蔭上層部の生徒でもあった。その後、2000年代に入ると、彼らの質というか、学力の底辺にある、知力みたいないものが劣化していく様は、その後の桐蔭の行く末を暗示してもいた。
神奈川県の、スポーツでも名を馳せた進学校は、創立者で、校長にして、理事長でもあった鵜養昇氏がいればの、学業の全盛期の文武両立の学校でもあった。まるで、平清盛が存命中、権勢をふるった平家、織田信長が、経済を主眼として絶対的でもあった織田家の如きものであった。このカリスマ鵜養理事長亡きあとの、桐蔭学園は、学業に関しては、準進学校になれ下がった感が否めない。平成の後半から、公立は嫌だが、学力がいまいちの小学生を引き受ける、みたくれ進学校になれ下がってしまった。敢えて、独立させてもいる桐蔭中等は、その没落の宿命をかろうじて回避さけてはいるが、今でも凡庸な進学校には変わりなはい。
この桐蔭学園、昭和の高度成長に出没した、大手スーパーに似ていなくもない。
ダイエー、イトーヨーカド―、西友などである。当時は、す~と現れ、ぱ~と消える業種と揶揄されたが、今や、平成から令和にかけて、それが的中してもいる。この桐蔭学園は、進学校の量販店なのだ。百貨店ではない。平成から台頭してきた渋谷学園系{渋渋と幕張}は、この桐蔭学園とは対照的でもあろう。
まだ、子どもの数、人口の数も右肩上がりまでいかなくても、消費者は、多くいた。ユニクロ、青山、アオキなどの紳士服チェーン店や家電量販店からドラッグストアーなどライバル店が、カテゴリーキラーとしては、勢力を増してもいなかった。戦国大名の武田、今川、北条の如き存在でもあった。それが、失われた30年の年月のうちに、量販店、いわゆるスーパーという業態は、「何でもあるが、欲しいものがない」という存在になれ下がった。情報化社会の目の肥えた消費者の台頭である。一方、伊勢丹、三越、高島屋などは、「欲しいものだらけだが、手が届かない」とも思われ、消費者が敬遠する存在として、ネット社会の中、斜陽産業化してもゆく。だが、何とかそのブランド価値は維持してもいる。経済の低迷と衣服などに関心がない、お金をかけない、ブランドにこだわらない、安くて質がいいユニクロに、消費がファッション観念を完全に変えられた。よって、スーパーの衣料品は、見向きもされなくなり、食品系スーパー、ライフ、サミット、OKなど勢力にGMSは駆逐されてもゆくというのが、平成後期の流通業の勢力図でもあったであろう
こうした、ダイエーなどの量販店、いや、このダイエーの創業者中内功にキャラがとてもよく似ている桐蔭学園の鵜養昇氏が、かつて次の様な言葉を吐いていたことが記憶にある。
「うちにくる生徒は、神奈川における栄光学園、聖光学院、浅野学園などに落ちた者です。彼らは、やはり、神奈川の男子進学校御三家に入れなかった、準秀才の連中である。彼らを、いかに、東大や、一橋や東工大、せめて、早慶に入れさせるか、それは、量につぐ量で、徹底的に、数をこなさせる方式で、演習につぐ演習で、6年後、栄光などの生徒にためを張れる域にまでもってゆく、それが、我が校のやり方です」
このインタビューを、ある雑誌記事か、彼の著作物か何かで観て、まさしく、昭和のスポ根アニメの練習手法を想起してしまった。才能も能力もない者は、ただ量につぐ量をこなして、才を持つ、質の集団に立ち向かってゆく、そして勝てと命じているようなものである。また、ドラフトでも嫌厭される弱小球団が、無名の選手を育成し、その後、日本一になる球団を彷彿されてもくる。
子どもの数がまだかろうじて多い、現今の少子化社会の前夜である。また、情報化社会の黎明期でもある。教育や勉学の知識が、『ドラゴン桜』『ビリギャル』『下剋上受験』などまだ出現する以前である。このマンモス校、これらが僥倖となっていた。生徒、親御さん以上に、情報量が、学校サイド、塾・予備校サイドにあった時代でもある。昭和から平成前半にかけて、勉学における千本ノック方式、「才能も、素質も、能力もない奴は、学校から課された宿題につぐ宿題で、その科目の成績を伸ばせ!」方式が通用した。生徒も親御さんも、昭和の時代、体罰をされても、「お前が悪い!」と容認されていたように、黙って、学校側の地獄の宿題を、まるで、犬の躾けの如くに、課題をもくもくとこなした。事実、弊塾で、中1から入塾して、中3から高1にかけて、この桐蔭学園の生徒がどれほど辞めていったことであろうか!理由は、「先生!学校の宿題が山ほどあって、塾などに通っていたら、宿題ができないんです!」と、親子そろって、半べそをかいて、退塾する者が大勢いた。また、桐蔭学園では、何故か、当時、塾厳禁派の学校でもあった。塾には、通うなという号令が出されていた。あくまでも、弊塾の桐蔭製生に関してだが。それは、穿った見方をすれば、まるで、江戸時代の鎖国のように、、外国の世界を見てはならぬ!というに等しい魂胆があったように感じた。大手の予備校、また、塾の優秀な講師の授業を目にした彼らは、自校の教師の教える力量がないことに気づく、それを回避するためと、当時の私は感じたものだ。この学校、準秀才以下を、悪しき帰納法で、徹底的に鍛え上げる、ある意味、勉学の軍隊方針もであった。
私は、よく、弊塾の生徒に、「塾、予備校に通うな!」と語る学校、先生がいることは、学びの鎖国校であると語ったものである。自校の先生の教え方のスキルを比較され、自校の先生の質の低さに気づかれないように、“塾に通うな令”がだされてもいたように思われたからだ。これは、邪推でも、勘繰りでもない、正鵠を得たものだと確信してもいた。今でも、そう思う。予備校、塾講師への、偏見ではなく、嫉妬の目線である。平成から、学校教師の質の低下と塾・予備校の講師のスキルの際立った上昇とSNS社会の到来で、学びの鎖国観など、尊王攘夷などなき明治の世の中、鬼畜米英など微塵もない戦後昭和の社会、隔世の感がある。その典型は、例えば、英語でいえば、スタサプの関正生である。彼の弁の立つ、立て板に水にように流暢に、英語の本質を解説・説明するカリスマ講師の登場で、神奈川県の中高一貫校でも、そのスタサプを見て、その内容が小テストでだされるとも語った教え子が少なくない。そうした学校は、英語教師でも、関正生に、白旗を挙げた如しである。こうした学校は、桐蔭の二の舞ともなる。
こうしたご時世、平成前期まで、超(?)進学校、いや、バブルの進学校が、まるで、ダイエーの如く薄利多売で、消滅していったように、今では、この神奈川の進学校、ラグビーや野球でこそ、名門校ではあるが、勉学に関しては、もはやそうではなくなった。子供が多かった頃に、体質改善をしなかったつけが、平成後半にまわてもっきた。いや、ダイエーの中内功というカリスマに、ノンと言えなかったように、鵜川昇理事長に、諫める提案ができなかった悲劇かもしれない。いや、彼の手法を祖法のように、堅持したつけが回ってきたのかもしれない。
余談ながら、現在の、桐蔭学園は、アクティブラーニング授業、探求型授業、キャリア授業の三本柱であるともいう。しかし、この三本柱で学校運営をやってゆける学校は、秀才以上が、半数以上いなければ成立しない理想形のものだ。文科省が言う、英語教育の、読み・書き・話し・聞くといった四技能を、公立中学校、標準的公立高校で同時並行で行うが如しである。理想と現実を峻別できない、現場を知らない蒙昧なる教育方針でもある。英語なら、まず、文法を下敷きに、徹敵的に読みを鍛える、その後、書きに以降する。そのあと、聞き、そして話すという順序で、語学は、12才以降教えるのが私の思念である。
準秀才校の鉄則なのだが、まず、英数国理社の学力の構築が先にありき、である。これは、横浜創英高校を、短期で辞任した、『学校の「当たり前」をやめた。』で名を馳せた工藤勇一校長にも当てはまる。桐蔭の以上の三理念の授業、それは、理想でもあるが、まず、区立麹町中学校という、エイリート校での成功事例が、神奈川県の、非進学校に当てはまるわけがない。工藤氏は、そこの慧眼の欠如、成功体験という玉座に座り続け、創英の他の教師と反りが合わなくなって、近年学校を去ったとも耳にしたことがる。
伊勢丹のカリスマバイヤー藤巻幸夫が、ヨーカド―に乗り込み、ヨーカド―の衣料部門を立て直しに失敗した。また、コンビニの父、Mrコンビニでもあった鈴木敏文が、そうごうや西武といた百貨店(デパート)という部門を立て直しするすことができなかっかジレンマも、教育分野においても適応できる、真理でもあろうか?
この、過去において、一学年1500名も抱えた進学校は、そもそも分母が巨大、分子の東大合格者が100名近くであっても、内実、優秀な進学校とも敢えていえない体質があった。因に、弊塾の創設年、1997年から1998年は、100名近くあった桐蔭は、1999年以降、50名前後に激減し、その後右下がりとなってゆく。この頃の弊塾の桐蔭生は、出来がよかった。皆、栄光や浅野を落ちた、桐蔭上層部の生徒でもあった。その後、2000年代に入ると、彼らの質というか、学力の底辺にある、知力みたいないものが劣化していく様は、その後の桐蔭の行く末を暗示してもいた。
神奈川県の、スポーツでも名を馳せた進学校は、創立者で、校長にして、理事長でもあった鵜養昇氏がいればの、学業の全盛期の文武両立の学校でもあった。まるで、平清盛が存命中、権勢をふるった平家、織田信長が、経済を主眼として絶対的でもあった織田家の如きものであった。このカリスマ鵜養理事長亡きあとの、桐蔭学園は、学業に関しては、準進学校になれ下がった感が否めない。平成の後半から、公立は嫌だが、学力がいまいちの小学生を引き受ける、みたくれ進学校になれ下がってしまった。敢えて、独立させてもいる桐蔭中等は、その没落の宿命をかろうじて回避さけてはいるが、今でも凡庸な進学校には変わりなはい。
この桐蔭学園、昭和の高度成長に出没した、大手スーパーに似ていなくもない。
ダイエー、イトーヨーカド―、西友などである。当時は、す~と現れ、ぱ~と消える業種と揶揄されたが、今や、平成から令和にかけて、それが的中してもいる。この桐蔭学園は、進学校の量販店なのだ。百貨店ではない。平成から台頭してきた渋谷学園系{渋渋と幕張}は、この桐蔭学園とは対照的でもあろう。
まだ、子どもの数、人口の数も右肩上がりまでいかなくても、消費者は、多くいた。ユニクロ、青山、アオキなどの紳士服チェーン店や家電量販店からドラッグストアーなどライバル店が、カテゴリーキラーとしては、勢力を増してもいなかった。戦国大名の武田、今川、北条の如き存在でもあった。それが、失われた30年の年月のうちに、量販店、いわゆるスーパーという業態は、「何でもあるが、欲しいものがない」という存在になれ下がった。情報化社会の目の肥えた消費者の台頭である。一方、伊勢丹、三越、高島屋などは、「欲しいものだらけだが、手が届かない」とも思われ、消費者が敬遠する存在として、ネット社会の中、斜陽産業化してもゆく。だが、何とかそのブランド価値は維持してもいる。経済の低迷と衣服などに関心がない、お金をかけない、ブランドにこだわらない、安くて質がいいユニクロに、消費がファッション観念を完全に変えられた。よって、スーパーの衣料品は、見向きもされなくなり、食品系スーパー、ライフ、サミット、OKなど勢力にGMSは駆逐されてもゆくというのが、平成後期の流通業の勢力図でもあったであろう
こうした、ダイエーなどの量販店、いや、このダイエーの創業者中内功にキャラがとてもよく似ている桐蔭学園の鵜養昇氏が、かつて次の様な言葉を吐いていたことが記憶にある。
「うちにくる生徒は、神奈川における栄光学園、聖光学院、浅野学園などに落ちた者です。彼らは、やはり、神奈川の男子進学校御三家に入れなかった、準秀才の連中である。彼らを、いかに、東大や、一橋や東工大、せめて、早慶に入れさせるか、それは、量につぐ量で、徹底的に、数をこなさせる方式で、演習につぐ演習で、6年後、栄光などの生徒にためを張れる域にまでもってゆく、それが、我が校のやり方です」
このインタビューを、ある雑誌記事か、彼の著作物か何かで観て、まさしく、昭和のスポ根アニメの練習手法を想起してしまった。才能も能力もない者は、ただ量につぐ量をこなして、才を持つ、質の集団に立ち向かってゆく、そして勝てと命じているようなものである。また、ドラフトでも嫌厭される弱小球団が、無名の選手を育成し、その後、日本一になる球団を彷彿されてもくる。
子どもの数がまだかろうじて多い、現今の少子化社会の前夜である。また、情報化社会の黎明期でもある。教育や勉学の知識が、『ドラゴン桜』『ビリギャル』『下剋上受験』などまだ出現する以前である。このマンモス校、これらが僥倖となっていた。生徒、親御さん以上に、情報量が、学校サイド、塾・予備校サイドにあった時代でもある。昭和から平成前半にかけて、勉学における千本ノック方式、「才能も、素質も、能力もない奴は、学校から課された宿題につぐ宿題で、その科目の成績を伸ばせ!」方式が通用した。生徒も親御さんも、昭和の時代、体罰をされても、「お前が悪い!」と容認されていたように、黙って、学校側の地獄の宿題を、まるで、犬の躾けの如くに、課題をもくもくとこなした。事実、弊塾で、中1から入塾して、中3から高1にかけて、この桐蔭学園の生徒がどれほど辞めていったことであろうか!理由は、「先生!学校の宿題が山ほどあって、塾などに通っていたら、宿題ができないんです!」と、親子そろって、半べそをかいて、退塾する者が大勢いた。また、桐蔭学園では、何故か、当時、塾厳禁派の学校でもあった。塾には、通うなという号令が出されていた。あくまでも、弊塾の桐蔭製生に関してだが。それは、穿った見方をすれば、まるで、江戸時代の鎖国のように、、外国の世界を見てはならぬ!というに等しい魂胆があったように感じた。大手の予備校、また、塾の優秀な講師の授業を目にした彼らは、自校の教師の教える力量がないことに気づく、それを回避するためと、当時の私は感じたものだ。この学校、準秀才以下を、悪しき帰納法で、徹底的に鍛え上げる、ある意味、勉学の軍隊方針もであった。
私は、よく、弊塾の生徒に、「塾、予備校に通うな!」と語る学校、先生がいることは、学びの鎖国校であると語ったものである。自校の先生の教え方のスキルを比較され、自校の先生の質の低さに気づかれないように、“塾に通うな令”がだされてもいたように思われたからだ。これは、邪推でも、勘繰りでもない、正鵠を得たものだと確信してもいた。今でも、そう思う。予備校、塾講師への、偏見ではなく、嫉妬の目線である。平成から、学校教師の質の低下と塾・予備校の講師のスキルの際立った上昇とSNS社会の到来で、学びの鎖国観など、尊王攘夷などなき明治の世の中、鬼畜米英など微塵もない戦後昭和の社会、隔世の感がある。その典型は、例えば、英語でいえば、スタサプの関正生である。彼の弁の立つ、立て板に水にように流暢に、英語の本質を解説・説明するカリスマ講師の登場で、神奈川県の中高一貫校でも、そのスタサプを見て、その内容が小テストでだされるとも語った教え子が少なくない。そうした学校は、英語教師でも、関正生に、白旗を挙げた如しである。こうした学校は、桐蔭の二の舞ともなる。
こうしたご時世、平成前期まで、超(?)進学校、いや、バブルの進学校が、まるで、ダイエーの如く薄利多売で、消滅していったように、今では、この神奈川の進学校、ラグビーや野球でこそ、名門校ではあるが、勉学に関しては、もはやそうではなくなった。子供が多かった頃に、体質改善をしなかったつけが、平成後半にまわてもっきた。いや、ダイエーの中内功というカリスマに、ノンと言えなかったように、鵜川昇理事長に、諫める提案ができなかった悲劇かもしれない。いや、彼の手法を祖法のように、堅持したつけが回ってきたのかもしれない。
余談ながら、現在の、桐蔭学園は、アクティブラーニング授業、探求型授業、キャリア授業の三本柱であるともいう。しかし、この三本柱で学校運営をやってゆける学校は、秀才以上が、半数以上いなければ成立しない理想形のものだ。文科省が言う、英語教育の、読み・書き・話し・聞くといった四技能を、公立中学校、標準的公立高校で同時並行で行うが如しである。理想と現実を峻別できない、現場を知らない蒙昧なる教育方針でもある。英語なら、まず、文法を下敷きに、徹敵的に読みを鍛える、その後、書きに以降する。そのあと、聞き、そして話すという順序で、語学は、12才以降教えるのが私の思念である。
準秀才校の鉄則なのだが、まず、英数国理社の学力の構築が先にありき、である。これは、横浜創英高校を、短期で辞任した、『学校の「当たり前」をやめた。』で名を馳せた工藤勇一校長にも当てはまる。桐蔭の以上の三理念の授業、それは、理想でもあるが、まず、区立麹町中学校という、エイリート校での成功事例が、神奈川県の、非進学校に当てはまるわけがない。工藤氏は、そこの慧眼の欠如、成功体験という玉座に座り続け、創英の他の教師と反りが合わなくなって、近年学校を去ったとも耳にしたことがる。
伊勢丹のカリスマバイヤー藤巻幸夫が、ヨーカド―に乗り込み、ヨーカド―の衣料部門を立て直しに失敗した。また、コンビニの父、Mrコンビニでもあった鈴木敏文が、そうごうや西武といた百貨店(デパート)という部門を立て直しするすことができなかっかジレンマも、教育分野においても適応できる、真理でもあろうか?