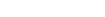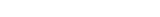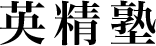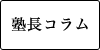カテゴリ
- おすすめの参考書
- 保護者の方へ (10)
- 2020年問題 (3)
- おすすめの教養書
月別 アーカイブ
- 2025年4月 (1)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (5)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (5)
- 2024年3月 (4)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (4)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (5)
- 2021年12月 (7)
- 2021年11月 (4)
- 2021年10月 (5)
- 2021年9月 (4)
- 2021年8月 (4)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (10)
- 2021年4月 (5)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (7)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (7)
- 2020年6月 (6)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (5)
- 2020年3月 (5)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (4)
- 2019年12月 (5)
- 2019年11月 (5)
- 2019年10月 (4)
- 2019年9月 (5)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (5)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (6)
- 2019年3月 (6)
- 2019年2月 (3)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (7)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (3)
- 2018年7月 (4)
最近のエントリー
HOME > コラム > 21世紀のアナログ派は印象派に学べ!
コラム
21世紀のアナログ派は印象派に学べ!
俳句に“意味”はない、と言えば、反論されるにきまっているが、いくつもの意味を同時にそなえている表現に、“意味”は存在しない。生まれるのは、受け手の“解釈”で、十人十色になる。
いくらノンキな教師でも、入学試験の問題に、俳句の意味を問うことはしない。アイマイなことばには、意味、正確な意味を特定することはできない。
俳句に限らず、日本語の表現で、意味を特定することは難しい。おびただしい試験で国語の問題が出されるが、意味を問うことはできない。せいぜい、“解釈”になる。解釈に点をつけることは難しいから、競争試験に国語の出番はないはずである。
俳句がおもしろいのは、あいまい、だからであり、意味がはっきりしないからである。わかりにくいから、おもしろい、わけのわからぬことを表現するからおもしろい。俳句はおごってはいけない。『伝達の生理学』(外山滋比古)~ちくま文庫~
デジタルは、二進法で組み立てられているという。即ち、1と0で全てを構成している。一方、私の考えでは、アナログとは、1と0の間に、無限に小数や分数の微細な数を含む世界である。極論ながら、デジタルは、この世に男と女という見た目の性差しかいないとする考えでもある。他方で、アナログ的観点では、LGBTQといった様々な内面をも含めた人間がいることを肯定する、区分する考えでもある。時代は、デジタルの時代でありながら、アナログを放逐する勢いである。しかし、ジェンダー論の考えでは、むしろアナログチックの視点が必要ともされている。アナログとは、ものごとは、1と0とのように、白黒、男女、昼夜といったように、二分裂などできないとする考えを根本とする。
令和の時代、デジタルに染まった若者を概観すると、世界観とも言おうか、価値観とも言おうか、自身の好き嫌いとも言おうか、このデジタルの二分割方式の論理で判断する人が大勢を占めている感が否めない。そうした10代、20代は、まるで一日24時間が、真っ昼間の明るい昼時と、真っ暗な夜時しかないと、どうも考えているような気がしてならない。デジタルネイティヴには、夜明けの茜色の美しさや、日没時の夕焼けの薄暮の情緒などの感慨に耽る暇も感性もないようである。朝日が昇る薄ら明かりの早朝の景色、夕日が沈む青から群青へ、緋色を交えたグラデーション宵のひと時、こうした情趣に心が染まらない人間は、アナログを忘却した、こてこてのデジタル人間とも言っていい。その点、和歌(短歌)や俳諧(俳句)などを解釈して、その意味だけを知ろうとする人間は、AIに心奪われた‘未来人間’とも言えよう。「解釈を拒絶して動じないものだけが美しい」と、小林秀雄は語っている。解釈だらけの現代は、デジタル帝国の世界でもある。そして、‘AIという皇帝’が君臨しかけてもいる。虎の威を借りる狐ではないが、AIの威を借りる習近平がそれを地で行く中国である。現代の中国に情緒・風情といった感性は育ちはしない。皮肉まじりに言わせてもらえば、インバウンドの活況や日本に住み着く中国人の増加は、本音では、そうしたドライで無機質な社会への嫌悪感からが大きな理由であると私はみている。
21世紀は、都市と自然、文明と文化、AI(コンピュータ)と人間、こうした対比構図を描きつつある様相を呈してもいる。そのしっぺ返しが地球温暖化と格差社会の到来でもある。デジタル独走社会では、これらの後者が、放逐され、消滅しかけてもいる。
スマホが、人間の精神と肉体の中に、組み込まれようとしている。プログラミングというコンピュータと会話する言語が、小学校から身に着くように、奨励されてもいる。ここに、「コンピュータが人間に近づいてきているだと?冗談じゃない!人間がコンピュータに近づいてきているんだろうが!」(養老孟司)という指摘が、真実味を増してくる。
19世紀まで、ヨーロッパの画家たちは、リアリズムを追求した。なるべく物事を写実的に描くことを求められ、それを使命とした。しかし、写真というものの発明、出現により、リアルという概念が揺るぎ始めた。王侯貴族のお抱え画家は、失業となった。リアルさの点では、写真機には到底かなわない。19世紀の文明の利器、カメラの台頭である。これこそ、約200年前の‘デジタル’の台頭である。それに反旗を翻したのが、印象派の画家たちである。もちろんチューブ絵具の開発もあっただろう、イーゼルを屋外に持ち出し、太陽の明るい日差しの下で、自身の印象、感性、肉眼のおもむくままに対象をタブローに連れ込む流儀が生まれた、これが、印象派の誕生である。私に言わせれば、<19世紀のアナログ復興>でもある。ここに、21世紀のアナログ復興のヒントがあると私は観た。
近年、ビジネスにアートを取り入れる考え方が、静かなブームである。山口周氏の著作が、それを証明してくれてもいる。
話はそれるが、大学受験の現代文では、論理というものがやたらと強調さている。また、数年後の国語の高校教科書も論理国語と文学国語と枝分かれするらしい。大学入学共通テストでも、論理性がやたらと重要視さてもいる。時代は、‘論理!論理!’の大合唱である。
論理というものは、ある意味、デジタルの独壇場の世界である。この論理を突き詰めてゆけば、C言語やプログラミングに行き着く。この論理旋風とやらは、どうも、19世紀の画家にとっての写真機の出現とも相似ている。
養老孟司も指摘しているが、将棋の名人が、AI棋士に負けるのは当然であるともいう。それは、100メートル走で人間が、自転車、オートバイにかないっこないのと同義だそうだ。そんな、生物としての人間が、機械のAIと勝負しても勝てるわけがないという。だからといって、将棋界や陸上界が地上から不要であると、根絶されることもない。それは、アナログの重要性を、まるで、自然の森林や河川、海同様に必要ともされているからである。気仙沼湾の良質で、美味なるカキは、陸地の森林から河川を通して流れてくる栄養分があればこそ育つように、真のデジタルには、アナログというものはなくてはならないというのが私の信念でもある。
ビジネスの世界でも同様であろう。マーケティングは、デジタル力の独壇場である。様々なデータを収集し、その分析には、スーパーコンピュータに人間がかなうわけがない。しかし、ブランディングというものは、アナログ力がものを言う。AIにブランディングができるか、AIに名作が書けるか。AIに名曲が書けるか、AIに哲学ができるか?この点、まさしく、ユニクロというファーストファッションがケーススタディとして挙げられよう。ユニクロは、今や、世界一の売り上げを誇る大企業にまで昇りつめた。しかし、ブランディングだけは、いまいち柳井正社長の思う通りには運んではいない。これぞ、デジタル化で急成長を遂げた企業の限界であり、ジレンマでもある。アナログ力とは、会社が大きくなればなれるほど、むしろ、削がれても行く事例でもあろう。だから大企業は、有名人を用いてCMを大々的に打つ!SDGsなどに熱を上げるそぶりを見せる。それは、数値だけでは、ビジネス判断できない領域でもある。例えば、草間彌生、村上隆、奈良美智などが、現代アートの巨匠となった経緯は、デジタル力ではない。別の文脈の‘アナログ力’である。
芸術というものの存在意義とは、デジタルの世界から、ある意味、人間を守るためにある。中世のキリスト教絶対から、その反動としてルネサンスというヒューマニズムに裏打ちされたサイエンスの誕生を招来したように、今や、ポストモダンのデジタル絶対社会から、アナログの復興を、私は希求する。
【補記】
偶然にも、今日6月28日(月曜日)日経MJの一面の記事のヘッドラインである。
Zの時代~Z世代の若者の時代~
昭和しか勝たん
非デジタルが居心地がいい
ほどよく身近な非日常
歌謡曲もボカロもどっちも好き=郷愁ではなくコンテンツ=
※Z世代の若者が、<昭和レトロというアナログ復興>の主役になり、逆に、デジタルかぶれのおやじ連中は、我に返るのではと私は予想している。西武園ゆうえんちやアナログレコード、昭和の名車、真空管アンプ、田舎の古民家などなどである。
いくらノンキな教師でも、入学試験の問題に、俳句の意味を問うことはしない。アイマイなことばには、意味、正確な意味を特定することはできない。
俳句に限らず、日本語の表現で、意味を特定することは難しい。おびただしい試験で国語の問題が出されるが、意味を問うことはできない。せいぜい、“解釈”になる。解釈に点をつけることは難しいから、競争試験に国語の出番はないはずである。
俳句がおもしろいのは、あいまい、だからであり、意味がはっきりしないからである。わかりにくいから、おもしろい、わけのわからぬことを表現するからおもしろい。俳句はおごってはいけない。『伝達の生理学』(外山滋比古)~ちくま文庫~
デジタルは、二進法で組み立てられているという。即ち、1と0で全てを構成している。一方、私の考えでは、アナログとは、1と0の間に、無限に小数や分数の微細な数を含む世界である。極論ながら、デジタルは、この世に男と女という見た目の性差しかいないとする考えでもある。他方で、アナログ的観点では、LGBTQといった様々な内面をも含めた人間がいることを肯定する、区分する考えでもある。時代は、デジタルの時代でありながら、アナログを放逐する勢いである。しかし、ジェンダー論の考えでは、むしろアナログチックの視点が必要ともされている。アナログとは、ものごとは、1と0とのように、白黒、男女、昼夜といったように、二分裂などできないとする考えを根本とする。
令和の時代、デジタルに染まった若者を概観すると、世界観とも言おうか、価値観とも言おうか、自身の好き嫌いとも言おうか、このデジタルの二分割方式の論理で判断する人が大勢を占めている感が否めない。そうした10代、20代は、まるで一日24時間が、真っ昼間の明るい昼時と、真っ暗な夜時しかないと、どうも考えているような気がしてならない。デジタルネイティヴには、夜明けの茜色の美しさや、日没時の夕焼けの薄暮の情緒などの感慨に耽る暇も感性もないようである。朝日が昇る薄ら明かりの早朝の景色、夕日が沈む青から群青へ、緋色を交えたグラデーション宵のひと時、こうした情趣に心が染まらない人間は、アナログを忘却した、こてこてのデジタル人間とも言っていい。その点、和歌(短歌)や俳諧(俳句)などを解釈して、その意味だけを知ろうとする人間は、AIに心奪われた‘未来人間’とも言えよう。「解釈を拒絶して動じないものだけが美しい」と、小林秀雄は語っている。解釈だらけの現代は、デジタル帝国の世界でもある。そして、‘AIという皇帝’が君臨しかけてもいる。虎の威を借りる狐ではないが、AIの威を借りる習近平がそれを地で行く中国である。現代の中国に情緒・風情といった感性は育ちはしない。皮肉まじりに言わせてもらえば、インバウンドの活況や日本に住み着く中国人の増加は、本音では、そうしたドライで無機質な社会への嫌悪感からが大きな理由であると私はみている。
21世紀は、都市と自然、文明と文化、AI(コンピュータ)と人間、こうした対比構図を描きつつある様相を呈してもいる。そのしっぺ返しが地球温暖化と格差社会の到来でもある。デジタル独走社会では、これらの後者が、放逐され、消滅しかけてもいる。
スマホが、人間の精神と肉体の中に、組み込まれようとしている。プログラミングというコンピュータと会話する言語が、小学校から身に着くように、奨励されてもいる。ここに、「コンピュータが人間に近づいてきているだと?冗談じゃない!人間がコンピュータに近づいてきているんだろうが!」(養老孟司)という指摘が、真実味を増してくる。
19世紀まで、ヨーロッパの画家たちは、リアリズムを追求した。なるべく物事を写実的に描くことを求められ、それを使命とした。しかし、写真というものの発明、出現により、リアルという概念が揺るぎ始めた。王侯貴族のお抱え画家は、失業となった。リアルさの点では、写真機には到底かなわない。19世紀の文明の利器、カメラの台頭である。これこそ、約200年前の‘デジタル’の台頭である。それに反旗を翻したのが、印象派の画家たちである。もちろんチューブ絵具の開発もあっただろう、イーゼルを屋外に持ち出し、太陽の明るい日差しの下で、自身の印象、感性、肉眼のおもむくままに対象をタブローに連れ込む流儀が生まれた、これが、印象派の誕生である。私に言わせれば、<19世紀のアナログ復興>でもある。ここに、21世紀のアナログ復興のヒントがあると私は観た。
近年、ビジネスにアートを取り入れる考え方が、静かなブームである。山口周氏の著作が、それを証明してくれてもいる。
話はそれるが、大学受験の現代文では、論理というものがやたらと強調さている。また、数年後の国語の高校教科書も論理国語と文学国語と枝分かれするらしい。大学入学共通テストでも、論理性がやたらと重要視さてもいる。時代は、‘論理!論理!’の大合唱である。
論理というものは、ある意味、デジタルの独壇場の世界である。この論理を突き詰めてゆけば、C言語やプログラミングに行き着く。この論理旋風とやらは、どうも、19世紀の画家にとっての写真機の出現とも相似ている。
養老孟司も指摘しているが、将棋の名人が、AI棋士に負けるのは当然であるともいう。それは、100メートル走で人間が、自転車、オートバイにかないっこないのと同義だそうだ。そんな、生物としての人間が、機械のAIと勝負しても勝てるわけがないという。だからといって、将棋界や陸上界が地上から不要であると、根絶されることもない。それは、アナログの重要性を、まるで、自然の森林や河川、海同様に必要ともされているからである。気仙沼湾の良質で、美味なるカキは、陸地の森林から河川を通して流れてくる栄養分があればこそ育つように、真のデジタルには、アナログというものはなくてはならないというのが私の信念でもある。
ビジネスの世界でも同様であろう。マーケティングは、デジタル力の独壇場である。様々なデータを収集し、その分析には、スーパーコンピュータに人間がかなうわけがない。しかし、ブランディングというものは、アナログ力がものを言う。AIにブランディングができるか、AIに名作が書けるか。AIに名曲が書けるか、AIに哲学ができるか?この点、まさしく、ユニクロというファーストファッションがケーススタディとして挙げられよう。ユニクロは、今や、世界一の売り上げを誇る大企業にまで昇りつめた。しかし、ブランディングだけは、いまいち柳井正社長の思う通りには運んではいない。これぞ、デジタル化で急成長を遂げた企業の限界であり、ジレンマでもある。アナログ力とは、会社が大きくなればなれるほど、むしろ、削がれても行く事例でもあろう。だから大企業は、有名人を用いてCMを大々的に打つ!SDGsなどに熱を上げるそぶりを見せる。それは、数値だけでは、ビジネス判断できない領域でもある。例えば、草間彌生、村上隆、奈良美智などが、現代アートの巨匠となった経緯は、デジタル力ではない。別の文脈の‘アナログ力’である。
芸術というものの存在意義とは、デジタルの世界から、ある意味、人間を守るためにある。中世のキリスト教絶対から、その反動としてルネサンスというヒューマニズムに裏打ちされたサイエンスの誕生を招来したように、今や、ポストモダンのデジタル絶対社会から、アナログの復興を、私は希求する。
【補記】
偶然にも、今日6月28日(月曜日)日経MJの一面の記事のヘッドラインである。
Zの時代~Z世代の若者の時代~
昭和しか勝たん
非デジタルが居心地がいい
ほどよく身近な非日常
歌謡曲もボカロもどっちも好き=郷愁ではなくコンテンツ=
※Z世代の若者が、<昭和レトロというアナログ復興>の主役になり、逆に、デジタルかぶれのおやじ連中は、我に返るのではと私は予想している。西武園ゆうえんちやアナログレコード、昭和の名車、真空管アンプ、田舎の古民家などなどである。
2021年6月28日 16:11