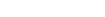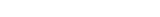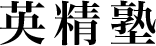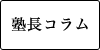カテゴリ
- おすすめの参考書
- 保護者の方へ (10)
- 2020年問題 (3)
- おすすめの教養書
月別 アーカイブ
- 2025年4月 (1)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (5)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (5)
- 2024年3月 (4)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (4)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (5)
- 2021年12月 (7)
- 2021年11月 (4)
- 2021年10月 (5)
- 2021年9月 (4)
- 2021年8月 (4)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (10)
- 2021年4月 (5)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (7)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (7)
- 2020年6月 (6)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (5)
- 2020年3月 (5)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (4)
- 2019年12月 (5)
- 2019年11月 (5)
- 2019年10月 (4)
- 2019年9月 (5)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (5)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (6)
- 2019年3月 (6)
- 2019年2月 (3)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (7)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (3)
- 2018年7月 (4)
最近のエントリー
HOME > コラム > 「ピンチはチャンスだ!」は本当か?
コラム
「ピンチはチャンスだ!」は本当か?
最近コロナ禍で、やたら新聞や雑誌でお目にかかる文言「ピンチはチャンスだ!」というものが私の脳裏に引っかかる。ひと昔前、そして今でも世間を賑わわせる言葉「自己責任問題」と一脈通ずるものがあるからである。この「ピンチはチャンスだ!」をいう時代のコピーを深く哲学チックに考えている論評、記事にお目にかかったことがない。慶應大学の中室牧子教授くらいであろうか?
この「ピンチはチャンスだ!」という文言を紐解くと、功成り名遂げた経営者、能力のある方、幸運を自身の実力と勘違いされている有名人などなどである。
エジソンの名言「99%の汗と1%のひらめき」ではないが、この1%こそ幸運や能力である点に凡人は気づいていない。彼は、この後者が言いたかったのである。凡庸なる大衆は、前者に目がゆく。言い古された、アスリートが頻繁に口にする「努力は裏切らない!」に典型的に表れている。多くの人は、この1%を、まるで図形数学問題の一本の補助線の如くに、突破口となることに気づかぬものである。そのひらめきを“自身の能力”と捉えるか否かという問題とも相似関係をなす。
このピンチを数学でいう難問と仮定すると、1本の補助線を引けるかどうか、それを才能とするか、運とするか、つまり、ひらめきというものが自身の資質に由来するものか否かという究極の問題とも相通じる。これは、国公立の二次試験における国語の記述問題にしろ、英語の英文和訳・和文英訳の問題にしろ、同様のことが言えるのである。その根拠には、今は深入りしない。前置きはこれくらいにしておこう。
会社や組織には、多くの人材がいる、ピンからキリまでである。しかし、その中には、天才や異能の人材がいるものである。江戸幕府における勝海舟や薩摩藩の西郷隆盛のような人物である。この異分子の二人がいなければ、幕末の開国から維新というアウフヘーベンは成立しなかったことだろう。ある大手企業、中小企業でもいい、社長が「ピンチはチャンス!」と唱えれば、誰かしら、会社内の“市井の隠士”が、ヒントを‘上奏’してもくれ、その組織はピンチをしのげるということでもある。また、下町工場や個人商店でさえも、「三人寄れば文殊の知恵」ではないが、ピンチを脱せる場合もある。
しかし、これが、個人レベルともなると、そうは問屋を卸してはくれない。フリーランスと言われる個人事業主、また、会社内での“社畜”と言われている人種である。つまり、会社から希望退職を募ると、会社にとって辞めて欲しくない人材が応募し、辞めて欲しい人材が応募しないという慣例から言って、後者の部族である。この後者にとって「ピンチはチャンス」という標語は、奈良時代の僧にとっての平安密教の如きものとして耳に響いてくるのである。
この「ピンチはチャンス!」には、自身の外部、つまり、会社や社会への武器ともなる知恵や情報が必要となるのは勿論である。社会の進化進歩という発展は、この知恵、そしてその融合体でもある英知がエンジンともなってきた。トヨタにしろ、京セラにしろ、ソニーにしろ、その英知が企業を成長させてもきた。最近では、富士フィルムの豹変ぶり、“企業維新”である。司馬史観だが、明治からせいぜい大正までは、これと同じ摂理で、日本は一等国となった。しかし、昭和に入るや、軍部の悪性ビールスが、この“異能・異質”を抹殺し、“有能なる人材”が払底して、日本を悲劇へと追いやったといってもいい。「ピンチはチャンス!」どころか、「ピンチは破滅」の謂いである。
集団という組織にとって、また、一個人にとっても、その窮状を突破し、生まれ変わる契機ともなる要素、いわば知恵という武器を持ち合わせていなければ、空疎なる理想論で終わってしまう。
よく、エライ人が、世のセイコウ者が、安易に口にする格言・諺「艱難汝を玉にする」「可愛い子には旅をさせよ」は、自身の体験から、実際創業者の社長が、我が子を自身の会社に入れ、即、重役にしたり、一代で苦労したお父さんが、我が子を何不自由なく育てたりする失敗例が、自身と他者との、この言葉の適用の難しさを物語ってもいる。
凡庸なる市民にとっては、それも一個人で生きていかねばならないご時世にあっては、「ピンチは破滅への一里塚」なのである。このコロナ禍で、会社を解雇された、飲食店をたたまざるを得なくなった、非正規社員で仕事が減った、こうした部族にとっては、「ピンチはチャンス!」は、マリーアントワネットの「パンがなければお菓子を食べれば!」くらいにしか心や頭に響きはしないのである。
ここで気づいてほしい。この知恵がない人は、自身の内面に向く武器、<禅でいう智慧>というものを自覚してほしいのである。
「ピンチはチャンス!」これをポジティブに考えても答えがでない、埒が明かない。能力や才能がないからでもある。時に、僥倖とやらでもある。このピンチによって、孤独が最近日本でも社会問題となってきたようである。イギリスに遅れること2年、孤独担当大臣なるものを菅総理は任命したそうである。こんな国のおせっかいを要らぬお世話と涼しい顔でかわす精神こそ、智慧というものである。
ちょっと、広辞苑なり、グーグルなりで調べて欲しい、この智慧こそが、「ピンチはチャンス!」という篩から漏れてしまった部族に、自己防衛の手段としておすすめしたい武器なのである。では、この禅の流れをくむ智慧であるが、これは、何も禅の本を読んだり、座禅を組んだりする必要など毛頭ない、それは、アナログ生活へと少しでも回帰することである。月並みな言葉では、スマホ断食やスマホラマダンでもいい、できれば、「吾唯足るを知る」をもじって、「吾唯“ガラケー”で足る」が一番いい。そういった生活の基盤、習慣を確立することである。ゲームではなく読書を、TDLやUSJではなく登山やキャンピングを、デジタルを遠ざけアナログに立ち返ること、それは、令和の疎外感、孤独という津波からの高台ともなるのである。
私のモットーでもある。「社会・会社では、デジタルの仮面を被り、自宅では、アナログの素顔で生活せよ」私のような凡庸なる市民が得た<生きる算段>としてのツールでもある。
※先週号(3月11日)の週刊新潮であるが、ミス東大(東大理Ⅲの上田彩瑛)やクイズ東大王(東大文Ⅰの鈴木光)など受験期にスマホを解約したという内容を取り上げたりと、最近この週刊誌は、スマホやらデジタルに反旗を翻している記事がやたらと目に付く。『スマホ脳』(新潮新書)もバカ売れのようである。がんばれ“保守”の新潮社!
この「ピンチはチャンスだ!」という文言を紐解くと、功成り名遂げた経営者、能力のある方、幸運を自身の実力と勘違いされている有名人などなどである。
エジソンの名言「99%の汗と1%のひらめき」ではないが、この1%こそ幸運や能力である点に凡人は気づいていない。彼は、この後者が言いたかったのである。凡庸なる大衆は、前者に目がゆく。言い古された、アスリートが頻繁に口にする「努力は裏切らない!」に典型的に表れている。多くの人は、この1%を、まるで図形数学問題の一本の補助線の如くに、突破口となることに気づかぬものである。そのひらめきを“自身の能力”と捉えるか否かという問題とも相似関係をなす。
このピンチを数学でいう難問と仮定すると、1本の補助線を引けるかどうか、それを才能とするか、運とするか、つまり、ひらめきというものが自身の資質に由来するものか否かという究極の問題とも相通じる。これは、国公立の二次試験における国語の記述問題にしろ、英語の英文和訳・和文英訳の問題にしろ、同様のことが言えるのである。その根拠には、今は深入りしない。前置きはこれくらいにしておこう。
会社や組織には、多くの人材がいる、ピンからキリまでである。しかし、その中には、天才や異能の人材がいるものである。江戸幕府における勝海舟や薩摩藩の西郷隆盛のような人物である。この異分子の二人がいなければ、幕末の開国から維新というアウフヘーベンは成立しなかったことだろう。ある大手企業、中小企業でもいい、社長が「ピンチはチャンス!」と唱えれば、誰かしら、会社内の“市井の隠士”が、ヒントを‘上奏’してもくれ、その組織はピンチをしのげるということでもある。また、下町工場や個人商店でさえも、「三人寄れば文殊の知恵」ではないが、ピンチを脱せる場合もある。
しかし、これが、個人レベルともなると、そうは問屋を卸してはくれない。フリーランスと言われる個人事業主、また、会社内での“社畜”と言われている人種である。つまり、会社から希望退職を募ると、会社にとって辞めて欲しくない人材が応募し、辞めて欲しい人材が応募しないという慣例から言って、後者の部族である。この後者にとって「ピンチはチャンス」という標語は、奈良時代の僧にとっての平安密教の如きものとして耳に響いてくるのである。
この「ピンチはチャンス!」には、自身の外部、つまり、会社や社会への武器ともなる知恵や情報が必要となるのは勿論である。社会の進化進歩という発展は、この知恵、そしてその融合体でもある英知がエンジンともなってきた。トヨタにしろ、京セラにしろ、ソニーにしろ、その英知が企業を成長させてもきた。最近では、富士フィルムの豹変ぶり、“企業維新”である。司馬史観だが、明治からせいぜい大正までは、これと同じ摂理で、日本は一等国となった。しかし、昭和に入るや、軍部の悪性ビールスが、この“異能・異質”を抹殺し、“有能なる人材”が払底して、日本を悲劇へと追いやったといってもいい。「ピンチはチャンス!」どころか、「ピンチは破滅」の謂いである。
集団という組織にとって、また、一個人にとっても、その窮状を突破し、生まれ変わる契機ともなる要素、いわば知恵という武器を持ち合わせていなければ、空疎なる理想論で終わってしまう。
よく、エライ人が、世のセイコウ者が、安易に口にする格言・諺「艱難汝を玉にする」「可愛い子には旅をさせよ」は、自身の体験から、実際創業者の社長が、我が子を自身の会社に入れ、即、重役にしたり、一代で苦労したお父さんが、我が子を何不自由なく育てたりする失敗例が、自身と他者との、この言葉の適用の難しさを物語ってもいる。
凡庸なる市民にとっては、それも一個人で生きていかねばならないご時世にあっては、「ピンチは破滅への一里塚」なのである。このコロナ禍で、会社を解雇された、飲食店をたたまざるを得なくなった、非正規社員で仕事が減った、こうした部族にとっては、「ピンチはチャンス!」は、マリーアントワネットの「パンがなければお菓子を食べれば!」くらいにしか心や頭に響きはしないのである。
ここで気づいてほしい。この知恵がない人は、自身の内面に向く武器、<禅でいう智慧>というものを自覚してほしいのである。
「ピンチはチャンス!」これをポジティブに考えても答えがでない、埒が明かない。能力や才能がないからでもある。時に、僥倖とやらでもある。このピンチによって、孤独が最近日本でも社会問題となってきたようである。イギリスに遅れること2年、孤独担当大臣なるものを菅総理は任命したそうである。こんな国のおせっかいを要らぬお世話と涼しい顔でかわす精神こそ、智慧というものである。
ちょっと、広辞苑なり、グーグルなりで調べて欲しい、この智慧こそが、「ピンチはチャンス!」という篩から漏れてしまった部族に、自己防衛の手段としておすすめしたい武器なのである。では、この禅の流れをくむ智慧であるが、これは、何も禅の本を読んだり、座禅を組んだりする必要など毛頭ない、それは、アナログ生活へと少しでも回帰することである。月並みな言葉では、スマホ断食やスマホラマダンでもいい、できれば、「吾唯足るを知る」をもじって、「吾唯“ガラケー”で足る」が一番いい。そういった生活の基盤、習慣を確立することである。ゲームではなく読書を、TDLやUSJではなく登山やキャンピングを、デジタルを遠ざけアナログに立ち返ること、それは、令和の疎外感、孤独という津波からの高台ともなるのである。
私のモットーでもある。「社会・会社では、デジタルの仮面を被り、自宅では、アナログの素顔で生活せよ」私のような凡庸なる市民が得た<生きる算段>としてのツールでもある。
※先週号(3月11日)の週刊新潮であるが、ミス東大(東大理Ⅲの上田彩瑛)やクイズ東大王(東大文Ⅰの鈴木光)など受験期にスマホを解約したという内容を取り上げたりと、最近この週刊誌は、スマホやらデジタルに反旗を翻している記事がやたらと目に付く。『スマホ脳』(新潮新書)もバカ売れのようである。がんばれ“保守”の新潮社!
2021年3月 8日 16:31