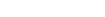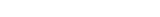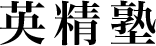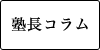カテゴリ
- おすすめの参考書
- 保護者の方へ (10)
- 2020年問題 (3)
- おすすめの教養書
月別 アーカイブ
- 2025年4月 (1)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (5)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (5)
- 2024年3月 (4)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (4)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (5)
- 2021年12月 (7)
- 2021年11月 (4)
- 2021年10月 (5)
- 2021年9月 (4)
- 2021年8月 (4)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (10)
- 2021年4月 (5)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (7)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (7)
- 2020年6月 (6)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (5)
- 2020年3月 (5)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (4)
- 2019年12月 (5)
- 2019年11月 (5)
- 2019年10月 (4)
- 2019年9月 (5)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (5)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (6)
- 2019年3月 (6)
- 2019年2月 (3)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (7)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (3)
- 2018年7月 (4)
最近のエントリー
HOME > コラム > 宗教・思想・経済、そして教育を貫徹している一本の真理
コラム
宗教・思想・経済、そして教育を貫徹している一本の真理
砂浜は歩きづらいが、振り返ると波うちぎわに自分の足跡が…自分だけの足跡が…一つ一つ残っている。アスファルトの道は歩きやすいが、そこには足跡など残りはしない。(遠藤周作)
最近、カトリック作家遠藤周作の未発表原稿『影に対して』が発見されたとNHKのEテレの番組(10月9日)で特集をしていた。その未発表作品のコアとなる考えというものに光があてられていた。それは、Lifeというものを、人生と生活という二つの意味で解釈、捉えるというものである。前者は、砂浜の道、後者は、コンクリートの道、そう遠藤は名づけていた。砂浜の道とは離婚したバイオリンを生きがいとした、おんぼろアパートで息を引き取った母の人生であり、コンクリートの道とは離婚後疎遠となった、東大法学部を出て、その後再婚したエリートサラリーマンの父のそれを投影したものである。
砂浜の道とは、私的な、家庭レベルの、個人の生活内の日常を指す。一方、コンクリートの道とは、公的な、会社レベルの、社会の範囲の行動を指すと私は解した。
砂浜の道とは、歩くにはとてもしんどいが、自ら歩んできた足跡が後ろに残るともいう人生行路であり、またチャレンジの道でもある。コンクリートの道とは、歩くにはとても楽で疲れもしない、ただ単調に前に進めるが、自らが歩んできた足跡はあとには残らない、いわば無難な道である。そうした、二つのメタファーをこの二つの道に遠藤は込めていたともいう。特に、後者は、大企業を定年退職した男が、「あの時、ああしていたら私の人生どうだったであろうか?」「私は、本当に好きなことを仕事にしてきたのだろうか?」と自問自答し、荒涼たる、何もない、後ろに見える自身の生きてきた形跡に、侘しい、空しい、無機質ともいっていい後悔の念が沸き起こる道程でもあると遠藤は示唆しているような気がする。「もっと真剣に、まじめに、自身の人生をお考えなさいよ!」と一般会社員に諭してもいるようである。
近年、社会学者宮台真司氏が、バブル崩壊後の日本に跋扈したネオリベラリズム(新自由主義)を総括して、次のように語っていた。
「ネオリベの奴らは、記憶がない、時間を持たない、歴史というものがない、毎日毎日が現在であって、過去というものない部族である。今さえよければ、今さえ快適なら、それでいい奴らである」これぞ、中途半端デジタル社会日本が生み出したモンスターでもある。
あるカトリック神父が語ってもいたが、「いっぱい思い出、たくさん幸福な記憶を積んでおきなさい、なぜなら、年をとってから、それが光り輝く‘宝もの’になるから」と。
人間とは、記憶の、歴史の動物でもある。「全ての動物は、社会の中に生まれてくる、しかし、歴史の中に生まれてくるのは人間だけである」と司馬遼太郎が述べてもいた。
人間である証明、それは、記憶の豊富さ、思い出の多彩さ、それに依拠するといってもいい。現代は、デジタルというガジェットというスマホに典型的に象徴されているといってもいい。便利さと、快適さ、効率性、そして、経済性といったもので、人間に、今だけ幸せ思想(娯楽の多様性)、過去を否定抹殺(サイエンスの‘神’化)、少々未来志向(社会スパンではなく家族スパン思考)、単視眼的思考(図書館の紙の書籍ではなくグーグル検索のみ)しかできない人間に劣化してしまった気がしなくもない。
遠藤没後25年、批評家若松英輔氏が、「日本人にとってキリスト教とは何か:遠藤周作『深い河』から考える」(NHK出版新書)を出された。彼は、小説家ではないが、クリスチャンでもあり、文芸批評家にスタンスを置いた思索家でもある。彼は、かつてない文明化社会の中で、静かに不安や、心を病む、また孤独なる人々への温かい怜悧な目線を失わない稀有な随筆家でもある。彼の言説は、この遠藤の、砂浜の道への覚醒を読み手、聞き手に自覚させずにはおかない。
また、ここ最近とくに注目されている経営コンサルタント山口周氏の、究極の文明消費社会への、大きな時代の転換点という指摘を挙げておく。
それは、家電製品にしろ、自動車にしろ、あらゆるものが、便利となり、もうこれ以上多機能、ハイスペックな製品は大衆は求めなくなるだろうという指摘である。それは、これからは、<役に立つ>から<意味ある>ものへとシフトするという指摘、予測である。
それは、新規の便利な製品を、まるでスマホの買い替え、ウインドウズソフトの買い替え、こうした狂乱異常高機能追求志向から、その製品の物語性、その製品のルーツ、その製品の背景考慮への消費転換であるともいう。例えば、オーガニックコットンのTシャツだとか、リサイクル製品だとか、長く大切に使用されてきたとか、そうした製品の歴史性・物語性ともいえる<人間の記憶>といったものがブランドたりえると山口氏は主張するのである。これは、モノという企業が作る製品での話である。この目線が、人間個人に向けられる時、それが、遠藤のいう、<コンクリートの道>から<砂浜の道>への回帰でもある。
私が、教育のジャンル、それも幼児は当然、小学校から中学校までの、学校教育というフィールドでは、デジタル器具の利用はできるだけ回避し、アナログの紙の教科書と鉛筆とノート、これを頑強に固執すべきだと声高に主張している根拠もここにあるのである。
デジタル教科書や端末タブレットなど、学校を卒業したら、母校に返却である。その学びの思い出など、ランドセルのように大切に押し入れにビニールに包み保管されることもない文明の利器である。一方、紙の国語の教科書の文豪の写真に落書きした跡や、歴史の教科書にマーカーなど線引きした色、算数の教科書の余白の筆算の形跡など、青春前夜の林間学校のスナップ写真同様に、その少年少女の記憶に残り続けるものである。
ここで、結論を言おう、砂浜の道とは、アナログ学習であり、コンクリートの道とは、デジタル学習でもあるということである。この文脈で、弊著『反デジタル考』は、令和の日本の教育に警鐘を鳴らしてもいる。
これは、少々過激な社会学者宮台真司氏の現代の教育観といったものである。贈与論から教育論への援用ともいっていい考え方である。「人にモノを与える、あげる、施しをする、人に何かをしてあげる、つまり、人を幸せにしてあげることに自らが幸福感を覚えるように子育てすることが肝要である。現代は、自分さえよければ、自分さえ豊かであれば、今さえよければといった空気に染まり切っている。それに染まらない教育が最も大切である」外見に似合わずと言ったら失礼かもしれないが、なかなかまともなことを述べられている。
三島由紀夫の言葉の最も好きなものの一つでもあるのだが、「この世の最も純粋な喜びは他人の喜びを見ることだ」と、宮台氏の言説と一脈通じるものがある。また、宮沢賢治の有名な言葉「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」という世界観と究極では同次元のものでもあろう。だから、斎藤幸平氏の『人新世の「資本論」』が注目の的ともなっている所以でもあろうし、新しい日本型資本主義(≒アベノミクス)’という看板だけの架け替え工事をしただけの、岸田首相のスローガンが、苦しい状況の中にいることを如実に物語ってもいる。
以下は、三島由紀夫が市ヶ谷駐屯地で自裁する約4カ月前に産経新聞に寄せた有名な一文「果たし得ていない約束」の一節である。
このまま行ったら「日本」なくなってしまうのではないかという感を日ましに深くする。日本はなくなって、その代わりに、無機質な、からっぽな、ニュートラルな、中間色の、富裕な、抜け目がない、或る経済的大国が極東の一角に残るのであろう。
もはや日本は経済大国ではない、この指摘は、現在の中華人民共和国であることは明白であるが、令和の日本人も笑えた義理はないのである。
最近、カトリック作家遠藤周作の未発表原稿『影に対して』が発見されたとNHKのEテレの番組(10月9日)で特集をしていた。その未発表作品のコアとなる考えというものに光があてられていた。それは、Lifeというものを、人生と生活という二つの意味で解釈、捉えるというものである。前者は、砂浜の道、後者は、コンクリートの道、そう遠藤は名づけていた。砂浜の道とは離婚したバイオリンを生きがいとした、おんぼろアパートで息を引き取った母の人生であり、コンクリートの道とは離婚後疎遠となった、東大法学部を出て、その後再婚したエリートサラリーマンの父のそれを投影したものである。
砂浜の道とは、私的な、家庭レベルの、個人の生活内の日常を指す。一方、コンクリートの道とは、公的な、会社レベルの、社会の範囲の行動を指すと私は解した。
砂浜の道とは、歩くにはとてもしんどいが、自ら歩んできた足跡が後ろに残るともいう人生行路であり、またチャレンジの道でもある。コンクリートの道とは、歩くにはとても楽で疲れもしない、ただ単調に前に進めるが、自らが歩んできた足跡はあとには残らない、いわば無難な道である。そうした、二つのメタファーをこの二つの道に遠藤は込めていたともいう。特に、後者は、大企業を定年退職した男が、「あの時、ああしていたら私の人生どうだったであろうか?」「私は、本当に好きなことを仕事にしてきたのだろうか?」と自問自答し、荒涼たる、何もない、後ろに見える自身の生きてきた形跡に、侘しい、空しい、無機質ともいっていい後悔の念が沸き起こる道程でもあると遠藤は示唆しているような気がする。「もっと真剣に、まじめに、自身の人生をお考えなさいよ!」と一般会社員に諭してもいるようである。
近年、社会学者宮台真司氏が、バブル崩壊後の日本に跋扈したネオリベラリズム(新自由主義)を総括して、次のように語っていた。
「ネオリベの奴らは、記憶がない、時間を持たない、歴史というものがない、毎日毎日が現在であって、過去というものない部族である。今さえよければ、今さえ快適なら、それでいい奴らである」これぞ、中途半端デジタル社会日本が生み出したモンスターでもある。
あるカトリック神父が語ってもいたが、「いっぱい思い出、たくさん幸福な記憶を積んでおきなさい、なぜなら、年をとってから、それが光り輝く‘宝もの’になるから」と。
人間とは、記憶の、歴史の動物でもある。「全ての動物は、社会の中に生まれてくる、しかし、歴史の中に生まれてくるのは人間だけである」と司馬遼太郎が述べてもいた。
人間である証明、それは、記憶の豊富さ、思い出の多彩さ、それに依拠するといってもいい。現代は、デジタルというガジェットというスマホに典型的に象徴されているといってもいい。便利さと、快適さ、効率性、そして、経済性といったもので、人間に、今だけ幸せ思想(娯楽の多様性)、過去を否定抹殺(サイエンスの‘神’化)、少々未来志向(社会スパンではなく家族スパン思考)、単視眼的思考(図書館の紙の書籍ではなくグーグル検索のみ)しかできない人間に劣化してしまった気がしなくもない。
遠藤没後25年、批評家若松英輔氏が、「日本人にとってキリスト教とは何か:遠藤周作『深い河』から考える」(NHK出版新書)を出された。彼は、小説家ではないが、クリスチャンでもあり、文芸批評家にスタンスを置いた思索家でもある。彼は、かつてない文明化社会の中で、静かに不安や、心を病む、また孤独なる人々への温かい怜悧な目線を失わない稀有な随筆家でもある。彼の言説は、この遠藤の、砂浜の道への覚醒を読み手、聞き手に自覚させずにはおかない。
また、ここ最近とくに注目されている経営コンサルタント山口周氏の、究極の文明消費社会への、大きな時代の転換点という指摘を挙げておく。
それは、家電製品にしろ、自動車にしろ、あらゆるものが、便利となり、もうこれ以上多機能、ハイスペックな製品は大衆は求めなくなるだろうという指摘である。それは、これからは、<役に立つ>から<意味ある>ものへとシフトするという指摘、予測である。
それは、新規の便利な製品を、まるでスマホの買い替え、ウインドウズソフトの買い替え、こうした狂乱異常高機能追求志向から、その製品の物語性、その製品のルーツ、その製品の背景考慮への消費転換であるともいう。例えば、オーガニックコットンのTシャツだとか、リサイクル製品だとか、長く大切に使用されてきたとか、そうした製品の歴史性・物語性ともいえる<人間の記憶>といったものがブランドたりえると山口氏は主張するのである。これは、モノという企業が作る製品での話である。この目線が、人間個人に向けられる時、それが、遠藤のいう、<コンクリートの道>から<砂浜の道>への回帰でもある。
私が、教育のジャンル、それも幼児は当然、小学校から中学校までの、学校教育というフィールドでは、デジタル器具の利用はできるだけ回避し、アナログの紙の教科書と鉛筆とノート、これを頑強に固執すべきだと声高に主張している根拠もここにあるのである。
デジタル教科書や端末タブレットなど、学校を卒業したら、母校に返却である。その学びの思い出など、ランドセルのように大切に押し入れにビニールに包み保管されることもない文明の利器である。一方、紙の国語の教科書の文豪の写真に落書きした跡や、歴史の教科書にマーカーなど線引きした色、算数の教科書の余白の筆算の形跡など、青春前夜の林間学校のスナップ写真同様に、その少年少女の記憶に残り続けるものである。
ここで、結論を言おう、砂浜の道とは、アナログ学習であり、コンクリートの道とは、デジタル学習でもあるということである。この文脈で、弊著『反デジタル考』は、令和の日本の教育に警鐘を鳴らしてもいる。
これは、少々過激な社会学者宮台真司氏の現代の教育観といったものである。贈与論から教育論への援用ともいっていい考え方である。「人にモノを与える、あげる、施しをする、人に何かをしてあげる、つまり、人を幸せにしてあげることに自らが幸福感を覚えるように子育てすることが肝要である。現代は、自分さえよければ、自分さえ豊かであれば、今さえよければといった空気に染まり切っている。それに染まらない教育が最も大切である」外見に似合わずと言ったら失礼かもしれないが、なかなかまともなことを述べられている。
三島由紀夫の言葉の最も好きなものの一つでもあるのだが、「この世の最も純粋な喜びは他人の喜びを見ることだ」と、宮台氏の言説と一脈通じるものがある。また、宮沢賢治の有名な言葉「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」という世界観と究極では同次元のものでもあろう。だから、斎藤幸平氏の『人新世の「資本論」』が注目の的ともなっている所以でもあろうし、新しい日本型資本主義(≒アベノミクス)’という看板だけの架け替え工事をしただけの、岸田首相のスローガンが、苦しい状況の中にいることを如実に物語ってもいる。
以下は、三島由紀夫が市ヶ谷駐屯地で自裁する約4カ月前に産経新聞に寄せた有名な一文「果たし得ていない約束」の一節である。
このまま行ったら「日本」なくなってしまうのではないかという感を日ましに深くする。日本はなくなって、その代わりに、無機質な、からっぽな、ニュートラルな、中間色の、富裕な、抜け目がない、或る経済的大国が極東の一角に残るのであろう。
もはや日本は経済大国ではない、この指摘は、現在の中華人民共和国であることは明白であるが、令和の日本人も笑えた義理はないのである。
2021年11月15日 12:47