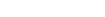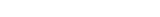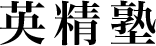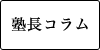カテゴリ
- おすすめの参考書
- 保護者の方へ (10)
- 2020年問題 (3)
- おすすめの教養書
月別 アーカイブ
- 2025年4月 (1)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (5)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (5)
- 2024年3月 (4)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (4)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (5)
- 2021年12月 (7)
- 2021年11月 (4)
- 2021年10月 (5)
- 2021年9月 (4)
- 2021年8月 (4)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (10)
- 2021年4月 (5)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (7)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (7)
- 2020年6月 (6)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (5)
- 2020年3月 (5)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (4)
- 2019年12月 (5)
- 2019年11月 (5)
- 2019年10月 (4)
- 2019年9月 (5)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (5)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (6)
- 2019年3月 (6)
- 2019年2月 (3)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (7)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (3)
- 2018年7月 (4)
最近のエントリー
コラム
私のコペルニクス的転換
人は、何故に本を読むようになるのか?ひとえに、それは、環境であろう。商人の家に育ち、“商人に学問は要らない!”という祖父伝来の、非教養的家系の中、両親も本を読まない、活字らしきもの、新聞でも、雑誌でも読んでいる姿を目にしたことがなかった。家のどこにも、書籍らしいものすらない、そうした環境で、娯楽と言えば、テレビ、テレビの毎日でもあった。私自身、両親の離婚した16才の終わりまで、一切、本などまともに読んだことのない人生でもあった。その来歴が、国語という科目の最大の 弱点的要因であったことは、宅浪の、それも中学浪人の時にうすうすと感づき始めてもいた。
余談だが、両親の仲の悪さ、両親の諍いの元は次の点に尽きる。父にしろ、母にしろ、本、活字、言葉といったロゴス(理性)で、自己のパトス(感情)を制御できない者同士であったことも口論、喧嘩というものが最大の原因であることが、その後大学時代に悟ることにもなる。両親が、言葉というものに貧困、貧弱ともなると、その制御するロゴスというブレーキが欠如した車のように暴走してしまう様が想起される。自身の様々な激情に支配されやすく、そういう人間の性というものを両親の夫婦喧嘩の淵源として、その後実感されもするのである。国語の弱点克服を、両親を半面教師として、活字・言葉を基盤とする人格形成、そして、全ての教科の土台は、国語にあるのではないかといった自身の啓蒙的自覚といったようなものが、当時(17才)芽生えてもきた。
両親の影響もあり、学校から帰ると、テレビ漬けの毎日を送り、その習慣が、弱まるのは、中学時代から通い始めた塾のおかでもある。週3回は、6時くらいから9時まで、島本自習塾という、日本最古のギネスにも載っている下町の“名門塾”のおかげともいっていい。
しかし、その塾でも、いつも最低だったのは、国語という科目である。堀辰雄好きの国語の講師の先生が、「お前は、作家で誰が好きか?」とか、「お前は、どんな小説が好きか?」などと質問してくるが、国語弱者の、中二の私は、いつも、コンプレックスの穴に閉じこもり、静かに、下を向いていたものである。驚くことに、その国語教師は、「中3のクラスの中に、新潮文庫の有名作家をほとんど読破したという猛者がいるぞ!」だの、「自身の大好きな井伏鱒二の全てを読んだ奴{※恐らく文庫本の類をすべてであったろう}がいるぞ!」などなど、情報弱者(情弱)ならぬ、当時の国(語)弱(者)の私は、別世界の中学生がいるもんだ!と畏れにも近い別次元の連中に圧倒されてもいた。こうした環境の中、私は、ますます国語コンプレックスのアリ地獄へ、そして、やる気が消耗、よって、国語という科目は、捨て科目ともなっていった。しかし、この島本自習塾では、英語と数学は、小6の余力(学力)を駆って、加速度的に、伸ばしてもいった。理科と社会は、中学校の授業が素晴らしく、また、面白くもあり、問題はなかった。
こうした、私の学力プロフィールからも想像に難くないであろう、国語だけ、唯一の弱点、圧倒的コンプレックスを抱き、東京の私立高校に進むも、3カ月で中退する運命に遭うのである。
離婚後、母方に就いた私は、中学浪人の環境に置かれた。離婚調停で、財産分与やら、私と妹の籍をどちらに入れるか、親権はどちらが持つか、などなど、半年以上もめにもめている最中、母と私と妹は、石巻市でお茶と陶器を手広く商ってもいる伯父{母よりも15歳も上で、一種、母には父のような存在でもあった}のもとで居候生活をすることとなった。屋敷も大きく、離れ屋に間借りして、祖母から母の甥っ子夫婦、さらに、未婚の私の従兄など、そしてその孫たちの中で、大家族内での生活が始まった。遠慮せずにはいられない状況である。当然、東京時代は、テレビのチャンネル権は、いや、自分専用のテレビがあって、見放題だった。でも、大きな居間に、大きなテレビが一台ある、その家族たちが、テレビの主導権を握ってもいる。遠慮して、テレビというものから、だんだんと遠ざかる生活へと生活習慣が、面舵いっぱいきることともなる。ここが転機である。来年の高校合格のための独学の、宅浪受験勉強の息抜き、娯楽といったものが、一切なくなった。そこで、東京の高校時代に配布された第一学習社の国語便覧というものを、毎日、ぺっらぺらと、無聊をかこつかのように、飛ばし読みをしてゆくうちに、漱石、鷗外、谷崎、志賀、芥川、川端、三島、太宰といった文豪たちの軽い、ちょっとした評伝を読み、自身の“不幸”を彼らの人生に準えて、何らかの、人生の悪(不運・不幸・挫折など)を人生の華(名作小説)に昇華した小説家という種族に惹かれてもいった。この時点では、かすかな自身の淡い将来像を、描いていてもいた、無意識の閾で、確かに、そうであったと思われる。
まず、彼らの人生が、最初である、契機となった。私の人生の、理系人間から文系人間への大転換でもある、思春期の第二幕が始まったのは。そうした、作家たちが、劇的人生を送って、その宿命とやらを芸術としての作品として昇華し、残していった、その生き様に惹かれた、そして、そういった人間の書くもの、あらすじやプロットといった解説から、その作品を読みたいという衝動に駆られた。活字の海への渇望といったものである。そして、以前は、苦手だった野菜を、食べてみようかといった少年の心境のように、名作の文庫本への食指が伸びてもいった。これが、国語以前、読書以前、文学以前の、活字・言葉世界との馴れ初めでもある。
しかしである、最初は、難しかった。それもそのはず、小学校と中学校で、野球やサッカーを一切やってこなかった少年が、高校から、そうしたスポーツをやるに等しい状況に立たされたからである。これは、別の回でも述べることとして、かの文豪たちは、厳密には、石巻高校の一年になってから文庫本で読み始めたのである。
中学浪人時代は、東京の錦糸中学校時代に、中3で、夏休みの読書推薦書{※できれば夏休み中に読んでおきなさい的課題図書}として、短編小説のアンソロジー集{※新学社という出版社のもの}を3冊ほど、友人たちに右エ倣え式に、読むつもりもなく、エエカッコしい的気持ちで、見栄っ張り根性で、教室内で申し込んで、それを購入し、未読のものが手元にあった。そこからが、活字の海への入り口でもあった。今でも、記憶にあるのは、永井龍男の『黒い御飯』安岡章太郎の『サーカスの馬』や小泉八雲の『怪談』である。そこで、活字の水泳でいうところの入門の洗礼をうけたわけである。では、次回は、この中学浪人時代の初級の読書体験を語ってみるとしよう。
余談だが、両親の仲の悪さ、両親の諍いの元は次の点に尽きる。父にしろ、母にしろ、本、活字、言葉といったロゴス(理性)で、自己のパトス(感情)を制御できない者同士であったことも口論、喧嘩というものが最大の原因であることが、その後大学時代に悟ることにもなる。両親が、言葉というものに貧困、貧弱ともなると、その制御するロゴスというブレーキが欠如した車のように暴走してしまう様が想起される。自身の様々な激情に支配されやすく、そういう人間の性というものを両親の夫婦喧嘩の淵源として、その後実感されもするのである。国語の弱点克服を、両親を半面教師として、活字・言葉を基盤とする人格形成、そして、全ての教科の土台は、国語にあるのではないかといった自身の啓蒙的自覚といったようなものが、当時(17才)芽生えてもきた。
両親の影響もあり、学校から帰ると、テレビ漬けの毎日を送り、その習慣が、弱まるのは、中学時代から通い始めた塾のおかでもある。週3回は、6時くらいから9時まで、島本自習塾という、日本最古のギネスにも載っている下町の“名門塾”のおかげともいっていい。
しかし、その塾でも、いつも最低だったのは、国語という科目である。堀辰雄好きの国語の講師の先生が、「お前は、作家で誰が好きか?」とか、「お前は、どんな小説が好きか?」などと質問してくるが、国語弱者の、中二の私は、いつも、コンプレックスの穴に閉じこもり、静かに、下を向いていたものである。驚くことに、その国語教師は、「中3のクラスの中に、新潮文庫の有名作家をほとんど読破したという猛者がいるぞ!」だの、「自身の大好きな井伏鱒二の全てを読んだ奴{※恐らく文庫本の類をすべてであったろう}がいるぞ!」などなど、情報弱者(情弱)ならぬ、当時の国(語)弱(者)の私は、別世界の中学生がいるもんだ!と畏れにも近い別次元の連中に圧倒されてもいた。こうした環境の中、私は、ますます国語コンプレックスのアリ地獄へ、そして、やる気が消耗、よって、国語という科目は、捨て科目ともなっていった。しかし、この島本自習塾では、英語と数学は、小6の余力(学力)を駆って、加速度的に、伸ばしてもいった。理科と社会は、中学校の授業が素晴らしく、また、面白くもあり、問題はなかった。
こうした、私の学力プロフィールからも想像に難くないであろう、国語だけ、唯一の弱点、圧倒的コンプレックスを抱き、東京の私立高校に進むも、3カ月で中退する運命に遭うのである。
離婚後、母方に就いた私は、中学浪人の環境に置かれた。離婚調停で、財産分与やら、私と妹の籍をどちらに入れるか、親権はどちらが持つか、などなど、半年以上もめにもめている最中、母と私と妹は、石巻市でお茶と陶器を手広く商ってもいる伯父{母よりも15歳も上で、一種、母には父のような存在でもあった}のもとで居候生活をすることとなった。屋敷も大きく、離れ屋に間借りして、祖母から母の甥っ子夫婦、さらに、未婚の私の従兄など、そしてその孫たちの中で、大家族内での生活が始まった。遠慮せずにはいられない状況である。当然、東京時代は、テレビのチャンネル権は、いや、自分専用のテレビがあって、見放題だった。でも、大きな居間に、大きなテレビが一台ある、その家族たちが、テレビの主導権を握ってもいる。遠慮して、テレビというものから、だんだんと遠ざかる生活へと生活習慣が、面舵いっぱいきることともなる。ここが転機である。来年の高校合格のための独学の、宅浪受験勉強の息抜き、娯楽といったものが、一切なくなった。そこで、東京の高校時代に配布された第一学習社の国語便覧というものを、毎日、ぺっらぺらと、無聊をかこつかのように、飛ばし読みをしてゆくうちに、漱石、鷗外、谷崎、志賀、芥川、川端、三島、太宰といった文豪たちの軽い、ちょっとした評伝を読み、自身の“不幸”を彼らの人生に準えて、何らかの、人生の悪(不運・不幸・挫折など)を人生の華(名作小説)に昇華した小説家という種族に惹かれてもいった。この時点では、かすかな自身の淡い将来像を、描いていてもいた、無意識の閾で、確かに、そうであったと思われる。
まず、彼らの人生が、最初である、契機となった。私の人生の、理系人間から文系人間への大転換でもある、思春期の第二幕が始まったのは。そうした、作家たちが、劇的人生を送って、その宿命とやらを芸術としての作品として昇華し、残していった、その生き様に惹かれた、そして、そういった人間の書くもの、あらすじやプロットといった解説から、その作品を読みたいという衝動に駆られた。活字の海への渇望といったものである。そして、以前は、苦手だった野菜を、食べてみようかといった少年の心境のように、名作の文庫本への食指が伸びてもいった。これが、国語以前、読書以前、文学以前の、活字・言葉世界との馴れ初めでもある。
しかしである、最初は、難しかった。それもそのはず、小学校と中学校で、野球やサッカーを一切やってこなかった少年が、高校から、そうしたスポーツをやるに等しい状況に立たされたからである。これは、別の回でも述べることとして、かの文豪たちは、厳密には、石巻高校の一年になってから文庫本で読み始めたのである。
中学浪人時代は、東京の錦糸中学校時代に、中3で、夏休みの読書推薦書{※できれば夏休み中に読んでおきなさい的課題図書}として、短編小説のアンソロジー集{※新学社という出版社のもの}を3冊ほど、友人たちに右エ倣え式に、読むつもりもなく、エエカッコしい的気持ちで、見栄っ張り根性で、教室内で申し込んで、それを購入し、未読のものが手元にあった。そこからが、活字の海への入り口でもあった。今でも、記憶にあるのは、永井龍男の『黒い御飯』安岡章太郎の『サーカスの馬』や小泉八雲の『怪談』である。そこで、活字の水泳でいうところの入門の洗礼をうけたわけである。では、次回は、この中学浪人時代の初級の読書体験を語ってみるとしよう。
2024年12月 2日 17:23