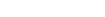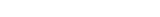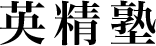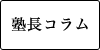カテゴリ
- おすすめの参考書
- 保護者の方へ (10)
- 2020年問題 (3)
- おすすめの教養書
月別 アーカイブ
- 2025年4月 (1)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (5)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (5)
- 2024年3月 (4)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (4)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (5)
- 2021年12月 (7)
- 2021年11月 (4)
- 2021年10月 (5)
- 2021年9月 (4)
- 2021年8月 (4)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (10)
- 2021年4月 (5)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (7)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (7)
- 2020年6月 (6)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (5)
- 2020年3月 (5)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (4)
- 2019年12月 (5)
- 2019年11月 (5)
- 2019年10月 (4)
- 2019年9月 (5)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (5)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (6)
- 2019年3月 (6)
- 2019年2月 (3)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (7)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (3)
- 2018年7月 (4)
最近のエントリー
コラム
林修と私の読書経験
中高生にとって、中学から英語を学び始めた生徒、そして、小学校時代、数年から十年近く海外に住んでいた帰国子女の生徒、彼らには、英語の実力、つまり、英語の技能というものにおいて、格段の差があることは、とみに有名である。当然でもあろう。英語の運用能力において、通称準ジャパと呼ばれる生徒、そして、淀みなく流暢に英語を話す生徒の存在である。この英語教育上の実体は、余りに知れわたった語学上の真実を示す事例として、すでに、誰もがご存じのことでもあろう。
それに対して、国語という、日本語を、敢えて授業で学ぶ、特に現代文というジャンル、小学校から高校まで、読解力や表現力を問う、必須の科目に関して、そういった視点で、指摘する者は少ない。つまり、国語という教科は、小学校4年生くらいまで、読書という、文章という水に慣れ親しんだ者は、中学受験は当然ながら、中学校以降では、嫌な謂いだが、勝ち組になるという厳然たる事実がある。小学校時代に、漢字もろくすっぽ覚えておらず、本も全く読んでいない公立の小学生が、中学にあがると、まず、現代文を基調とした国語は、まず、苦手科目として、3年間を“日陰者”として通す。いや、高校の3年間をも含め、大学受験まで、それがお荷物科目となる事実は、私をも含め、<国語科目の敗者>にこそ実感されることである。苦手科目の存在から、母国語言語の大切さというものを、言葉の意義というものを、痛感させてもくれる。
大手の有名な予備校英語講師の経歴として、カリスマ英語講師安河内哲也氏などが有名でもあるのだが、高校2年まで、英語は、お荷物科目、つまり、苦手科目であった者が少なくない。高校3年に、時に、浪人時に、自身の勉強の仕方、学び方、また。名参考書などの僥倖を経て、オリジナルなる英語学習法を編み出し、その後、有名大学に合格し、その手法を駆使して、英語のカリスマ講師となった者は少なくない。英語に関しては、私をも含め、こうした経緯で英語を得意とする存在にもなっていく。この経歴ルートは、社会科科目を含め、古文などにも多々見受けられる傾向ではある。
それに対して、理系科目、特に、数学や物理・化学などは、高校生で苦手で、その後、それを克服し、その分野の指導者となるものは、仄聞しない。理系が得意生徒は、算数(サナギ)から数学(蝶)へと<数の世界の学問>が孵化した時点で、すでに、得意の者が、そのまま、理系の勝ち組として君臨するのが定例になってもいるからである。従って、大手の予備校などで、数学などの講師を務めておられる方々は、ある意味、浪人体験なしの、理系のギフティッドの種族であることが多い{※これは、私の私見でもある}。
ここで私が強調したいのは、中等教育の勝敗は、初等教育の段階で、ある意味、勝ち組・負け組が大方決まってもいるという教育上の真理でもある。それは、中1から英語を学び始めても、シンガポールに3年間いた帰国子女には、到底、英語では歯が立たないという悲しき事実にも通底していよう。
これは、弊著『反デジタル考』や『英語教師は<英語>ができなくてもよい!』でも言及していることだが、国語という科目は、丁度、水泳にもいているという私見的事実である。
小学校4年まで、一切泳いだことのない少年が、4年時に学校にプールが設置された状況を考えてみよう。4年生から体育の授業で水泳が始まる。しかし、小1からスイミングスクールに通っていた少年は、楽しくて、4種目をイルカのように泳ぐ。泳げない、その生徒はその姿を目にする、そのコンプレクスたるや、丁度、中1の英語の時間に、帰国子女の英語を耳にした衝撃に近いものがある。活字という水にどれだけ慣れ親しんだ者が、水泳が得意になるように、また、母国語の未発達な小学校の数年間海外で英語で生活した者が、英会話に巧みになるように、小学校低学年(幼少期から6~8歳まで)から読書を習慣としてきた者が、国語という読書を基盤とした教科の勝ち組にもなれるのである。
カリスマ現代文講師林修氏は、父が宝酒造の副社長を務めたサラリーマン家庭の、知的上層階層の部族である。オマケに、祖父は日本画家で、彼の所蔵する日本文学大全集(50巻ほど)を小学校低学年で読破したともいう。また、小学校時代、源氏という武士に興味を持ち、源氏の家系図を、独自にノートでまとめる、自由研究を行う、殊勝なる小学生でもあった。そのノートの完成度たるや、進学校の中高生の研究ノートに勝るとも劣らぬ趣を呈するものである{※ある番組内で披露していた}。そうしたバックグラウンドがあったればこそ、小学校6年生から始めた中学受験勉強も、たった1年で愛知ナンバーワンの中高一貫校に合格する。一般的には、1年間で、中学受験勉強を始めて、日本で一番医学部に進学する者が多い超名門校(4人に1人が医学部進学)に合格するのは超至難のわざでもある。ここに、小学校で、一番大切な科目は、「1に国語、2に国語、3、4がなくて5に算数」(藤原正彦)とされる所以が存する。
この林修氏の小学生学びのプロフィールとは、まさに、真逆とも言えるのが、私の国語経歴でもある。中小企業の商人の家系に育ち、「商人に学問はいらない!」という家風の中、小6まで勉強らしい勉強も一切せず、昭和のわんぱく小僧として、学校周辺を、放課後遊び回り、1冊も本なんぞは読んだこともない、漢字も苦手な少年が、公立小学校でも、小5までは、成績なんぞは、中の中のど真ん中でもあった。そうした環境の中、将来商業高校へと進ませる父の思惑から、早くから算盤をやっていた方が何かと好都合という目算で、父は、私を小5の初めから算盤塾への通わせた。それが父の、将来設計の運のつき、算数が、小6から特に得意になり始め、私立中学校という、学びの欲も出てきて、中学受験勉強をすることとなる。普通は、中学受験をする、クラスのできる奴らは、小4から四谷大塚という、当時の私からいえば“憧れと、垂涎の的でもある超進学塾”に通っているものが多かったが、私は、そんなエリート進学塾なんぞを諦め、地元の個人塾で中学受験を始めたわけでもある。当時は、算数と国語の2科目受験が、とても多かったと記憶している。算数は、武器の科目ともなり、模試などでも、7割以上をゲットしていたが、国語に関しては、いつも、5割を切るありさまであった。こうした、算数と国語との関係は、高校受験にまで尾を引くこととなる。当然ながら、中学3年間も、一切、読書とは、無縁なる時代を経験する。
この、林修氏と私の、小学校時代の、国語体験、読書経験といったもの、更に、家庭環境の知的な差、文化的ギャップというもの、ここでいう文化的なバックグラウンドといったものは、大学時代に結構読み込んだ、フランスの社会学者ピエール・ブリュデユーの用語、“文化資本”というものの多寡が左右するものだという事実に瞠目したものである。しかし、我が人生の僥倖なるかな、両親の離婚、高校中退、それが、<私の明治維新>のような役割を果たしのである。19世紀の帝国主義時代、イコール、昭和の受験戦争ともいえる時代、林修氏という英仏独などの欧米列強国に肩を並べるという、自身の近代化には、国語という科目の改善が必要不可欠でもあると愕然としたのは、17才の夏のことでもあった。
近代化の遅れた、アジアの小国が、富国強兵・殖産興業ともいえる理念を、あのビスマルクに大久保利通が学んだように、遅ればせながら、我が知的なる近代化、つまりは、国語という科目の改革、いや、革命の必要性、日本語という言語の豊饒なる土壌の肥料として、読書がなくてはならないものであると気が付くのは、高校も2年生になりかかろうとする春のことでもあった。
それに対して、国語という、日本語を、敢えて授業で学ぶ、特に現代文というジャンル、小学校から高校まで、読解力や表現力を問う、必須の科目に関して、そういった視点で、指摘する者は少ない。つまり、国語という教科は、小学校4年生くらいまで、読書という、文章という水に慣れ親しんだ者は、中学受験は当然ながら、中学校以降では、嫌な謂いだが、勝ち組になるという厳然たる事実がある。小学校時代に、漢字もろくすっぽ覚えておらず、本も全く読んでいない公立の小学生が、中学にあがると、まず、現代文を基調とした国語は、まず、苦手科目として、3年間を“日陰者”として通す。いや、高校の3年間をも含め、大学受験まで、それがお荷物科目となる事実は、私をも含め、<国語科目の敗者>にこそ実感されることである。苦手科目の存在から、母国語言語の大切さというものを、言葉の意義というものを、痛感させてもくれる。
大手の有名な予備校英語講師の経歴として、カリスマ英語講師安河内哲也氏などが有名でもあるのだが、高校2年まで、英語は、お荷物科目、つまり、苦手科目であった者が少なくない。高校3年に、時に、浪人時に、自身の勉強の仕方、学び方、また。名参考書などの僥倖を経て、オリジナルなる英語学習法を編み出し、その後、有名大学に合格し、その手法を駆使して、英語のカリスマ講師となった者は少なくない。英語に関しては、私をも含め、こうした経緯で英語を得意とする存在にもなっていく。この経歴ルートは、社会科科目を含め、古文などにも多々見受けられる傾向ではある。
それに対して、理系科目、特に、数学や物理・化学などは、高校生で苦手で、その後、それを克服し、その分野の指導者となるものは、仄聞しない。理系が得意生徒は、算数(サナギ)から数学(蝶)へと<数の世界の学問>が孵化した時点で、すでに、得意の者が、そのまま、理系の勝ち組として君臨するのが定例になってもいるからである。従って、大手の予備校などで、数学などの講師を務めておられる方々は、ある意味、浪人体験なしの、理系のギフティッドの種族であることが多い{※これは、私の私見でもある}。
ここで私が強調したいのは、中等教育の勝敗は、初等教育の段階で、ある意味、勝ち組・負け組が大方決まってもいるという教育上の真理でもある。それは、中1から英語を学び始めても、シンガポールに3年間いた帰国子女には、到底、英語では歯が立たないという悲しき事実にも通底していよう。
これは、弊著『反デジタル考』や『英語教師は<英語>ができなくてもよい!』でも言及していることだが、国語という科目は、丁度、水泳にもいているという私見的事実である。
小学校4年まで、一切泳いだことのない少年が、4年時に学校にプールが設置された状況を考えてみよう。4年生から体育の授業で水泳が始まる。しかし、小1からスイミングスクールに通っていた少年は、楽しくて、4種目をイルカのように泳ぐ。泳げない、その生徒はその姿を目にする、そのコンプレクスたるや、丁度、中1の英語の時間に、帰国子女の英語を耳にした衝撃に近いものがある。活字という水にどれだけ慣れ親しんだ者が、水泳が得意になるように、また、母国語の未発達な小学校の数年間海外で英語で生活した者が、英会話に巧みになるように、小学校低学年(幼少期から6~8歳まで)から読書を習慣としてきた者が、国語という読書を基盤とした教科の勝ち組にもなれるのである。
カリスマ現代文講師林修氏は、父が宝酒造の副社長を務めたサラリーマン家庭の、知的上層階層の部族である。オマケに、祖父は日本画家で、彼の所蔵する日本文学大全集(50巻ほど)を小学校低学年で読破したともいう。また、小学校時代、源氏という武士に興味を持ち、源氏の家系図を、独自にノートでまとめる、自由研究を行う、殊勝なる小学生でもあった。そのノートの完成度たるや、進学校の中高生の研究ノートに勝るとも劣らぬ趣を呈するものである{※ある番組内で披露していた}。そうしたバックグラウンドがあったればこそ、小学校6年生から始めた中学受験勉強も、たった1年で愛知ナンバーワンの中高一貫校に合格する。一般的には、1年間で、中学受験勉強を始めて、日本で一番医学部に進学する者が多い超名門校(4人に1人が医学部進学)に合格するのは超至難のわざでもある。ここに、小学校で、一番大切な科目は、「1に国語、2に国語、3、4がなくて5に算数」(藤原正彦)とされる所以が存する。
この林修氏の小学生学びのプロフィールとは、まさに、真逆とも言えるのが、私の国語経歴でもある。中小企業の商人の家系に育ち、「商人に学問はいらない!」という家風の中、小6まで勉強らしい勉強も一切せず、昭和のわんぱく小僧として、学校周辺を、放課後遊び回り、1冊も本なんぞは読んだこともない、漢字も苦手な少年が、公立小学校でも、小5までは、成績なんぞは、中の中のど真ん中でもあった。そうした環境の中、将来商業高校へと進ませる父の思惑から、早くから算盤をやっていた方が何かと好都合という目算で、父は、私を小5の初めから算盤塾への通わせた。それが父の、将来設計の運のつき、算数が、小6から特に得意になり始め、私立中学校という、学びの欲も出てきて、中学受験勉強をすることとなる。普通は、中学受験をする、クラスのできる奴らは、小4から四谷大塚という、当時の私からいえば“憧れと、垂涎の的でもある超進学塾”に通っているものが多かったが、私は、そんなエリート進学塾なんぞを諦め、地元の個人塾で中学受験を始めたわけでもある。当時は、算数と国語の2科目受験が、とても多かったと記憶している。算数は、武器の科目ともなり、模試などでも、7割以上をゲットしていたが、国語に関しては、いつも、5割を切るありさまであった。こうした、算数と国語との関係は、高校受験にまで尾を引くこととなる。当然ながら、中学3年間も、一切、読書とは、無縁なる時代を経験する。
この、林修氏と私の、小学校時代の、国語体験、読書経験といったもの、更に、家庭環境の知的な差、文化的ギャップというもの、ここでいう文化的なバックグラウンドといったものは、大学時代に結構読み込んだ、フランスの社会学者ピエール・ブリュデユーの用語、“文化資本”というものの多寡が左右するものだという事実に瞠目したものである。しかし、我が人生の僥倖なるかな、両親の離婚、高校中退、それが、<私の明治維新>のような役割を果たしのである。19世紀の帝国主義時代、イコール、昭和の受験戦争ともいえる時代、林修氏という英仏独などの欧米列強国に肩を並べるという、自身の近代化には、国語という科目の改善が必要不可欠でもあると愕然としたのは、17才の夏のことでもあった。
近代化の遅れた、アジアの小国が、富国強兵・殖産興業ともいえる理念を、あのビスマルクに大久保利通が学んだように、遅ればせながら、我が知的なる近代化、つまりは、国語という科目の改革、いや、革命の必要性、日本語という言語の豊饒なる土壌の肥料として、読書がなくてはならないものであると気が付くのは、高校も2年生になりかかろうとする春のことでもあった。
2024年12月16日 16:17