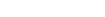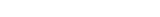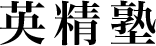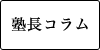カテゴリ
- おすすめの参考書
- 保護者の方へ (10)
- 2020年問題 (3)
- おすすめの教養書
月別 アーカイブ
- 2025年4月 (1)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (5)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (5)
- 2024年3月 (4)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (4)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (5)
- 2021年12月 (7)
- 2021年11月 (4)
- 2021年10月 (5)
- 2021年9月 (4)
- 2021年8月 (4)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (10)
- 2021年4月 (5)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (7)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (7)
- 2020年6月 (6)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (5)
- 2020年3月 (5)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (4)
- 2019年12月 (5)
- 2019年11月 (5)
- 2019年10月 (4)
- 2019年9月 (5)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (5)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (6)
- 2019年3月 (6)
- 2019年2月 (3)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (7)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (3)
- 2018年7月 (4)
最近のエントリー
HOME > コラム > 本という"寺"の門前の小僧、その扉を開く
コラム
本という"寺"の門前の小僧、その扉を開く
東京の私立の進学校を高校1年の6月で中退し、それから、石巻の母の実家で居候の身として,半年以上、中学浪人の生活を送り始めるなか、文学、読書、そして活字、さらには言葉というものを意識し始める。本という存在が、口などきいたこともない友人から親しき友へと変貌するかのように強烈に自覚されれようになっていった。インベーダーゲーム人気絶頂の頃、テレビが娯楽の王様で、様々な番組が超魅力的な時代、知人友人もいない、見知らぬ土地、まだ東北新幹線もない世の中、東京と仙台の文化格差{※特急ひばりで4時間半かかった}はもちろん、この東北の片田舎の石巻での、思春期の生活は、ある意味、永平寺などで、ただ座禅と掃除、読経をする毎日の、禅宗の修行僧の赴きでもあった。街角のゲームセンターも居間のテレビ受像機も、疎遠なる日々の始まりでもあった。
石巻市の渡波という水産加工業を地場産業とする町で、中学浪人が始まった。宅浪生の生活圏にある渡波小学校の校門前の、ハタナカ書店という、文房具も販売している本屋が、私にとっての、蘭学者にとっての江戸時代の、長崎、また、“出島”のようなものであった。その本屋で、母から書籍代をもらい、本の渉猟が、17才の私の気休め、知的娯楽、また、“教養という大寺院”の書庫の山門が見習い禅僧の本選びの端緒ともなった。
読書は、入門以前の、超入門、それも、名前くらいは知ってもいた、芥川龍之介の新潮文庫本の全てを購入した、これは、高校生になって気づくことでもあったのだが、やはり、日本文学で、語彙力を豊富にするには、この芥川はもちろんだが、森鴎外と三島由紀夫がとても勉強になる、自身よりも国語ができる級友に“マウントを取る”、いわば、言葉において優越感に浸れる、言葉の多彩さ、難易度というものの教師ともなる三大作家であることに覚醒した。語彙と文章のハーモニー、つまり、文体というものに強烈なるインパクトを与えられた。因に、この芥川の系譜に入る典型的作家が、教科書でもおなじみの中嶋敦である。漢籍の素養で、芥川を凌ぐ名文家でもある。
この芥川の作品は、漢字が無理なき程度で高度なのだ。文章も明晰で分かりやすかった。それとは対照的な作家、志賀直哉も新潮文庫で、長編『暗夜行路』、中編『和解』なども含め、特に、短編のほとんどを読んだ。読みやすい。漢字とひらがなの塩梅が絶妙で、ヘミングウェイの文体に似ているな!と、その後実感したものである。中卒でも読める語彙の文でありながらも、大卒をも唸らせる文章という見本のような文体である。これは、その後、様々な文豪による『文章読本』{谷崎・川端・三島・中村真一郎・丸谷才一など}なるものを、読んだとき、その中の代表格の谷崎潤一郎が、志賀の文体を絶賛していたことに、得心したものである。志賀直哉が、“小説の神様”とされる所以の一つでもある。
この時期(中学浪人時代)は、芥川と志賀の短編小説で、小説を読む面白さ、楽しさのようなものを教えられたが、唯一、長編小説で、最も感銘を受けた作品が、北杜夫の『楡家の人々』でもあった。“なんと!小説ってこんなにも面白いのか!こんな素晴らしい世界があったのか!”と、読書の悦びを教えてもくれた最大の恩人は、この作品でもあった。この作品体験と同様の感銘をうけたのが、芥川賞作家磯崎憲一郎氏でもある。そのことを、近年、朝日新聞投稿コラムで知った。因に、この作品は、三島由紀夫が、超絶賛している点でも、その書評で記している的確なる批評が、私の文学的感性と同類のものであると、経験が浅い我ながら、文豪の知的感性に自信を与えられた記憶がある。本からの、圧倒的な感動とやらを覚えた瞬間である。「風立ちぬ、いざ、生きねばならぬ」(ヴァレリー)を捩って、「本立ちぬ、いざ、読まねばならなぬ」と実感したひと時でもある。
更に、この『楡家の人々』という作品、ドイツのトーマス・マンの『ブッテンブローグ家の人々』に、北が影響を受けて書いたともいうエピソードを知り、その後、大学時代に、最も読み込んだドイツ人作家で、最も偉大な20世紀の作家の一人として、このマンは、自身の愛好する文豪ともなる。彼の小説『ベニスに死す』がきっかけともなり、その後、芸術映画の最高峰ルキノ・ヴィスコンティの『ベニスに死す』の存在を知り、その作品群を観るまでになる。大学時代の、彼の映画作品を、ほぼ観るようになる。そして、この映画の中の、マーラーの交響曲第五番、それにえらく惹かれ、マーラーという作曲家の存在を知り、彼をも聴くようになってもゆく。私の芸術という水面の波紋は、このように広がってもいった。
最後に、高校受験の勉強の合間の息抜きに、このハタナカ書店に足を運び、書棚を見渡していると、とりわけ、『隠された十字架』という背文字が、私の眼を引いた。副題が、法隆寺の謎(法隆寺論)とも記してあった。あれ!これ、もしかしたら、錦糸中学校の社会科の先生で、非常に知的なオーラを放ってもいた柴本先生が、授業の雑談で、法隆寺が聖徳太子の鎮魂の寺、彼の怨霊を鎮めるために再建された寺であることを話していたな!法隆寺には、昔から不気味な謎がいっぱいある、そうした話をされていた光景がよみがえり、もしかしたら、あの柴本先生は、この本の内容を語っていたのかもしれないと直感した。その直感は正しかった。帯や目次などを眺めると、まさしく、そのことズバリであった。その場で、このハードカバーの『隠された十字架を』即購入し、知的ミステリーの世界へと足を踏み入れた。この書のおかげで、古代史、特に、飛鳥から天平といった奈良時代は、超得意ともなり、歴史への自信へと結びついた。この書に刺激を受けて、『水底の歌』という、柿本人麻呂論の書、あれは罪人として石見の国に流されたとする説の本である。この本に出てくる、歌人斎藤茂吉にも興味をもった。この茂吉は、芥川が最も評価する近代歌人でもあることも、その後知った。更に、この茂吉、あの北杜夫の『楡家の人々』の登場人物であり、北氏の父であることも興味がそそられる一因ともなる。更に、梅原には自伝的作品『学問のすすめ』というものがあり、三冊目は、これを読んだ。 この三冊目の『学問のすすめ』に関しては、次回語るとする。
余談だが、毎日出版文化賞というものが、『隠された十字架』や『楡家の人々』に、それぞれ、帯に記されてもいた。また、大佛次郎賞という文字も、『水底の歌』の帯に配されてもいた。三島由紀夫の『金閣寺』や安倍公房の『砂の女』といった彼らの代名詞ともなった名作などは、読売文学賞というもの受賞している。高校時代は、出版社系の文学賞よりも、三大新聞社が主催する文学賞の方が“凄い!”という印象を私に植え付けものである。
さらに、高校1年時に読んだ第26回江戸川乱歩賞を受賞した『猿丸幻視行』も面白く読んだが、その作者井沢元彦氏は、その後歴史関係の書籍をだされてもゆくが、彼の歴史観は、実は、根底で、梅原古代史観、歴史観といったものの系譜であり、彼の説や考えにも、梅原史観と同じくらいに影響を受けることになる。怨霊と言霊といったキーワードから歴史を観る眼である。
石巻市の渡波という水産加工業を地場産業とする町で、中学浪人が始まった。宅浪生の生活圏にある渡波小学校の校門前の、ハタナカ書店という、文房具も販売している本屋が、私にとっての、蘭学者にとっての江戸時代の、長崎、また、“出島”のようなものであった。その本屋で、母から書籍代をもらい、本の渉猟が、17才の私の気休め、知的娯楽、また、“教養という大寺院”の書庫の山門が見習い禅僧の本選びの端緒ともなった。
読書は、入門以前の、超入門、それも、名前くらいは知ってもいた、芥川龍之介の新潮文庫本の全てを購入した、これは、高校生になって気づくことでもあったのだが、やはり、日本文学で、語彙力を豊富にするには、この芥川はもちろんだが、森鴎外と三島由紀夫がとても勉強になる、自身よりも国語ができる級友に“マウントを取る”、いわば、言葉において優越感に浸れる、言葉の多彩さ、難易度というものの教師ともなる三大作家であることに覚醒した。語彙と文章のハーモニー、つまり、文体というものに強烈なるインパクトを与えられた。因に、この芥川の系譜に入る典型的作家が、教科書でもおなじみの中嶋敦である。漢籍の素養で、芥川を凌ぐ名文家でもある。
この芥川の作品は、漢字が無理なき程度で高度なのだ。文章も明晰で分かりやすかった。それとは対照的な作家、志賀直哉も新潮文庫で、長編『暗夜行路』、中編『和解』なども含め、特に、短編のほとんどを読んだ。読みやすい。漢字とひらがなの塩梅が絶妙で、ヘミングウェイの文体に似ているな!と、その後実感したものである。中卒でも読める語彙の文でありながらも、大卒をも唸らせる文章という見本のような文体である。これは、その後、様々な文豪による『文章読本』{谷崎・川端・三島・中村真一郎・丸谷才一など}なるものを、読んだとき、その中の代表格の谷崎潤一郎が、志賀の文体を絶賛していたことに、得心したものである。志賀直哉が、“小説の神様”とされる所以の一つでもある。
この時期(中学浪人時代)は、芥川と志賀の短編小説で、小説を読む面白さ、楽しさのようなものを教えられたが、唯一、長編小説で、最も感銘を受けた作品が、北杜夫の『楡家の人々』でもあった。“なんと!小説ってこんなにも面白いのか!こんな素晴らしい世界があったのか!”と、読書の悦びを教えてもくれた最大の恩人は、この作品でもあった。この作品体験と同様の感銘をうけたのが、芥川賞作家磯崎憲一郎氏でもある。そのことを、近年、朝日新聞投稿コラムで知った。因に、この作品は、三島由紀夫が、超絶賛している点でも、その書評で記している的確なる批評が、私の文学的感性と同類のものであると、経験が浅い我ながら、文豪の知的感性に自信を与えられた記憶がある。本からの、圧倒的な感動とやらを覚えた瞬間である。「風立ちぬ、いざ、生きねばならぬ」(ヴァレリー)を捩って、「本立ちぬ、いざ、読まねばならなぬ」と実感したひと時でもある。
更に、この『楡家の人々』という作品、ドイツのトーマス・マンの『ブッテンブローグ家の人々』に、北が影響を受けて書いたともいうエピソードを知り、その後、大学時代に、最も読み込んだドイツ人作家で、最も偉大な20世紀の作家の一人として、このマンは、自身の愛好する文豪ともなる。彼の小説『ベニスに死す』がきっかけともなり、その後、芸術映画の最高峰ルキノ・ヴィスコンティの『ベニスに死す』の存在を知り、その作品群を観るまでになる。大学時代の、彼の映画作品を、ほぼ観るようになる。そして、この映画の中の、マーラーの交響曲第五番、それにえらく惹かれ、マーラーという作曲家の存在を知り、彼をも聴くようになってもゆく。私の芸術という水面の波紋は、このように広がってもいった。
最後に、高校受験の勉強の合間の息抜きに、このハタナカ書店に足を運び、書棚を見渡していると、とりわけ、『隠された十字架』という背文字が、私の眼を引いた。副題が、法隆寺の謎(法隆寺論)とも記してあった。あれ!これ、もしかしたら、錦糸中学校の社会科の先生で、非常に知的なオーラを放ってもいた柴本先生が、授業の雑談で、法隆寺が聖徳太子の鎮魂の寺、彼の怨霊を鎮めるために再建された寺であることを話していたな!法隆寺には、昔から不気味な謎がいっぱいある、そうした話をされていた光景がよみがえり、もしかしたら、あの柴本先生は、この本の内容を語っていたのかもしれないと直感した。その直感は正しかった。帯や目次などを眺めると、まさしく、そのことズバリであった。その場で、このハードカバーの『隠された十字架を』即購入し、知的ミステリーの世界へと足を踏み入れた。この書のおかげで、古代史、特に、飛鳥から天平といった奈良時代は、超得意ともなり、歴史への自信へと結びついた。この書に刺激を受けて、『水底の歌』という、柿本人麻呂論の書、あれは罪人として石見の国に流されたとする説の本である。この本に出てくる、歌人斎藤茂吉にも興味をもった。この茂吉は、芥川が最も評価する近代歌人でもあることも、その後知った。更に、この茂吉、あの北杜夫の『楡家の人々』の登場人物であり、北氏の父であることも興味がそそられる一因ともなる。更に、梅原には自伝的作品『学問のすすめ』というものがあり、三冊目は、これを読んだ。 この三冊目の『学問のすすめ』に関しては、次回語るとする。
余談だが、毎日出版文化賞というものが、『隠された十字架』や『楡家の人々』に、それぞれ、帯に記されてもいた。また、大佛次郎賞という文字も、『水底の歌』の帯に配されてもいた。三島由紀夫の『金閣寺』や安倍公房の『砂の女』といった彼らの代名詞ともなった名作などは、読売文学賞というもの受賞している。高校時代は、出版社系の文学賞よりも、三大新聞社が主催する文学賞の方が“凄い!”という印象を私に植え付けものである。
さらに、高校1年時に読んだ第26回江戸川乱歩賞を受賞した『猿丸幻視行』も面白く読んだが、その作者井沢元彦氏は、その後歴史関係の書籍をだされてもゆくが、彼の歴史観は、実は、根底で、梅原古代史観、歴史観といったものの系譜であり、彼の説や考えにも、梅原史観と同じくらいに影響を受けることになる。怨霊と言霊といったキーワードから歴史を観る眼である。
2024年12月23日 17:13