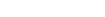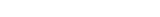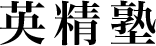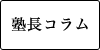カテゴリ
- おすすめの参考書
- 保護者の方へ (10)
- 2020年問題 (3)
- おすすめの教養書
月別 アーカイブ
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (5)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (5)
- 2024年3月 (4)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (4)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (5)
- 2021年12月 (7)
- 2021年11月 (4)
- 2021年10月 (5)
- 2021年9月 (4)
- 2021年8月 (4)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (10)
- 2021年4月 (5)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (7)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (7)
- 2020年6月 (6)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (5)
- 2020年3月 (5)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (4)
- 2019年12月 (5)
- 2019年11月 (5)
- 2019年10月 (4)
- 2019年9月 (5)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (5)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (6)
- 2019年3月 (6)
- 2019年2月 (3)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (7)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (3)
- 2018年7月 (4)
最近のエントリー
HOME > コラム > 私の読書の深層心理~こういう読書人もいる!~
コラム
私の読書の深層心理~こういう読書人もいる!~
幼少期からの読書、遅まきながらの読書、この決定的な違いはどこにありましょうや?それは、真という意味での、読書の楽しみ、読書の愉楽、読書の快感を味わえるかどうかにあるやも知れません。
まず、私は、幼少期からテレビっ子で、アニメーションで日がな一日過ごしてもきた典型的昭和テレビ世代でもあります。おまけに、両親は全く読書とは無縁の人間、したがって、もの心がついた頃から、両親から絵本など読み聞かせの習慣もなく、活字や言葉といったものに接するのは、小学校1年からの国語の授業でのみというありさまでもあった。そして、小学校5年くらいだったろうか、自身より勉強ができるM君から、或るマンガコミック本「キャプテン」という野球マンガを勧められて以降、それを読み始めたのが、マンガ本、つまり、紙の本への端緒ともなったのです。この紙のコミックマンガ本は、週に数冊、特に野球系マンガのものを購入しては、テレビアニメと並行して、マンガ本の世界に没入してゆきました。でも、このコラムで数回にわたり語ってもきたように、活字オンリーの、いわゆる、小説や物語は、高校1年になるまで、一切無縁の生活を送ってもきました。活字、言葉のみの世界が、嫌で、嫌で堪らず、敬遠してきた十代前半でもありました。
17才で、両親の離婚から、高校中退、そして中学浪人のさなかに、やっと活字のみの世界、言葉で表徴する世界へのイマジネーションの飛翔という、翼を身に付けた、つまりは、読書の悦びを知ったわけであります。
しかしでありますが、この遅まきながらの読書という経験、率直に申せば、読書の快感とやらは、小学校低学年までのアニメの世界、中学校3年までのマンガの世界、こうした映像や劇画に接してこみ上げてくる面白さや楽しさといったものに、正直及ばないといった程度でもあり、それは、丁度、松本清張の『砂の器』の映画と彼自身の小説の両方を天秤にかけた場合、前者の方が断然感動の度合いは優っているといった、一般人の感想に似たものとも言えましょうか。余談ではありますが、清張自身、この映画は、原作に優っていると語ったほどの名作ではあります。単刀直入に言えば、映像と音楽、そして橋本忍の脚本の力といった総合力の勝利でもありましょう。
人間とは、<安きに流れる習性:苦痛が伴わない>、<易きに靡く気質:単純明解でわかりやすい>があるとも言える人性論の文脈から言えば、アニメーション⇒マンガ本⇒読書(活字のみの世界)という年齢上昇によって、逆行して身についた自身の、安直で安易なる資質には抗いがたいもので、幼児に身についた習慣は、まるで、第二外国語(12才から学ぶ英語)に対する母国語のように、厄介なる自身の内面の文化のようなものとして無意識世界に沈殿してもいるという実体があります。それは、江戸末期に青春を過ごした人間が、明治期に、違和感を覚えながらも、散切り頭の自身を文明化していったように、また、明治期に青春を過ごした若者が、大正デモクラシーに馴染めぬメンタルを有していたように、さらに、昭和初期に、いわば、戦前学生であった者が、戦後の民主主義社会に、どこか心理的距離を置いて生きていかざるをえなかったように、あの三島由紀夫が、ビートルズを理解できなかったように、どうしても、自身の青春時代の原体験の喜びというものが、その後の人生の趣味・娯楽の基軸を規定してしまう事実は、人性論的観点から、当然の帰結とも申せましょう。
昭和の終わり頃までは、英語に関しては、紙の辞書が当たりまえ、平成の後半頃までは、電子辞書が主流ともなり、今や、令和7年にいたるや、ほぼ、スマホの辞書機能で、分からない単語を引く時代にもなっている現実から、近年の若者に、紙の辞書を使えというのは、ちょうど、自身の経歴でもある、超アニメ世代に、マンガを通り越し、活字の読書を強要するようなものでもありましょう。事実、私は、修行のように読書を始めたわけです。苦痛以外のなにものでもない、それ以前に、悦びなどを覚えた動画や劇画に比べれば、時間もかかる、言葉のイメージ喚起する労力など、感動などとは無縁の行為とすら言えるのではないでしょうか。
今話題の本『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(三宅香帆)〔集英社新書〕の文脈でいえば、この本を読まない人種は、小中時代は読書はしてきた、本が好きでもあった連中を前提にしています。この筆者自身が、小学校から大学まで文学少女、読書人間でもあった、それをフォーマットとして、この書を世に問うたわけでもありましょう。そうした彼らが、社会人になると、仕事に追われて、読書をする労力・意欲がなくなる、消耗してしまう現実的事例の暴露本であり、私のような種族とは、一線を画すともいえましょう。私なんぞは、そもそも、小学校から中学校まで全く本など読んでこなかった部族でもありますから。高校を中退せず、東京で理系人間で仕事をしていれば、アニメやマンガオンリーの非読書人であり続けたことでしょう。<たら・ればの私>であれば、この令和、こうした本の内容など、夢物語、神話上のことでもあったでしょう。
遅れてきた帝国、プロイセン王国のという謂いがあります。18世紀になって台頭して、第一次大戦までに、世界一の産業国ともなったプロセイン王国(ドイツ第二帝国)のことです。この、産業革命なども含め、日本も同様なのですが、遅れての、近代化した国家というものは、どこか、脆弱にして、危うい点があるものです。どこかしらの無理が祟って、この両国、第1次、第2次、それぞれの大戦で惨敗を舐めました。私などの、遅まきながらの読書人とは、国家レベルの戦争というものの次元に引き寄せて申せば、やはり、共通一次試験やセンター試験の現代文、そして、国公立の二次の現代文や早稲田大学の現代文などでは、苦労した経験があることを考えると、やはり、読書(近代化)と国語という教科・現代文という入試問題(総力戦という近代戦争)には、複雑な関係が潜在していると考えられます。その角度からは、次回語ってみようとか思います。
遅れてきた読書族、私を含めてなのですが、どうも、アニメの映像、マンガの劇画、そうしたイメージという直接的なインパクトなるもの、それは映画やドラマも含めてなのですが、どうも、隔靴掻痒のごとく、そうした存在に比べて、読書という存在からの感動というもは、“もやもや感の伴う感動”しか味わってもこなかたように思われるのです。『七人の侍』を先に観て感動し、それをリメイクした『荒野の七人』をその後に観る大人、子どもがディズニーアニメを吹き替えで観るのと字幕で観るのとの違いに似たものがありましょうか。いや、山下達郎の名曲『クリスマス・イヴ』と他のアーティストがカヴァーした『クリスマス・イヴ』を聴いた、その心のゆすぶられ方の大きさの違いともいえるものです。これは、山下達郎の弁ですが、「その曲は、初めて聴いた時のその楽曲が一番いいと感じる習性が聴衆(人間)にはある」といった説まで想起させられてしまいます。また、翻訳本で世界の名作、例えば、『老人と海』や『異邦人』を読んだ時の感動と、英語や仏語で、それらを、文法を意識し、辞書を片手に読み込んでゆく営為の感動の違いとも申せましょうか。当然、私の英語力や仏語力のなさを考慮しての前提があってのことです。
私の読書の、十代後半の第一の目的とは、精神の健康、知の体力、そうしたものの涵養にも似た、一種、<教養の筋トレ>の一環ですらあったように思われるのです。なぜ、そうした筋トレをするのか?恐らく、大方の人の返答は、マッチョな肉体を得たい、また、筋肉をつけて、健康体質でいたい、恐らく、見た目と内面のメンテナスというのが主目的で、“読書”を日々怠らないのがモチベーションではないかとおもいます。中高生の英検・漢検取得の動機に似たものでもありましょう。楽しい以前に、それをやった後の、自己の肉体の美、そして、健康体質、これのために行うのが、筋トレであり、私の読書は、まさにこれにあたってもいたように思われるのです。今でも、この意図は、薄れてはきましたが、半分近く残存しています。
まず、私は、幼少期からテレビっ子で、アニメーションで日がな一日過ごしてもきた典型的昭和テレビ世代でもあります。おまけに、両親は全く読書とは無縁の人間、したがって、もの心がついた頃から、両親から絵本など読み聞かせの習慣もなく、活字や言葉といったものに接するのは、小学校1年からの国語の授業でのみというありさまでもあった。そして、小学校5年くらいだったろうか、自身より勉強ができるM君から、或るマンガコミック本「キャプテン」という野球マンガを勧められて以降、それを読み始めたのが、マンガ本、つまり、紙の本への端緒ともなったのです。この紙のコミックマンガ本は、週に数冊、特に野球系マンガのものを購入しては、テレビアニメと並行して、マンガ本の世界に没入してゆきました。でも、このコラムで数回にわたり語ってもきたように、活字オンリーの、いわゆる、小説や物語は、高校1年になるまで、一切無縁の生活を送ってもきました。活字、言葉のみの世界が、嫌で、嫌で堪らず、敬遠してきた十代前半でもありました。
17才で、両親の離婚から、高校中退、そして中学浪人のさなかに、やっと活字のみの世界、言葉で表徴する世界へのイマジネーションの飛翔という、翼を身に付けた、つまりは、読書の悦びを知ったわけであります。
しかしでありますが、この遅まきながらの読書という経験、率直に申せば、読書の快感とやらは、小学校低学年までのアニメの世界、中学校3年までのマンガの世界、こうした映像や劇画に接してこみ上げてくる面白さや楽しさといったものに、正直及ばないといった程度でもあり、それは、丁度、松本清張の『砂の器』の映画と彼自身の小説の両方を天秤にかけた場合、前者の方が断然感動の度合いは優っているといった、一般人の感想に似たものとも言えましょうか。余談ではありますが、清張自身、この映画は、原作に優っていると語ったほどの名作ではあります。単刀直入に言えば、映像と音楽、そして橋本忍の脚本の力といった総合力の勝利でもありましょう。
人間とは、<安きに流れる習性:苦痛が伴わない>、<易きに靡く気質:単純明解でわかりやすい>があるとも言える人性論の文脈から言えば、アニメーション⇒マンガ本⇒読書(活字のみの世界)という年齢上昇によって、逆行して身についた自身の、安直で安易なる資質には抗いがたいもので、幼児に身についた習慣は、まるで、第二外国語(12才から学ぶ英語)に対する母国語のように、厄介なる自身の内面の文化のようなものとして無意識世界に沈殿してもいるという実体があります。それは、江戸末期に青春を過ごした人間が、明治期に、違和感を覚えながらも、散切り頭の自身を文明化していったように、また、明治期に青春を過ごした若者が、大正デモクラシーに馴染めぬメンタルを有していたように、さらに、昭和初期に、いわば、戦前学生であった者が、戦後の民主主義社会に、どこか心理的距離を置いて生きていかざるをえなかったように、あの三島由紀夫が、ビートルズを理解できなかったように、どうしても、自身の青春時代の原体験の喜びというものが、その後の人生の趣味・娯楽の基軸を規定してしまう事実は、人性論的観点から、当然の帰結とも申せましょう。
昭和の終わり頃までは、英語に関しては、紙の辞書が当たりまえ、平成の後半頃までは、電子辞書が主流ともなり、今や、令和7年にいたるや、ほぼ、スマホの辞書機能で、分からない単語を引く時代にもなっている現実から、近年の若者に、紙の辞書を使えというのは、ちょうど、自身の経歴でもある、超アニメ世代に、マンガを通り越し、活字の読書を強要するようなものでもありましょう。事実、私は、修行のように読書を始めたわけです。苦痛以外のなにものでもない、それ以前に、悦びなどを覚えた動画や劇画に比べれば、時間もかかる、言葉のイメージ喚起する労力など、感動などとは無縁の行為とすら言えるのではないでしょうか。
今話題の本『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(三宅香帆)〔集英社新書〕の文脈でいえば、この本を読まない人種は、小中時代は読書はしてきた、本が好きでもあった連中を前提にしています。この筆者自身が、小学校から大学まで文学少女、読書人間でもあった、それをフォーマットとして、この書を世に問うたわけでもありましょう。そうした彼らが、社会人になると、仕事に追われて、読書をする労力・意欲がなくなる、消耗してしまう現実的事例の暴露本であり、私のような種族とは、一線を画すともいえましょう。私なんぞは、そもそも、小学校から中学校まで全く本など読んでこなかった部族でもありますから。高校を中退せず、東京で理系人間で仕事をしていれば、アニメやマンガオンリーの非読書人であり続けたことでしょう。<たら・ればの私>であれば、この令和、こうした本の内容など、夢物語、神話上のことでもあったでしょう。
遅れてきた帝国、プロイセン王国のという謂いがあります。18世紀になって台頭して、第一次大戦までに、世界一の産業国ともなったプロセイン王国(ドイツ第二帝国)のことです。この、産業革命なども含め、日本も同様なのですが、遅れての、近代化した国家というものは、どこか、脆弱にして、危うい点があるものです。どこかしらの無理が祟って、この両国、第1次、第2次、それぞれの大戦で惨敗を舐めました。私などの、遅まきながらの読書人とは、国家レベルの戦争というものの次元に引き寄せて申せば、やはり、共通一次試験やセンター試験の現代文、そして、国公立の二次の現代文や早稲田大学の現代文などでは、苦労した経験があることを考えると、やはり、読書(近代化)と国語という教科・現代文という入試問題(総力戦という近代戦争)には、複雑な関係が潜在していると考えられます。その角度からは、次回語ってみようとか思います。
遅れてきた読書族、私を含めてなのですが、どうも、アニメの映像、マンガの劇画、そうしたイメージという直接的なインパクトなるもの、それは映画やドラマも含めてなのですが、どうも、隔靴掻痒のごとく、そうした存在に比べて、読書という存在からの感動というもは、“もやもや感の伴う感動”しか味わってもこなかたように思われるのです。『七人の侍』を先に観て感動し、それをリメイクした『荒野の七人』をその後に観る大人、子どもがディズニーアニメを吹き替えで観るのと字幕で観るのとの違いに似たものがありましょうか。いや、山下達郎の名曲『クリスマス・イヴ』と他のアーティストがカヴァーした『クリスマス・イヴ』を聴いた、その心のゆすぶられ方の大きさの違いともいえるものです。これは、山下達郎の弁ですが、「その曲は、初めて聴いた時のその楽曲が一番いいと感じる習性が聴衆(人間)にはある」といった説まで想起させられてしまいます。また、翻訳本で世界の名作、例えば、『老人と海』や『異邦人』を読んだ時の感動と、英語や仏語で、それらを、文法を意識し、辞書を片手に読み込んでゆく営為の感動の違いとも申せましょうか。当然、私の英語力や仏語力のなさを考慮しての前提があってのことです。
私の読書の、十代後半の第一の目的とは、精神の健康、知の体力、そうしたものの涵養にも似た、一種、<教養の筋トレ>の一環ですらあったように思われるのです。なぜ、そうした筋トレをするのか?恐らく、大方の人の返答は、マッチョな肉体を得たい、また、筋肉をつけて、健康体質でいたい、恐らく、見た目と内面のメンテナスというのが主目的で、“読書”を日々怠らないのがモチベーションではないかとおもいます。中高生の英検・漢検取得の動機に似たものでもありましょう。楽しい以前に、それをやった後の、自己の肉体の美、そして、健康体質、これのために行うのが、筋トレであり、私の読書は、まさにこれにあたってもいたように思われるのです。今でも、この意図は、薄れてはきましたが、半分近く残存しています。
2025年1月13日 17:14