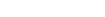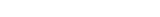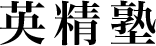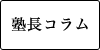カテゴリ
- おすすめの参考書
- 保護者の方へ (10)
- 2020年問題 (3)
- おすすめの教養書
月別 アーカイブ
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (5)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (5)
- 2024年3月 (4)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (4)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (5)
- 2021年12月 (7)
- 2021年11月 (4)
- 2021年10月 (5)
- 2021年9月 (4)
- 2021年8月 (4)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (10)
- 2021年4月 (5)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (7)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (7)
- 2020年6月 (6)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (5)
- 2020年3月 (5)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (4)
- 2019年12月 (5)
- 2019年11月 (5)
- 2019年10月 (4)
- 2019年9月 (5)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (5)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (6)
- 2019年3月 (6)
- 2019年2月 (3)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (7)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (3)
- 2018年7月 (4)
最近のエントリー
コラム
<私の将来の夢>の思春期の変遷
前回にも言及したように、私の読書の動機は、中学浪人から高校一年くらいまでは、国語の成績を伸ばそうという単純なものでありました。そして、高校2年くらいからは、自身の負の人生の昇華として、いつか小説のようなものを書いて、小中高の自身の経験のマイナスをプラスに転化してみたいといったかすかな野心のようなもの、その武器として表現力・文章力、そういった技能を身に付け、磨いてもいきたいというものになってもいった。そうした読書には、純粋な喜びや素直な感動というものは二の次でもあったでありましょう。それは、大学時代に遊びまわり、ろくすっぽ勉強もせず、サークルやアルバイトにあけくれて、超有名企業の社員ともなり、その環境で、教養といったものを痛感し、古今東西の古典から、政治経済などの書物を読み始める動機にも似た、明治から昭和の名作にその文体や語彙を吸収する、一種、邪道の、不純な動機の読書でもあったろうと思われるのです。
この、淡い将来のモノ書きへの憧れ、目標といったものが、薄れる、いや、ライバルとして浮上してきたのは、大学受験の宅浪後の、予備校時代の講師の面々の姿、彼らの職業でした。この予備校時代に、9割ほど、将来の作家志望の目標が、4割に、そして、予備講師の目標が、5割へとなったわけでもあります。そして、大学に入るや、本来ならば、なんでも読み漁る<子供の読書>期間でもある濫読時代、“大人の濫読”時代が始まるのです。思想哲学、海外文学、歴史小説、政治経済、マーケティングなど、様々な書籍を読み始めたのです。理由は、詳しくは、語りませんが、この大学4年間で、特に、時代はバブルでもあった、また、P・ドラッカーから松下幸之助、本田宗一郎、井深大と盛田昭夫、そして小林一三{この人がリアルに響いた!:作家志望から伝説的経営者となった傑物}などの戦後日本経済を民の面から貢献した立志伝中の偉人などの影響を受けました。これらの人物は、リアルに、私には、“ビジネスの“信玄・信長・秀吉・家康”のように見えたものです。当時はベンチャー企業とも言われ、今では、スタートアップ企業ともいう、自身の会社など、また、大手の傘下の子会社を、上場に育て上げたい{※ヨーカ堂の子会社セブンイレブンを上場企業に}などとビジネス的野心も加味し、大学4年時には、将来、作家志望3割、予備校講師3割、そして、新規事業をいつか立ち上げたいという企業家精神が3割、そういった将来の目論見、夢が、三叉路の如く、私の面前に伸びてもいったものです。この点で、卒業後進む業界でもある、流通業界で、三国時代とも言える、“ダイエー、ヨーカドー、セゾングループ(西武・西友)”で、興味関心が一番惹かれたのは、セゾングループの堤清二でもありました。経営者にして作家でもあり、西武美術館を立ち上げたり、インテリ経営者という面も、興味の対象でありました。ここでは、これ以上の自身の将来像としての職業には言及しません。機会があれば、私の職業観といったものとして、別の機会にこの場で語ってみたいと思います。
本題に戻ります。そうです。私の、特に、高校時代は、将来モノ書きの修練の場として読書があったわけであります。
高校時時代は、特に、いや、日本文学作品だけを読んでいました。それも、新潮文庫には、どれほどお世話になったことでありましょう。絶版、もしくは廃版ともなった文庫は、わざわざ新潮社に、在庫はありますか?とハガキで書いて、問い合わせ、購入することが多かった。特に、横光利一や福永武彦は、そうやって作品を手に入れて読み耽りました。同じ作品でも、岩波文庫や、講談社文庫,角川文庫を避け、とりわけ新潮文庫を選んでいました。特に紐のしおりが魅力的で重宝できた点もあったと思われます。何より、私の好みの作家は、新潮文庫でだいたい読めたからでもあります。『寺田寅彦随筆集』(五巻)や『古寺巡礼』・『風土』(和辻哲郎)など、漱石の弟子たちの作家は、岩波文庫でよまざるをえないものはそうもしました。谷崎の『陰翳礼讃』などは、中公文庫でしか読めませんでした。当然、最も影響をうけた三島由紀夫や小林秀雄などは、高価な全集を買わなくても、新潮文庫で、名作のだいたいは読めたものです。海外文学は、大学生になって読んでやろうと目論んでもいた、日本文学の内海で航海法(文章技法など)を身に付け、大海(海外文学)に乗り出してやろうという読書的野心でもあったでありましょう。
生意気な弁ですが、高校3年時では、自身の好きな作家(横光利一・福永武彦・三島由紀夫など)は、メモなりノートなりに様々なことを記し、その時点で、大学の国文科の学生の卒論でも書ける域に達してもいて、当時、「もし、今、大学の国文科にいたら結構いい卒論を書けるのに!」と、現役時代、浪人時代など、歯がゆい思いをしたものです。そうです、大学に入る前は、将来国文科へと志してもいたのですが、予備校浪人時代の英語という教科、英語という言語、英語はどう読むべきか、さらに、それを面白おかしく、そしてためなる手法で、生徒に教鞭する予備校講師の姿と、その当時目にした、丸谷才一の「国文学を究めるなら、大学時代は、外国語を学び、外国文学を読み、大学院において国文学に手をつけよ」というような言葉に出会い、大学時代は、英文学だなと、一石二鳥の算段で大学に入りました。余談ではありますが、長きにわたる浪人時代{宅浪⇒駿台⇒代ゼミ}は、読書第一、受験勉強二の次、英単語を覚えたり、日本史や世界史の知識の暗記の時間を、読書に充てていたのが仇となり、多浪の大きな原因でもあったと思われます。普通の受験生は、その読書がテレビでもあったのが昭和の時代です。
入った慶應大学という、それも文学部は、一年時は、一般教養と称し、日吉キャンパスで、まだ二年次の専攻の学科が未定のカリキュラムのシステムでもあり、自身の大学1年の志望は、予備校講師の影響もあり、英文科でもありました。第二外国語は、フランス語を履修し、月と水の週二コマながら、自身で仏文法を、まじめに勉強した口でもあり、そこそこ、フランス語が、読めて、書けるレベルには到達してもいました。この内部進学(大学二年の専攻)において、従来の英文科に進むべきか、仏文科へ軌道修正すべきか悩みました。その、分岐点における模索・決断といったものを次回お話しするとしましょう。
この、淡い将来のモノ書きへの憧れ、目標といったものが、薄れる、いや、ライバルとして浮上してきたのは、大学受験の宅浪後の、予備校時代の講師の面々の姿、彼らの職業でした。この予備校時代に、9割ほど、将来の作家志望の目標が、4割に、そして、予備講師の目標が、5割へとなったわけでもあります。そして、大学に入るや、本来ならば、なんでも読み漁る<子供の読書>期間でもある濫読時代、“大人の濫読”時代が始まるのです。思想哲学、海外文学、歴史小説、政治経済、マーケティングなど、様々な書籍を読み始めたのです。理由は、詳しくは、語りませんが、この大学4年間で、特に、時代はバブルでもあった、また、P・ドラッカーから松下幸之助、本田宗一郎、井深大と盛田昭夫、そして小林一三{この人がリアルに響いた!:作家志望から伝説的経営者となった傑物}などの戦後日本経済を民の面から貢献した立志伝中の偉人などの影響を受けました。これらの人物は、リアルに、私には、“ビジネスの“信玄・信長・秀吉・家康”のように見えたものです。当時はベンチャー企業とも言われ、今では、スタートアップ企業ともいう、自身の会社など、また、大手の傘下の子会社を、上場に育て上げたい{※ヨーカ堂の子会社セブンイレブンを上場企業に}などとビジネス的野心も加味し、大学4年時には、将来、作家志望3割、予備校講師3割、そして、新規事業をいつか立ち上げたいという企業家精神が3割、そういった将来の目論見、夢が、三叉路の如く、私の面前に伸びてもいったものです。この点で、卒業後進む業界でもある、流通業界で、三国時代とも言える、“ダイエー、ヨーカドー、セゾングループ(西武・西友)”で、興味関心が一番惹かれたのは、セゾングループの堤清二でもありました。経営者にして作家でもあり、西武美術館を立ち上げたり、インテリ経営者という面も、興味の対象でありました。ここでは、これ以上の自身の将来像としての職業には言及しません。機会があれば、私の職業観といったものとして、別の機会にこの場で語ってみたいと思います。
本題に戻ります。そうです。私の、特に、高校時代は、将来モノ書きの修練の場として読書があったわけであります。
高校時時代は、特に、いや、日本文学作品だけを読んでいました。それも、新潮文庫には、どれほどお世話になったことでありましょう。絶版、もしくは廃版ともなった文庫は、わざわざ新潮社に、在庫はありますか?とハガキで書いて、問い合わせ、購入することが多かった。特に、横光利一や福永武彦は、そうやって作品を手に入れて読み耽りました。同じ作品でも、岩波文庫や、講談社文庫,角川文庫を避け、とりわけ新潮文庫を選んでいました。特に紐のしおりが魅力的で重宝できた点もあったと思われます。何より、私の好みの作家は、新潮文庫でだいたい読めたからでもあります。『寺田寅彦随筆集』(五巻)や『古寺巡礼』・『風土』(和辻哲郎)など、漱石の弟子たちの作家は、岩波文庫でよまざるをえないものはそうもしました。谷崎の『陰翳礼讃』などは、中公文庫でしか読めませんでした。当然、最も影響をうけた三島由紀夫や小林秀雄などは、高価な全集を買わなくても、新潮文庫で、名作のだいたいは読めたものです。海外文学は、大学生になって読んでやろうと目論んでもいた、日本文学の内海で航海法(文章技法など)を身に付け、大海(海外文学)に乗り出してやろうという読書的野心でもあったでありましょう。
生意気な弁ですが、高校3年時では、自身の好きな作家(横光利一・福永武彦・三島由紀夫など)は、メモなりノートなりに様々なことを記し、その時点で、大学の国文科の学生の卒論でも書ける域に達してもいて、当時、「もし、今、大学の国文科にいたら結構いい卒論を書けるのに!」と、現役時代、浪人時代など、歯がゆい思いをしたものです。そうです、大学に入る前は、将来国文科へと志してもいたのですが、予備校浪人時代の英語という教科、英語という言語、英語はどう読むべきか、さらに、それを面白おかしく、そしてためなる手法で、生徒に教鞭する予備校講師の姿と、その当時目にした、丸谷才一の「国文学を究めるなら、大学時代は、外国語を学び、外国文学を読み、大学院において国文学に手をつけよ」というような言葉に出会い、大学時代は、英文学だなと、一石二鳥の算段で大学に入りました。余談ではありますが、長きにわたる浪人時代{宅浪⇒駿台⇒代ゼミ}は、読書第一、受験勉強二の次、英単語を覚えたり、日本史や世界史の知識の暗記の時間を、読書に充てていたのが仇となり、多浪の大きな原因でもあったと思われます。普通の受験生は、その読書がテレビでもあったのが昭和の時代です。
入った慶應大学という、それも文学部は、一年時は、一般教養と称し、日吉キャンパスで、まだ二年次の専攻の学科が未定のカリキュラムのシステムでもあり、自身の大学1年の志望は、予備校講師の影響もあり、英文科でもありました。第二外国語は、フランス語を履修し、月と水の週二コマながら、自身で仏文法を、まじめに勉強した口でもあり、そこそこ、フランス語が、読めて、書けるレベルには到達してもいました。この内部進学(大学二年の専攻)において、従来の英文科に進むべきか、仏文科へ軌道修正すべきか悩みました。その、分岐点における模索・決断といったものを次回お話しするとしましょう。
2025年2月 3日 15:55