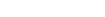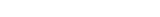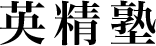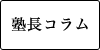カテゴリ
- おすすめの参考書
- 保護者の方へ (10)
- 2020年問題 (3)
- おすすめの教養書
月別 アーカイブ
- 2025年4月 (1)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (5)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (5)
- 2024年3月 (4)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (4)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (5)
- 2021年12月 (7)
- 2021年11月 (4)
- 2021年10月 (5)
- 2021年9月 (4)
- 2021年8月 (4)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (10)
- 2021年4月 (5)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (7)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (7)
- 2020年6月 (6)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (5)
- 2020年3月 (5)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (4)
- 2019年12月 (5)
- 2019年11月 (5)
- 2019年10月 (4)
- 2019年9月 (5)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (5)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (6)
- 2019年3月 (6)
- 2019年2月 (3)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (7)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (3)
- 2018年7月 (4)
最近のエントリー
コラム
④質か量か?~宗教を介した独学~
前回のコラムの続きとして、独学というものから、帰納法と演繹法へと、論を進めたいところなのだが、ここで、その、教育的帰納法と演繹法という主題へ移行する前に、独学というものが、真の意味で、純粋的に、どれほど無理があるのか、その困難性というもの、その角度から、少々脱線して語ってみることとする。
本、書籍のみを通した独学という難行は、宗教を介すると納得がゆくものと思われる。
そもそも宗教には、聖典というものがある。仏教だと、様々な“~経”といったもの、キリスト教には、聖書、イスラム教には、コーランといった本という存在がある。しかし、そのバイブルとやらは、子供が童話を、少年少女が名作を、自身で黙読して、その聖なる世界に目覚める類のものではない。両親や聖職者といった、生身の人間の声を介して、信仰の深まりへと到達する。思春期に、法華経や般若心経を読んで僧を志すとか、新約聖書を、中学時代に手に入れ、それを密かに読んでキリスト教徒に入信した者は皆無であろう。祖父の代からその宗派の仏壇が居間にあり、初詣などで、家族連れで寺社仏閣に赴く、その日蓮宗や浄土宗の門徒、いわゆる檀家であるのである。両親から、赤子、子どもの頃に洗礼を受けなどして、その聖書の世界へと踏み入っている者が大勢である。つまり、宗教とは、内発的というより、外部の人間の声や行為による外発的なものだ。遠藤周作など、まさしく、その典型でもあろう。彼は、もの心つかぬ頃の母から洗礼を受ける。その後、母との絆の証として、信仰を深めてもいった。宿命のクリスチャンでもある。
キリスト教を例にとろう。ルターの宗教改革で、聖書主義と称して、教会を経ずして、聖書のみに神の声があるとするプロテスタントが生まれたが、それでも、牧師という、その聖書の解釈者?いや、音読者、いわば、伝道師がいて初めて、布教、新教の浸透が可能ともなったのである。ここにも、本のみの、ある意味、独学の限界という命題が浮上しもくる。一個人の人間と書物(聖書・コーラン)の間には、必ず、生身の仲介者が存在する事実である。これは、生徒と教科書に、学校(教会)における教師(聖職者)が介在する関係そのものだ。
宗教改革と時機を同じくする、グーテンベルグの活版印刷による、聖書の書籍化、それによる、バイブルとしての神の声を載せた本なるものが誕生しても、やはり、聖職者が、その福音なるものに生を与えなければ、息吹を吹き込まなければ、信者の拡大に結び付かなかった。
下世話な例だが、大手予備校に、意図的に“カリスマ講師=金ぴか先生、コト、佐藤忠志のような講師”を誕生させて、その教祖的講師に参考書を執筆させて、そのカリスマ性をさらに増してゆく教育的マーケティング手法とも似ている。逆もまた、事実である。無名ではあるが、実力を持つ講師に、予備校系出版社から、参考書を出させて、その威信・威力に駆られ、有名、スター的自校のカリスマ講師に育て上げる、一種、芸能事務所的手法もある。
この教育産業的マーケティングが成功するルートは、この宗教と聖典の関係にも似ているのである。つまりは、英語であれ、数学であれ、国語であれ、やはり、その字面で書かれた内容を捉えるリテラシー能力に欠けている大衆がほとんであるという真実が垣間見えもする。ここに、独学の、一見きれい的にみえる手法の、実は、限界という実体が潜んでいるからだ。独学が出来きない、出来ても不十分な9割近い層の学びの上の、陥穽・虚妄・弱点をつく教育的マーケティング手法である。学習者も、学びにおいても、オルテガの言う、“大衆”に過ぎぬという真実である。
黙読という行為は、つまり、自室で、静かに、一人で書物と対峙する行為は、ここ、200年ほどの歴史しかないとも言われる。それ以前は、音読、朗読などを経ないと、深くその内容が読み込めない、理解できないという経緯がうかがえる。恐らく、日本でも、黙読は、近世の江戸時代になって普及したものと思われる。ここにも、遺伝子的に、本、参考書でも、独学する限界があった。江戸の武士・町人でも、幼少期はまず、声に出す素読が重視されたことでも理解できよう。読書が真の意味でできる子供、少年とは、それを目で追いながら、まるで、名優・名アナウンサーに朗読されているかの如く、内容が、場面が、映像のように脳裏によみがえる資質を有する部族のことでもある。
シェイクスピア研究者の石川実氏の引用だが、「戯曲とは、声に出して初めて完結する」という、その文脈でも、台本の範疇に入る戯曲・脚本などは、声に出してその世界がリアルに浮かびがってもくる証明でもあろう。名作『ハムレット』などは、生の芝居、また、ローレンス・オリビエの映画を観て、その素晴らしさ、凄さがわかるというものである。私なんぞは、そのあらすじに魅了されて、高校生の頃、福田恆存訳の新潮文庫で読んではみたものの、そのあらすじやプロットの先入観で“感動のフライング”をしてしまい、失望した記憶がある。この逆もまた真なりである。名作映画『砂の器』を観て、その後、原作の松本清張の小説を読んでも、感動は伝わらなかったという、同じ芸術上の摂理がうかがえる。これを、“芸術上の規則”ともいう。フランスの社会学者P・ブルデューの『芸術の規則』の文脈においてである。
実は、独学が可能な人、ある意味、知的天才とは、名演出家蜷川幸雄のような資質を有する人間なのだ。どんな台本{戯曲・脚本}に目を通しても、自身で、その究極的な世界がイメージされてしまう人のことなのだ。名指揮者、カラヤン、バーンスタイン、そして、小澤征爾なども、クラッシックの天才がしたためたスコアー(楽譜)を観て、その、モーツァルトやベートーヴェンの脳内の、美のイデー、いや、それ以上の、理想郷を、オーケストラを通じて再現してしまう天才でもある。これは、ポピュラーミュージックにおける名編曲者(アレンジャー)でも該当する。服部克久や山下達郎にも言える才能なのである。また、映画やドラマの名プロデューサー気質にも当てはまる。ある、どこにでもある素材を、それをもとして、美味しい料理{=作品が}できるシェフにもいいうることだ。この観点から大成功したのが、伝説的番組が『料理の鉄人』(フジテレビ)でもあろうか?
そうである、ある種・核、いや素材とでもいっていい、それを、本だと措定しよう。そこから、自身の技能なり、武器なり、自身の世界を構築できた者、それが、独学者の王道というものである。しかし、ここで、その独学者の大家であれ、やはり、ゼロから有、すなわち、1にしろ、2にしろ、5にしろ、それを生み出すことは至難の技なのである。彼らは、やはり、1を5に、2を10にした達人なのである。ここは、様々な宗教家、仏教徒を概観すると首肯できることでもある。次回は、この代表例、空海を例に話しを拡げてみたい。芸術であれ、思想であれ、独創性といったものは、皆無であるという仮説にも帰着する。
本、書籍のみを通した独学という難行は、宗教を介すると納得がゆくものと思われる。
そもそも宗教には、聖典というものがある。仏教だと、様々な“~経”といったもの、キリスト教には、聖書、イスラム教には、コーランといった本という存在がある。しかし、そのバイブルとやらは、子供が童話を、少年少女が名作を、自身で黙読して、その聖なる世界に目覚める類のものではない。両親や聖職者といった、生身の人間の声を介して、信仰の深まりへと到達する。思春期に、法華経や般若心経を読んで僧を志すとか、新約聖書を、中学時代に手に入れ、それを密かに読んでキリスト教徒に入信した者は皆無であろう。祖父の代からその宗派の仏壇が居間にあり、初詣などで、家族連れで寺社仏閣に赴く、その日蓮宗や浄土宗の門徒、いわゆる檀家であるのである。両親から、赤子、子どもの頃に洗礼を受けなどして、その聖書の世界へと踏み入っている者が大勢である。つまり、宗教とは、内発的というより、外部の人間の声や行為による外発的なものだ。遠藤周作など、まさしく、その典型でもあろう。彼は、もの心つかぬ頃の母から洗礼を受ける。その後、母との絆の証として、信仰を深めてもいった。宿命のクリスチャンでもある。
キリスト教を例にとろう。ルターの宗教改革で、聖書主義と称して、教会を経ずして、聖書のみに神の声があるとするプロテスタントが生まれたが、それでも、牧師という、その聖書の解釈者?いや、音読者、いわば、伝道師がいて初めて、布教、新教の浸透が可能ともなったのである。ここにも、本のみの、ある意味、独学の限界という命題が浮上しもくる。一個人の人間と書物(聖書・コーラン)の間には、必ず、生身の仲介者が存在する事実である。これは、生徒と教科書に、学校(教会)における教師(聖職者)が介在する関係そのものだ。
宗教改革と時機を同じくする、グーテンベルグの活版印刷による、聖書の書籍化、それによる、バイブルとしての神の声を載せた本なるものが誕生しても、やはり、聖職者が、その福音なるものに生を与えなければ、息吹を吹き込まなければ、信者の拡大に結び付かなかった。
下世話な例だが、大手予備校に、意図的に“カリスマ講師=金ぴか先生、コト、佐藤忠志のような講師”を誕生させて、その教祖的講師に参考書を執筆させて、そのカリスマ性をさらに増してゆく教育的マーケティング手法とも似ている。逆もまた、事実である。無名ではあるが、実力を持つ講師に、予備校系出版社から、参考書を出させて、その威信・威力に駆られ、有名、スター的自校のカリスマ講師に育て上げる、一種、芸能事務所的手法もある。
この教育産業的マーケティングが成功するルートは、この宗教と聖典の関係にも似ているのである。つまりは、英語であれ、数学であれ、国語であれ、やはり、その字面で書かれた内容を捉えるリテラシー能力に欠けている大衆がほとんであるという真実が垣間見えもする。ここに、独学の、一見きれい的にみえる手法の、実は、限界という実体が潜んでいるからだ。独学が出来きない、出来ても不十分な9割近い層の学びの上の、陥穽・虚妄・弱点をつく教育的マーケティング手法である。学習者も、学びにおいても、オルテガの言う、“大衆”に過ぎぬという真実である。
黙読という行為は、つまり、自室で、静かに、一人で書物と対峙する行為は、ここ、200年ほどの歴史しかないとも言われる。それ以前は、音読、朗読などを経ないと、深くその内容が読み込めない、理解できないという経緯がうかがえる。恐らく、日本でも、黙読は、近世の江戸時代になって普及したものと思われる。ここにも、遺伝子的に、本、参考書でも、独学する限界があった。江戸の武士・町人でも、幼少期はまず、声に出す素読が重視されたことでも理解できよう。読書が真の意味でできる子供、少年とは、それを目で追いながら、まるで、名優・名アナウンサーに朗読されているかの如く、内容が、場面が、映像のように脳裏によみがえる資質を有する部族のことでもある。
シェイクスピア研究者の石川実氏の引用だが、「戯曲とは、声に出して初めて完結する」という、その文脈でも、台本の範疇に入る戯曲・脚本などは、声に出してその世界がリアルに浮かびがってもくる証明でもあろう。名作『ハムレット』などは、生の芝居、また、ローレンス・オリビエの映画を観て、その素晴らしさ、凄さがわかるというものである。私なんぞは、そのあらすじに魅了されて、高校生の頃、福田恆存訳の新潮文庫で読んではみたものの、そのあらすじやプロットの先入観で“感動のフライング”をしてしまい、失望した記憶がある。この逆もまた真なりである。名作映画『砂の器』を観て、その後、原作の松本清張の小説を読んでも、感動は伝わらなかったという、同じ芸術上の摂理がうかがえる。これを、“芸術上の規則”ともいう。フランスの社会学者P・ブルデューの『芸術の規則』の文脈においてである。
実は、独学が可能な人、ある意味、知的天才とは、名演出家蜷川幸雄のような資質を有する人間なのだ。どんな台本{戯曲・脚本}に目を通しても、自身で、その究極的な世界がイメージされてしまう人のことなのだ。名指揮者、カラヤン、バーンスタイン、そして、小澤征爾なども、クラッシックの天才がしたためたスコアー(楽譜)を観て、その、モーツァルトやベートーヴェンの脳内の、美のイデー、いや、それ以上の、理想郷を、オーケストラを通じて再現してしまう天才でもある。これは、ポピュラーミュージックにおける名編曲者(アレンジャー)でも該当する。服部克久や山下達郎にも言える才能なのである。また、映画やドラマの名プロデューサー気質にも当てはまる。ある、どこにでもある素材を、それをもとして、美味しい料理{=作品が}できるシェフにもいいうることだ。この観点から大成功したのが、伝説的番組が『料理の鉄人』(フジテレビ)でもあろうか?
そうである、ある種・核、いや素材とでもいっていい、それを、本だと措定しよう。そこから、自身の技能なり、武器なり、自身の世界を構築できた者、それが、独学者の王道というものである。しかし、ここで、その独学者の大家であれ、やはり、ゼロから有、すなわち、1にしろ、2にしろ、5にしろ、それを生み出すことは至難の技なのである。彼らは、やはり、1を5に、2を10にした達人なのである。ここは、様々な宗教家、仏教徒を概観すると首肯できることでもある。次回は、この代表例、空海を例に話しを拡げてみたい。芸術であれ、思想であれ、独創性といったものは、皆無であるという仮説にも帰着する。
2025年3月17日 17:18