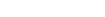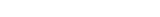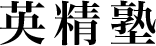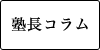カテゴリ
- おすすめの参考書
- 保護者の方へ (10)
- 2020年問題 (3)
- おすすめの教養書
月別 アーカイブ
- 2025年4月 (1)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (5)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (5)
- 2024年3月 (4)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (4)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (5)
- 2021年12月 (7)
- 2021年11月 (4)
- 2021年10月 (5)
- 2021年9月 (4)
- 2021年8月 (4)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (10)
- 2021年4月 (5)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (7)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (7)
- 2020年6月 (6)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (5)
- 2020年3月 (5)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (4)
- 2019年12月 (5)
- 2019年11月 (5)
- 2019年10月 (4)
- 2019年9月 (5)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (5)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (6)
- 2019年3月 (6)
- 2019年2月 (3)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (7)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (3)
- 2018年7月 (4)
最近のエントリー
HOME > コラム > ⑥質か量か?~ブランディングとマーケティング~
コラム
⑥質か量か?~ブランディングとマーケティング~
世に、マーケティングなる用語の認知度は高い。教え子の生徒なども、高校生ながら、将来大学に入ったらマーケティングを学び、その後社会人として、それを武器に会社に貢献したいなどと口にする者もいる。しかし、高校生はもちろん、大学生でも、ブランディングなる概念、手法、ビジネスツールなるものがあると知っているものは、恐らく、皆無、や少数派といっていいだろう。
そもそも、マーケティングとは、量の側面のビジネスツールである、一方、ブランディングとは、質の側面のそれ、ビジネススキルの範疇には入らぬ一種、暗黙知の世界やもしれない。また、陶工が、窯から出てこないとわからない名品とも言えなくもない、半分は自然・偶然の“神”の足が踏み入れる領域やもしれぬ。
マーケティングとは、面の戦術であり、いかに、市場のパイ、領域を獲得し、売り上げをあげるか、その手段である。時期や状況、時代時代で日々戦術を変えればならぬ手法でもある。それに対して、ブランディングとは、点、線の戦略であり、いかに、自社製品・商品の支持層を増やす、信頼度を増す、敢えて言えば、時代や状況を超越して、いかに利益をだすか、敢えていえば売り上げよりも利益を優先することを旨とする方法である。あのルイヴィトンの会社、LVMHを見れば一目瞭然である。ディズニーという会社も同様である。
この両面の、獲得に一番のジレンマを抱えている大企業は、平成で台頭した、ファーストファッション雄のユニクロと、携帯電話・スマホのソフトバンクや楽天でもあろう。前者は、百貨店で販売されているラルフに、後者は、ドコモやAUに、いまいち、ブランド力で劣ることは、周知の事実でもあろう。この三社、CMの露出度が際立ってもいることがその一つの証明であろうか?CMによる“自転車操業的マーケティング”である。“吠える犬は嚙みつかぬ”ではないが、CMやり放題の企業に限り、時代から落ちこぼれることを最も恐れる証左ともいえる。
一般論として、このマーケティングは、平時には強いが、窮時には弱い。ブランディングは、平時には、強いというより、安定感・信用度を増し、更に、窮時にこそ、その強味が発揮される。この証明として、昭和の松下幸之助の、「好況よし、不況さらによし」、その言葉が、ものの見事に、それを証明してもいよう。幸之助の自社ブランドへのゆるぎない自信、自負の表れである。卑近な例を挙げれば、巷の飲食業で、コロナ禍で消滅した店、今でも健在の店、それが、試金石ともなった事実である。
人間レベルいうところの、マーケティングは、知識であり、ブランディングとは、教養ともいいうるものだ。巧い喩えとは言えないが、昆布と鰹節、これが、知識であり、そこから抽出した“うまみ”・“だし”、これが教養ともいえるものだ。しかし、このうま味も生かすも殺すも、料理人の腕にかかっている。この名料理人とは、厨房だけからは生まれない。これは、知識力で、弁護士や公認会計士になっても、教養力がなければ、昼行燈の資格士に留まる“凡庸~士”であるのと同義である。知識は、計算づくで、いかようにも増やせるが、教養とは、計算づくで身につくものではない。そこにも、小泉信三の名言、「すぐに役に立つものは、すぐに役に立たなくなる」が輝きを増してもくる。この名言、その真意は、製品でいう質、人間の根幹ともいえる教養を指す。さらに、渋沢栄一の『論語と算盤』の題名にも、その皮肉なる暗示、警鐘が滲んでもいる。論語は教養、算盤は知識とも言えよう。ブランディングの真髄とは、“急がば回れ”のことわざの逆説の真理に行き着く。
今最も注目を浴びているマーケティングをする人、いわゆる、マーケターは、森岡毅氏でもあろう。マーケターは、落ち目企業、赤字企業を、脚光浴びる企業に、黒字企業には、出来ても、その後、ブランド化しうるか否かは、その人物(マーケター)には依らないというのが、悲しくも、厳しい現実がある。そこが、ブランディンの難しさなのだ。その一人のやり手で、その企業をV字回復させただけでは、ブランドは確立しない。
「伝統とは、どれだけその危機を乗り越えてきたか、その戦歴の証である」(西部邁)という名言があるが、この伝統、いわば、ブランドとほぼイコールともなる。
シャネルは、ココシャネルという女性、iPhoneは、S・ジョブスという革命児、ソニーには、井深大と盛田昭夫という名コンビの伝説、そして、本田技研には、本田宗一郎の創業精神“ホンダ・スピリット(本田イズム)”の継承が、それぞれ、ブランドの頸椎、いわば、物語性として脈々と流れている“神話”、その象徴としてブランドとして、生き続けてもいる。この点、日産には、車のスカイラインという名車があれど、会社のブランドには、寄与していない。ここにこそ、俗なるマーケティングでは、及びもつかない、高貴なる領域が厳然として存在するのである。手塚治虫マンガは、ブランド足りえた、そして、手塚はマンガの神様として世に認識されてはいるが、手塚プロは倒産した。一方、スタジオジブリが、アニメーションのブランド足りえているのは、設立者の二人、高畑勲と宮崎駿という人間が根底にある。ちょうど、ディズニーカンパニーが、W・ディズニーの理念、彼のブランド力に負うこと絶大であるのと同義である。
こうした点でも、「量があって質がある」という名医三角和雄氏の言葉の、限界というものが浮かびあがってもこよう。これは、士農工商における、工なる、職人の世界での真意でもあろう、しかし、商なる、商人の世界では、この弁は、限界があると私は主張したいのである。いくら、“量があっても、いつかは滅びる”、昭和に台頭した量販店(すーぱー)(GMS)のダイエーや西友、そしてヨーカ堂を概観すれば得心がゆくであろう。字の如く、<商品を大量に仕入れて安く販売する小売店>、これは、豊かな1950~60年代のアメリカをモデルとしたビジネススタイルの店である。社会が成熟する(目が肥えた消費者の台頭)と、特に、衣料品・雑貨品などは、見向きもされなくなる。これら三社は、昭和でマックス、平成でバブル崩壊とともに、下降線を辿る。平成初期から揶揄されるように「何でもあるが、欲しいものがない」、その言葉にそれが集約されてもいる。そして、令和の今では、前者2社はもちろん、後者1社も消滅しつつある。量の追求の昭和の消費者価値観のままでいたつけが回ってもきた。こうした平成30年の量から質へ、最も嗅覚、いや直観力を働かせ、セブンイレブンというコンビニを流通業界の雄、王者へと君臨せしめた経営者、それが、コンビニの父鈴木敏文でもある。彼が、セブン&ホールディングを去ったあと、凡庸、盆暗CEO井坂修一により、今や、コンビニの雄セブンが、外資に買収されようとするありさまである。また、ファミマに、大谷翔平起用のCM、つまり、マーケティングで、そのブランドイメージ?ミスターコンビニの地位が、脅かされてもいる。
“変化への対応”が最も必要とされる、商の世界では、質を追い求め、ブランディングするということが、如何に困難であるか!
これ、人間80年の寿命のなかで、マーケティングして生きる人は、多数派である。リスキリングの学び直しは、まさしくそれである。一方、ブランディングして生きる人、真のその人は、そんな意識すらないのだが、教養を積む人、徳を積む人、これが、質の人である。仕事とは、一切関係のない人文科学系の書籍を読む人。また、私の好きな言葉、<規矩>、それを忘れない人が、質の人の同義でもある、教養ある人とも言い得るのではないかと思う。
遠い昔、セブン&ホールディングスに入社した年、新人の、写真付き自己紹介をする名簿に記載するコメント欄に以下のように書いた。少々キザに聞こえはするが。
「芸術家(アーティスト)であるより職人(アルティザン)でありたい。ビジネスマンであるより商人(あきんど)でありたい」
おのれ自身の人生は、帝国ホテル、ホテルオークラ、ホテルニューオータニに準えるのではなく、京都の老舗旅館、柊屋、俵屋、炭屋に準えるのが賢明である。これも、大手予備校の雇われ講師ではなく、場末の“名店的”個人塾が、少数の生徒を相手にする、アナログ塾、この方が性分に合っているのである。
そもそも、マーケティングとは、量の側面のビジネスツールである、一方、ブランディングとは、質の側面のそれ、ビジネススキルの範疇には入らぬ一種、暗黙知の世界やもしれない。また、陶工が、窯から出てこないとわからない名品とも言えなくもない、半分は自然・偶然の“神”の足が踏み入れる領域やもしれぬ。
マーケティングとは、面の戦術であり、いかに、市場のパイ、領域を獲得し、売り上げをあげるか、その手段である。時期や状況、時代時代で日々戦術を変えればならぬ手法でもある。それに対して、ブランディングとは、点、線の戦略であり、いかに、自社製品・商品の支持層を増やす、信頼度を増す、敢えて言えば、時代や状況を超越して、いかに利益をだすか、敢えていえば売り上げよりも利益を優先することを旨とする方法である。あのルイヴィトンの会社、LVMHを見れば一目瞭然である。ディズニーという会社も同様である。
この両面の、獲得に一番のジレンマを抱えている大企業は、平成で台頭した、ファーストファッション雄のユニクロと、携帯電話・スマホのソフトバンクや楽天でもあろう。前者は、百貨店で販売されているラルフに、後者は、ドコモやAUに、いまいち、ブランド力で劣ることは、周知の事実でもあろう。この三社、CMの露出度が際立ってもいることがその一つの証明であろうか?CMによる“自転車操業的マーケティング”である。“吠える犬は嚙みつかぬ”ではないが、CMやり放題の企業に限り、時代から落ちこぼれることを最も恐れる証左ともいえる。
一般論として、このマーケティングは、平時には強いが、窮時には弱い。ブランディングは、平時には、強いというより、安定感・信用度を増し、更に、窮時にこそ、その強味が発揮される。この証明として、昭和の松下幸之助の、「好況よし、不況さらによし」、その言葉が、ものの見事に、それを証明してもいよう。幸之助の自社ブランドへのゆるぎない自信、自負の表れである。卑近な例を挙げれば、巷の飲食業で、コロナ禍で消滅した店、今でも健在の店、それが、試金石ともなった事実である。
人間レベルいうところの、マーケティングは、知識であり、ブランディングとは、教養ともいいうるものだ。巧い喩えとは言えないが、昆布と鰹節、これが、知識であり、そこから抽出した“うまみ”・“だし”、これが教養ともいえるものだ。しかし、このうま味も生かすも殺すも、料理人の腕にかかっている。この名料理人とは、厨房だけからは生まれない。これは、知識力で、弁護士や公認会計士になっても、教養力がなければ、昼行燈の資格士に留まる“凡庸~士”であるのと同義である。知識は、計算づくで、いかようにも増やせるが、教養とは、計算づくで身につくものではない。そこにも、小泉信三の名言、「すぐに役に立つものは、すぐに役に立たなくなる」が輝きを増してもくる。この名言、その真意は、製品でいう質、人間の根幹ともいえる教養を指す。さらに、渋沢栄一の『論語と算盤』の題名にも、その皮肉なる暗示、警鐘が滲んでもいる。論語は教養、算盤は知識とも言えよう。ブランディングの真髄とは、“急がば回れ”のことわざの逆説の真理に行き着く。
今最も注目を浴びているマーケティングをする人、いわゆる、マーケターは、森岡毅氏でもあろう。マーケターは、落ち目企業、赤字企業を、脚光浴びる企業に、黒字企業には、出来ても、その後、ブランド化しうるか否かは、その人物(マーケター)には依らないというのが、悲しくも、厳しい現実がある。そこが、ブランディンの難しさなのだ。その一人のやり手で、その企業をV字回復させただけでは、ブランドは確立しない。
「伝統とは、どれだけその危機を乗り越えてきたか、その戦歴の証である」(西部邁)という名言があるが、この伝統、いわば、ブランドとほぼイコールともなる。
シャネルは、ココシャネルという女性、iPhoneは、S・ジョブスという革命児、ソニーには、井深大と盛田昭夫という名コンビの伝説、そして、本田技研には、本田宗一郎の創業精神“ホンダ・スピリット(本田イズム)”の継承が、それぞれ、ブランドの頸椎、いわば、物語性として脈々と流れている“神話”、その象徴としてブランドとして、生き続けてもいる。この点、日産には、車のスカイラインという名車があれど、会社のブランドには、寄与していない。ここにこそ、俗なるマーケティングでは、及びもつかない、高貴なる領域が厳然として存在するのである。手塚治虫マンガは、ブランド足りえた、そして、手塚はマンガの神様として世に認識されてはいるが、手塚プロは倒産した。一方、スタジオジブリが、アニメーションのブランド足りえているのは、設立者の二人、高畑勲と宮崎駿という人間が根底にある。ちょうど、ディズニーカンパニーが、W・ディズニーの理念、彼のブランド力に負うこと絶大であるのと同義である。
こうした点でも、「量があって質がある」という名医三角和雄氏の言葉の、限界というものが浮かびあがってもこよう。これは、士農工商における、工なる、職人の世界での真意でもあろう、しかし、商なる、商人の世界では、この弁は、限界があると私は主張したいのである。いくら、“量があっても、いつかは滅びる”、昭和に台頭した量販店(すーぱー)(GMS)のダイエーや西友、そしてヨーカ堂を概観すれば得心がゆくであろう。字の如く、<商品を大量に仕入れて安く販売する小売店>、これは、豊かな1950~60年代のアメリカをモデルとしたビジネススタイルの店である。社会が成熟する(目が肥えた消費者の台頭)と、特に、衣料品・雑貨品などは、見向きもされなくなる。これら三社は、昭和でマックス、平成でバブル崩壊とともに、下降線を辿る。平成初期から揶揄されるように「何でもあるが、欲しいものがない」、その言葉にそれが集約されてもいる。そして、令和の今では、前者2社はもちろん、後者1社も消滅しつつある。量の追求の昭和の消費者価値観のままでいたつけが回ってもきた。こうした平成30年の量から質へ、最も嗅覚、いや直観力を働かせ、セブンイレブンというコンビニを流通業界の雄、王者へと君臨せしめた経営者、それが、コンビニの父鈴木敏文でもある。彼が、セブン&ホールディングを去ったあと、凡庸、盆暗CEO井坂修一により、今や、コンビニの雄セブンが、外資に買収されようとするありさまである。また、ファミマに、大谷翔平起用のCM、つまり、マーケティングで、そのブランドイメージ?ミスターコンビニの地位が、脅かされてもいる。
“変化への対応”が最も必要とされる、商の世界では、質を追い求め、ブランディングするということが、如何に困難であるか!
これ、人間80年の寿命のなかで、マーケティングして生きる人は、多数派である。リスキリングの学び直しは、まさしくそれである。一方、ブランディングして生きる人、真のその人は、そんな意識すらないのだが、教養を積む人、徳を積む人、これが、質の人である。仕事とは、一切関係のない人文科学系の書籍を読む人。また、私の好きな言葉、<規矩>、それを忘れない人が、質の人の同義でもある、教養ある人とも言い得るのではないかと思う。
遠い昔、セブン&ホールディングスに入社した年、新人の、写真付き自己紹介をする名簿に記載するコメント欄に以下のように書いた。少々キザに聞こえはするが。
「芸術家(アーティスト)であるより職人(アルティザン)でありたい。ビジネスマンであるより商人(あきんど)でありたい」
おのれ自身の人生は、帝国ホテル、ホテルオークラ、ホテルニューオータニに準えるのではなく、京都の老舗旅館、柊屋、俵屋、炭屋に準えるのが賢明である。これも、大手予備校の雇われ講師ではなく、場末の“名店的”個人塾が、少数の生徒を相手にする、アナログ塾、この方が性分に合っているのである。
2025年4月 1日 09:31