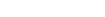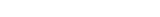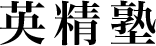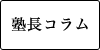カテゴリ
- おすすめの参考書
- 保護者の方へ (10)
- 2020年問題 (3)
- おすすめの教養書
月別 アーカイブ
- 2025年4月 (2)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (5)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (5)
- 2024年3月 (4)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (4)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (5)
- 2021年12月 (7)
- 2021年11月 (4)
- 2021年10月 (5)
- 2021年9月 (4)
- 2021年8月 (4)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (10)
- 2021年4月 (5)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (7)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (7)
- 2020年6月 (6)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (5)
- 2020年3月 (5)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (4)
- 2019年12月 (5)
- 2019年11月 (5)
- 2019年10月 (4)
- 2019年9月 (5)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (5)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (6)
- 2019年3月 (6)
- 2019年2月 (3)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (7)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (3)
- 2018年7月 (4)
最近のエントリー
HOME > コラム > ⑦質か量か?~演繹法から帰納法へ~
コラム
⑦質か量か?~演繹法から帰納法へ~
これは、教え子から聞いたことなので、一般論としては通用しないかもしれないが、なるほど一理あるな!と感じ入ったことを語るとしょう。
東工大に進んだ教え子H君の弁である。
「東工大の二次の数学の問題は、遠回り、即ち、計算力で少々時間をかけて解答までたどり着くことができる問題というのが特徴で、それに対して、東大の二次の数学問題は、その城ともいっていいその問題は、計算力、時間をかける、こうした手法では、落とせない。つまり、その城をどこから攻めればいのか、その入り口、切り口がわからない。つまり、ここだ!という一種の閃きというものがないと解けない問題なんです。」
次の一節は、弊塾の第一期生で、その後神奈川県で有名な某中学受験進学塾の教室長になった教え子と話した折に、彼が語ったものです。
「私教室長が、月曜日から日曜日まで、週7日間、本当は、週3回のレギュラー授業だけなのですが、そのほかに、特別にプライベートで勉強指導して、浅野学園までは、その親御さんに合格をある程度は保証してあげることはできる。しかし、その子に、栄光学園や聖光学院のレベルになると、保証はできない。つまり、標準的な小学生を、良き指導、努力という絶対量の勉強でも、そのレベルだと、きついとう現実があるんです。」
この教え子のS君の弁を聞くと、あるコーチが、オリンピック入賞までは、俺の力で何とかなるが、金銀銅のメダルという段になると、もうこれは、環境やトレーニングなどの及びもつかない、その人の資質や才能がものをいう次元にもなるということにも似ていようか。歌の上手い・下手が、また、足の速い・遅いが、先天的なものであるという真理と相通じるものが伺える現実でもある。
あの東大の二次の数学の問題にしろ、栄光や聖光の中学入試の問題にしろ、ある意味、そのギフティッドの高校生や小学生を篩に賭ける問題にも突き当たるという実相が見えもくる。
さて、前置きは、これくらいにして、質と量、そして、演繹法と帰納法、それらの関係性に関して、思春期の中高生に該当する、私なりの法則というものを語ってみたい。
東工大に進んだH君や中学受験進学塾の塾長S君の言葉から、数学(算数)は、やはりセンスがもの言うのかといった命題が浮上してもこよう。しかし、今もっとも注目を浴びている精神科医で、鉄緑会の創設者でもある和田秀樹氏などは、「数学は暗記だ!」といった説まで述べている。事実、その題名の書籍が、現にある。彼曰く、大学受験レベルの数学など、センスなど不要、数をこなし、その解法パターンを覚えれば解けるレベルだと語る。事実、それは、数学者藤原正彦氏の「高校の数学なんて、数学の超入門、大学生の理学部の数学が入門、そして、大学院のそれが初級程度だ!」からもうなずけはするが、秀才以下の凡人ぞろいの高校生には、理解できない準天才から秀才までの基準でもあろうか。
ここで、和田秀樹氏の、“数学は数多くやって、その解き方のパターンの暗記だ!”とする説、これこそ、努力の天才、王貞治的天才の王道というものである。帰納法から、真理、解答へのヒントが認識できてしまう種族なのだ。この数多くやる、その行為が、難行苦行に思われてしまう、その途上で挫折に陥り、失望感に苛まれるのが、準秀才以下の定め、宿命でもある。こうした非ギフティッドに対して発せられることば、それが、“天才とは努力する才”といったものだ。これは、愚鈍というひたむきさに、幸運の女神が微笑んでくれた成功例なのだ。
「天才とは、蝶を追いかけていつの間にか山頂にまで登ってしまっている少年である」(J・スタインベック)これは、また、王貞治より、長嶋茂雄に該当する言葉でもあろう。
よく、天才や超勉強ができる小学生などに対して発せられる言葉、「頭のいい子は、一を聞いて、十を理解する」というものがあるが、これなんぞは、そのギフティッドの資質や才能に依るものではないような気がしてならない。そんな現象は、科学上ありえない。それは、空海が師恵果から密教の秘儀を1年ほど習得した才に等しい。その言葉の真意とは、一を聞いた知識と、別のもう一つの知識とが、鼠算式、掛け算式に化学反応して、一種、知の止揚現象が起きたケースとしか考えられない。
この、「一を聞き、十を理解する」という脳内の現象は、一部の天才は除き、実は、その本人にあるのではなく、実は、その教師・指導者・講師が、“知の化学反応の触媒”の役割をしているとしか考えられないのである。この謂いを色々なケースに当てはめ、その人自身に存する分析がなんと多いことか!当然、モーツアルト、ピカソ、アインシュタインなどの、Mr天才は除外させていただくとするが。それは、どういう事かと言えば、その、高校生に教える内容、数学や英語にしろ、演繹法で学ぶように誘導しているのである。その演繹法のコアとなる、本質をまず教授しているということである。これは、料理を例にとれば、鰹と昆布からとった“うまみ・だし”を基にして、様々な食材から美味しい料理を作れという手法であり、帰納法とは、様々な食材を前にして、それに合う様々な調味料を使って美味しい料理を作る、そういうプロセスに近いことかもしれない。
まず、優秀なる教師とは、教え子に、その学ぶ項目、学ぶ対象の、コア、本質、言い換えれば、例えば、微積分なら、その微積分の世界の本質を表徴する、絶対不可欠な問題、それを、一点の曇りもなく解説説明してあげる、たとえ、それが超難問であってもである。その問題は、微積分というものの精髄ともいっていいものを内包している良問でもある。それを、習得すれば、大学受験レベルの微積分の問題ならほぼ解ける域にもなるということを生徒に覚醒、自覚させるのである。そのコアともいえるものを伝授した段階で、その本人は自身で、生徒たちは、旧7帝大の過去問を相手に、帰納法的に、他流試合をする。千葉道場の剣士の如く、師範格のめいめいはその後、場数を踏んで、その、千葉周作から学んだ秘伝のコアが、自身には、ほぼ絶対ともいえる武器として確立した時点で、自信が確信に豹変するのである。これが、実力とも呼べるものである。宮本武蔵の剣が最強だったのは、彼が、文から武へと、出発点が、演繹法だったとうことだ。それを、武蔵は、実践という帰納法で鍛錬していったというに過ぎぬ。『五輪書』が、それをものの見事に証明している。武芸書を超越して、経営・人生などに不変的に通じる真理とは、コアから、そして演繹法へと導く強烈なるベクトルのオーラを放つ。それは古典であることの絶対条件なのだ。古典には、こうした要素が必要不可欠でもある。
実は、この良き師に出会わなければ、この、演繹法から帰納法への学びの成功のプロセスは歩めないのである。ここに、リアルの学び、対面授業、アナログという流儀がj光を増す。御三家の秀才の高校生は、鉄緑会へ、県立高校の秀才は、大手の予備校へと足繁く通う原因が、ここにあるのである。一般の中学や高校の教師の授業の光景に観られるは、この手法ではなく、帰納法から自力で演繹法のコアに到達せよと、自助努力強要の、生徒自身による暗中模索の授業のぶん投げ・放り投げをしてもいるものだ。
実は、<下手な鉄砲数打ちゃ当たる的帰納法>が、巷の学びの場では余りに跋扈しすぎているのである。これは、ほとんどの個別指導塾の経営態度であり、教えない塾、こと、武田塾の手法でもある。この手法には、根気、愚鈍といった気質を有する者が、成功するといったものだ。しかも時間と運という要素も絡んでくる。一般の高校生なんぞは、時間もない、我慢強さもない、ないない尽くしのキャラの人間には、オアシスのない巨大な砂漠を横断するような蛮行でもある。
この私が主張する、<良き師により行われる演繹法から帰納法へ手法>、これを、ものの見事に大成させた人物こそ、桐朋学園創設者で、名指揮者小澤征爾や秋山和慶を育てあげた斎藤秀雄でもあろう。かの有名な斎藤メソッドである。バーンスタインも絶賛した『指揮法教程』を著した。その二人の教え子は、その音楽教育の“演繹法の天才”に徹底的に学び、そこから、クラッシックの譜面からオーケストラにオリジナルな美を表徴させるスキルを磨き上げてもいった。ここにこそ、英数国理社の教師が、自覚しなければならない、教えの本質というものがある。
私から言わせていただくと、この斉藤秀雄の『指揮法教程』こそ、いや、講義の斉藤メソッドこそ、ある意味で、デカルトの『方法序説』に相当するものであるとの確信がある。その根拠は、“演繹法”という流儀が、音楽であれ、哲学(自然科学)であれ、その後の人間や学問の飛躍、躍進、進歩といったものにどれほど寄与するか、それが証拠でもある。
因みに、幕末の吉田松陰、明治初期のクラーク博士、彼らは、ほんの数年といった短期間でしか、教え子に接しなかったが、その後、その弟子たちは、どれほど、日本の近代化に貢献したか、恐らくは、私の謂う、面授面受(アナログ)による、その受け継いだコアを信奉し、演繹法から帰納法へ、そしてそれが開花した。今に知られている“教育”の本質でもある。次回、演繹法を生徒に用いさせる際の、教師の側の直観力と洞察力の必要性を語ってみたい。
東工大に進んだ教え子H君の弁である。
「東工大の二次の数学の問題は、遠回り、即ち、計算力で少々時間をかけて解答までたどり着くことができる問題というのが特徴で、それに対して、東大の二次の数学問題は、その城ともいっていいその問題は、計算力、時間をかける、こうした手法では、落とせない。つまり、その城をどこから攻めればいのか、その入り口、切り口がわからない。つまり、ここだ!という一種の閃きというものがないと解けない問題なんです。」
次の一節は、弊塾の第一期生で、その後神奈川県で有名な某中学受験進学塾の教室長になった教え子と話した折に、彼が語ったものです。
「私教室長が、月曜日から日曜日まで、週7日間、本当は、週3回のレギュラー授業だけなのですが、そのほかに、特別にプライベートで勉強指導して、浅野学園までは、その親御さんに合格をある程度は保証してあげることはできる。しかし、その子に、栄光学園や聖光学院のレベルになると、保証はできない。つまり、標準的な小学生を、良き指導、努力という絶対量の勉強でも、そのレベルだと、きついとう現実があるんです。」
この教え子のS君の弁を聞くと、あるコーチが、オリンピック入賞までは、俺の力で何とかなるが、金銀銅のメダルという段になると、もうこれは、環境やトレーニングなどの及びもつかない、その人の資質や才能がものをいう次元にもなるということにも似ていようか。歌の上手い・下手が、また、足の速い・遅いが、先天的なものであるという真理と相通じるものが伺える現実でもある。
あの東大の二次の数学の問題にしろ、栄光や聖光の中学入試の問題にしろ、ある意味、そのギフティッドの高校生や小学生を篩に賭ける問題にも突き当たるという実相が見えもくる。
さて、前置きは、これくらいにして、質と量、そして、演繹法と帰納法、それらの関係性に関して、思春期の中高生に該当する、私なりの法則というものを語ってみたい。
東工大に進んだH君や中学受験進学塾の塾長S君の言葉から、数学(算数)は、やはりセンスがもの言うのかといった命題が浮上してもこよう。しかし、今もっとも注目を浴びている精神科医で、鉄緑会の創設者でもある和田秀樹氏などは、「数学は暗記だ!」といった説まで述べている。事実、その題名の書籍が、現にある。彼曰く、大学受験レベルの数学など、センスなど不要、数をこなし、その解法パターンを覚えれば解けるレベルだと語る。事実、それは、数学者藤原正彦氏の「高校の数学なんて、数学の超入門、大学生の理学部の数学が入門、そして、大学院のそれが初級程度だ!」からもうなずけはするが、秀才以下の凡人ぞろいの高校生には、理解できない準天才から秀才までの基準でもあろうか。
ここで、和田秀樹氏の、“数学は数多くやって、その解き方のパターンの暗記だ!”とする説、これこそ、努力の天才、王貞治的天才の王道というものである。帰納法から、真理、解答へのヒントが認識できてしまう種族なのだ。この数多くやる、その行為が、難行苦行に思われてしまう、その途上で挫折に陥り、失望感に苛まれるのが、準秀才以下の定め、宿命でもある。こうした非ギフティッドに対して発せられることば、それが、“天才とは努力する才”といったものだ。これは、愚鈍というひたむきさに、幸運の女神が微笑んでくれた成功例なのだ。
「天才とは、蝶を追いかけていつの間にか山頂にまで登ってしまっている少年である」(J・スタインベック)これは、また、王貞治より、長嶋茂雄に該当する言葉でもあろう。
よく、天才や超勉強ができる小学生などに対して発せられる言葉、「頭のいい子は、一を聞いて、十を理解する」というものがあるが、これなんぞは、そのギフティッドの資質や才能に依るものではないような気がしてならない。そんな現象は、科学上ありえない。それは、空海が師恵果から密教の秘儀を1年ほど習得した才に等しい。その言葉の真意とは、一を聞いた知識と、別のもう一つの知識とが、鼠算式、掛け算式に化学反応して、一種、知の止揚現象が起きたケースとしか考えられない。
この、「一を聞き、十を理解する」という脳内の現象は、一部の天才は除き、実は、その本人にあるのではなく、実は、その教師・指導者・講師が、“知の化学反応の触媒”の役割をしているとしか考えられないのである。この謂いを色々なケースに当てはめ、その人自身に存する分析がなんと多いことか!当然、モーツアルト、ピカソ、アインシュタインなどの、Mr天才は除外させていただくとするが。それは、どういう事かと言えば、その、高校生に教える内容、数学や英語にしろ、演繹法で学ぶように誘導しているのである。その演繹法のコアとなる、本質をまず教授しているということである。これは、料理を例にとれば、鰹と昆布からとった“うまみ・だし”を基にして、様々な食材から美味しい料理を作れという手法であり、帰納法とは、様々な食材を前にして、それに合う様々な調味料を使って美味しい料理を作る、そういうプロセスに近いことかもしれない。
まず、優秀なる教師とは、教え子に、その学ぶ項目、学ぶ対象の、コア、本質、言い換えれば、例えば、微積分なら、その微積分の世界の本質を表徴する、絶対不可欠な問題、それを、一点の曇りもなく解説説明してあげる、たとえ、それが超難問であってもである。その問題は、微積分というものの精髄ともいっていいものを内包している良問でもある。それを、習得すれば、大学受験レベルの微積分の問題ならほぼ解ける域にもなるということを生徒に覚醒、自覚させるのである。そのコアともいえるものを伝授した段階で、その本人は自身で、生徒たちは、旧7帝大の過去問を相手に、帰納法的に、他流試合をする。千葉道場の剣士の如く、師範格のめいめいはその後、場数を踏んで、その、千葉周作から学んだ秘伝のコアが、自身には、ほぼ絶対ともいえる武器として確立した時点で、自信が確信に豹変するのである。これが、実力とも呼べるものである。宮本武蔵の剣が最強だったのは、彼が、文から武へと、出発点が、演繹法だったとうことだ。それを、武蔵は、実践という帰納法で鍛錬していったというに過ぎぬ。『五輪書』が、それをものの見事に証明している。武芸書を超越して、経営・人生などに不変的に通じる真理とは、コアから、そして演繹法へと導く強烈なるベクトルのオーラを放つ。それは古典であることの絶対条件なのだ。古典には、こうした要素が必要不可欠でもある。
実は、この良き師に出会わなければ、この、演繹法から帰納法への学びの成功のプロセスは歩めないのである。ここに、リアルの学び、対面授業、アナログという流儀がj光を増す。御三家の秀才の高校生は、鉄緑会へ、県立高校の秀才は、大手の予備校へと足繁く通う原因が、ここにあるのである。一般の中学や高校の教師の授業の光景に観られるは、この手法ではなく、帰納法から自力で演繹法のコアに到達せよと、自助努力強要の、生徒自身による暗中模索の授業のぶん投げ・放り投げをしてもいるものだ。
実は、<下手な鉄砲数打ちゃ当たる的帰納法>が、巷の学びの場では余りに跋扈しすぎているのである。これは、ほとんどの個別指導塾の経営態度であり、教えない塾、こと、武田塾の手法でもある。この手法には、根気、愚鈍といった気質を有する者が、成功するといったものだ。しかも時間と運という要素も絡んでくる。一般の高校生なんぞは、時間もない、我慢強さもない、ないない尽くしのキャラの人間には、オアシスのない巨大な砂漠を横断するような蛮行でもある。
この私が主張する、<良き師により行われる演繹法から帰納法へ手法>、これを、ものの見事に大成させた人物こそ、桐朋学園創設者で、名指揮者小澤征爾や秋山和慶を育てあげた斎藤秀雄でもあろう。かの有名な斎藤メソッドである。バーンスタインも絶賛した『指揮法教程』を著した。その二人の教え子は、その音楽教育の“演繹法の天才”に徹底的に学び、そこから、クラッシックの譜面からオーケストラにオリジナルな美を表徴させるスキルを磨き上げてもいった。ここにこそ、英数国理社の教師が、自覚しなければならない、教えの本質というものがある。
私から言わせていただくと、この斉藤秀雄の『指揮法教程』こそ、いや、講義の斉藤メソッドこそ、ある意味で、デカルトの『方法序説』に相当するものであるとの確信がある。その根拠は、“演繹法”という流儀が、音楽であれ、哲学(自然科学)であれ、その後の人間や学問の飛躍、躍進、進歩といったものにどれほど寄与するか、それが証拠でもある。
因みに、幕末の吉田松陰、明治初期のクラーク博士、彼らは、ほんの数年といった短期間でしか、教え子に接しなかったが、その後、その弟子たちは、どれほど、日本の近代化に貢献したか、恐らくは、私の謂う、面授面受(アナログ)による、その受け継いだコアを信奉し、演繹法から帰納法へ、そしてそれが開花した。今に知られている“教育”の本質でもある。次回、演繹法を生徒に用いさせる際の、教師の側の直観力と洞察力の必要性を語ってみたい。
2025年4月 7日 16:26