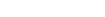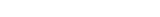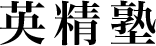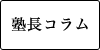カテゴリ
- おすすめの参考書
- 保護者の方へ (10)
- 2020年問題 (3)
- おすすめの教養書
月別 アーカイブ
- 2025年4月 (1)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (5)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (5)
- 2024年3月 (4)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (4)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (5)
- 2021年12月 (7)
- 2021年11月 (4)
- 2021年10月 (5)
- 2021年9月 (4)
- 2021年8月 (4)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (10)
- 2021年4月 (5)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (7)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (7)
- 2020年6月 (6)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (5)
- 2020年3月 (5)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (4)
- 2019年12月 (5)
- 2019年11月 (5)
- 2019年10月 (4)
- 2019年9月 (5)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (5)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (6)
- 2019年3月 (6)
- 2019年2月 (3)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (7)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (3)
- 2018年7月 (4)
最近のエントリー
コラム
早稲田の国際教養学部について
今や「国際共通語としての英語」なのだから、ネイティブ・スピーカーを真似する必要ない、と言われれば「あ、そうなんだ」と頭では理解するけれど、「ネイティブの英語はやっぱりきえいだな」と思う。「帰国子女はネイティブみたいな英語だから羨ましいな」と思う。某有名私大の国際教養学部では、話す英語で暗黙の序列があるそうです。教員であれ、学生であれ、英語ネイティブ・スピーカーが最上位、次が、「ネイティブに近い英語」を話す帰国生、最下層が日本で生まれ育ち日本で英語を学んだ「純ジャパ」(純粋ジャパニーズ)。英語ができる人とできない人との間に格差があるのみならず、英語ができる人の間にも格差があるということになります。そしてその判断基準は、「話す英語」がどのくらい流暢か、ということのようです。『話すための英語力』(鳥飼玖美子)講談社現代新書~P8より~
以上の某有名私大の国際教養学部とは早稲田のことです。内容の主旨ですが、日本という土地にありながら、早稲田の国際教養学部のキャンパスは、“治外法権”の場所です。しかも、お客さん(※ネイティブや帰国子女)に合わせて、英語で授業、ネイティブや帰国子女にとっては、超楽単(※超楽に単位が取れる)の授業でもあります。しかし、純ジャパにとっては、講義内容は2流の事(※日本語に翻訳されている本の内容:わざわざ英語で授業を受けるほどのものではないということ)でも、英語で聞き取ることに全精力を傾けざるを得ず、“ああ、そんな内容、翻訳の日本語の専門書・新書などに書かれてあるものじゃん!”とあとで気づくのです。
それも、主にアジアからの留学生で、日本の大学にやって来る学生は、皮肉まじりに言わせてもらえば、2流学生、とどのつまり、欧米の大学へは、学力や経済面で行けなかった人種です。そうした‘お茶の出がらし’的学生を相手に、日本の土地で、英語で授業をするなど、そのネイティブ教師ですら、恐らく2流教授が大方ではないかと思われます。
半数以上は、ネイティブ・帰国子女の学生がひしめく教室、それも、2流ネイティブ教授、かたことの英語しか話せない純ジャパ教授が、英語授業で教壇に立つ、こうした空間に、<純ジャパ学生をぶち込めば、そこそこぺらぺら英語がしべれるようになるんじゃないか>といったお目でたい早稲田の教育方針なんぞは、まるで、高校の英語の授業を英語のみで行えといった単細胞的文科省の理念と全くおなじものを感じずにはいられないのです。
早稲田国際教養の純ジャパは、ちょうど、上智大学の英語学部や国際教養学部に背伸びして入学して、後悔する純ジャパと全く心情的辛酸をなめていると思われます。
はっきり申しますが、純ジャパが、早稲田であれ、上智であれ、国際教養なんぞという学部に入学すれば、知識・教養はもちろんのこと、英語力も中途半端で卒業する羽目となるのは目に見えています。恐らく、こうした学部に入った学生は、絶対的読書量による、即ち、日本語による、本での知識量や感性の鋭さ、教養といったものの厚み、そうしたものを身に付けるべき貴重な4年間を、中途半端な“国内留学”で終わらせてしまうことと相成るのです。
秋田県立国際教養大学は、学生全員が、人里離れた場所で、アルバイトも無縁、全寮生活を強いられます。それに対して、早稲田や上智の都会のど真ん中にあるキャンパスでは、教室から一歩外に出てしまえば、新宿・高田馬場、四谷など周囲は日本語空間で満ち満ちています。さらに、アルバイトでもしている学生ともなれば、職場で日本語、自宅に帰れば親子で日本語、ちょうど、幼稚園児が英会話スクールなんぞに週数回通っても、サウナ後のビールの如きに、母語のリバウンドが待ち構えてもいるのです。英語力の伸び具合など、微々たるものです。正直いいますが、真に賢明な学生は、日本では、このような、一見英語力が伸びそうに思える名ばかり“魅力的な”学部なんどには、通ってはいないということです。ですから、厭味ったらしく申し上げれば、知的に賢い高校生で、12歳から英語を始めた人は、こうした学部になんぞは受験しない。こうしたまやかし学部に入学し、なーんちゃって国内留学し、1年の海外留学を義務付けているにしてもです、知識・教養・英語力が中途半端の学生が卒業し、また、アジアからの2流留学生が卒業してゆく学部であるからして、SFCに比べて、様々な分野で活躍している人物が雲泥の差となっているのです。
以下の引用文は『早稲田と慶應の研究』(オバタカズユキ)小学館新書によるものです。純ジャパにとっては、いかに恵まれない学部であるか、その証明ともなっている箇所です。
大学が学部につけたキャッチは「地球社会の縮図」である。大胆なフレーズだが、SILS(School of International Liberal Studiesの略称:国際教養学部)において日本以外の国籍をもつ学生の比率は32,7%、地域は45ヵ国、教員に関しても、日本以外の国籍を持つ者は36,5%を占める。(P43)
まるで、幕末の横浜・神戸の外交人居留区に住み着いた、迷い込んだ日本人の如き運命です。語学上不自由な学生生活を余儀なくされましょう。こうした環境が果たして、純ジャパの英語スキルアップに結び付くのか甚だ疑問です。
SILSの学生たちを片端から取材した限りでは、上智、ICU、東京外語大を併願したケースが多かった。その中に、ちょこちょこ東大おちが混じっている。慶應の併願者はあまりいない。教養教育と実学の違いの他、慶應SFCはそこまで英語力を徹底して鍛えるわけではない、という理由が考えられる。(P44)
早稲田と慶應は今や、全く学生の気質が半世紀前に比べさらに隔たった感が否めない。先日の“朝まで生テレビ”(2019・7月)≪激論!若手起業家大集合!ド~する?ニッポン≫というテーマでのパネリスト(主席者)のメンバーは、ほとんどが、慶應出身でありました。そのことが番組内でも、ちょっと言及されていたことが、以上の内容を如実に物語ってもいよう。早稲田出身者は、齢50を超えた夏野剛氏のみであった。その彼も、現在は慶應の教授の肩書で、母校の教授にはなってはいないという皮肉さが伝わってもきます。
彼女ら彼ら(純ジャパ)は非常に大変だ。
留学生や帰国子女にとっても、プレゼンテーションやディスカッションの準備、レポート課題などに追われる日々。とにかく忙しいということで「いそがしSILS」というあだ名もついている学部である。(P46)
ただ、こうした学生は、英語で読み、英語で書く日々に追われ、知的思考訓練の余裕すらなく、図書館でも読者三昧などの生活をおくる暇も余裕もない。いたってつまらない無機質な英語専門学校的学生生活をあっという間に過ごしてしまうことを暗示してもいます。研究者はもちろん、一般の大学生にも、<知的あそび・自主性・余裕>といったものがないと、頭から独創性など生まれてはこないと言われています。この点、山中伸弥教授はもちろん、ノーベル賞受賞者たちは、この点の重要性に、常日頃言及してもいます。
「ガムシャラに頑張っていると、講義内容はだいたいわかるようになりました。でも、ネイティブの講義が放つジョークが辛い。教室のみんなが一斉に笑い、自分だけが置いていかれる。パーティーでもそういうことがしばしばあります。だからといって、みんなから疎外されたりはしませんが、自分自身が最下層にいるんだなって思っちゃうんです」(純ジャパ、短期留学経験などもない2年生男子)(P47)
私も大学院時代、フランス人のプルースト研究の大家でもある専門講師による、フランス語でのゼミに出席してはいましたが、内容は半分も聞き取れてはいなかったと思う{※私の知識量のなさや仏語の聴力のなさも原因だったと思います}。しかし、後で、その講師の内容を、プリント(レジュメ)などで見返すと、すでに、プルースト研究の碩学、日本人教授の専門書で書かれている内容で、取りたてて貴重な内容ではなく、ただフランス語の耳を鍛えていた時間であったことが思いかえされてきます。
「英語ができれば人権がある(なんでも自由にやれる)という学部です。純ジャパは、英語のリーディング、リスニング、ライティングとすべてとる必要があるけど、帰国子女はリーディングとライティングはオープン科目でとる科目で、必須じゃないんです」(純ジャパの1年生男子)(P48)
以上から、帰国子女や留学生は、英語力は伸びる場ではない証拠となっていましょう。東大や国学院の国文科大学院学生が、コロンビア大学の日本文学科に留学するようなものです。彼ら(帰国子女や留学生)にきちんとした日本語のリーディングやライティングの科目を必須にしているのでなければ、片手落ちというカリキュラムということになりやしないでしょうか?彼らは、キャンパス外で、日常的に日本語をシャワーのように浴びて、“使える日本語”は身に付いてはいるようです。
以上の某有名私大の国際教養学部とは早稲田のことです。内容の主旨ですが、日本という土地にありながら、早稲田の国際教養学部のキャンパスは、“治外法権”の場所です。しかも、お客さん(※ネイティブや帰国子女)に合わせて、英語で授業、ネイティブや帰国子女にとっては、超楽単(※超楽に単位が取れる)の授業でもあります。しかし、純ジャパにとっては、講義内容は2流の事(※日本語に翻訳されている本の内容:わざわざ英語で授業を受けるほどのものではないということ)でも、英語で聞き取ることに全精力を傾けざるを得ず、“ああ、そんな内容、翻訳の日本語の専門書・新書などに書かれてあるものじゃん!”とあとで気づくのです。
それも、主にアジアからの留学生で、日本の大学にやって来る学生は、皮肉まじりに言わせてもらえば、2流学生、とどのつまり、欧米の大学へは、学力や経済面で行けなかった人種です。そうした‘お茶の出がらし’的学生を相手に、日本の土地で、英語で授業をするなど、そのネイティブ教師ですら、恐らく2流教授が大方ではないかと思われます。
半数以上は、ネイティブ・帰国子女の学生がひしめく教室、それも、2流ネイティブ教授、かたことの英語しか話せない純ジャパ教授が、英語授業で教壇に立つ、こうした空間に、<純ジャパ学生をぶち込めば、そこそこぺらぺら英語がしべれるようになるんじゃないか>といったお目でたい早稲田の教育方針なんぞは、まるで、高校の英語の授業を英語のみで行えといった単細胞的文科省の理念と全くおなじものを感じずにはいられないのです。
早稲田国際教養の純ジャパは、ちょうど、上智大学の英語学部や国際教養学部に背伸びして入学して、後悔する純ジャパと全く心情的辛酸をなめていると思われます。
はっきり申しますが、純ジャパが、早稲田であれ、上智であれ、国際教養なんぞという学部に入学すれば、知識・教養はもちろんのこと、英語力も中途半端で卒業する羽目となるのは目に見えています。恐らく、こうした学部に入った学生は、絶対的読書量による、即ち、日本語による、本での知識量や感性の鋭さ、教養といったものの厚み、そうしたものを身に付けるべき貴重な4年間を、中途半端な“国内留学”で終わらせてしまうことと相成るのです。
秋田県立国際教養大学は、学生全員が、人里離れた場所で、アルバイトも無縁、全寮生活を強いられます。それに対して、早稲田や上智の都会のど真ん中にあるキャンパスでは、教室から一歩外に出てしまえば、新宿・高田馬場、四谷など周囲は日本語空間で満ち満ちています。さらに、アルバイトでもしている学生ともなれば、職場で日本語、自宅に帰れば親子で日本語、ちょうど、幼稚園児が英会話スクールなんぞに週数回通っても、サウナ後のビールの如きに、母語のリバウンドが待ち構えてもいるのです。英語力の伸び具合など、微々たるものです。正直いいますが、真に賢明な学生は、日本では、このような、一見英語力が伸びそうに思える名ばかり“魅力的な”学部なんどには、通ってはいないということです。ですから、厭味ったらしく申し上げれば、知的に賢い高校生で、12歳から英語を始めた人は、こうした学部になんぞは受験しない。こうしたまやかし学部に入学し、なーんちゃって国内留学し、1年の海外留学を義務付けているにしてもです、知識・教養・英語力が中途半端の学生が卒業し、また、アジアからの2流留学生が卒業してゆく学部であるからして、SFCに比べて、様々な分野で活躍している人物が雲泥の差となっているのです。
以下の引用文は『早稲田と慶應の研究』(オバタカズユキ)小学館新書によるものです。純ジャパにとっては、いかに恵まれない学部であるか、その証明ともなっている箇所です。
大学が学部につけたキャッチは「地球社会の縮図」である。大胆なフレーズだが、SILS(School of International Liberal Studiesの略称:国際教養学部)において日本以外の国籍をもつ学生の比率は32,7%、地域は45ヵ国、教員に関しても、日本以外の国籍を持つ者は36,5%を占める。(P43)
まるで、幕末の横浜・神戸の外交人居留区に住み着いた、迷い込んだ日本人の如き運命です。語学上不自由な学生生活を余儀なくされましょう。こうした環境が果たして、純ジャパの英語スキルアップに結び付くのか甚だ疑問です。
SILSの学生たちを片端から取材した限りでは、上智、ICU、東京外語大を併願したケースが多かった。その中に、ちょこちょこ東大おちが混じっている。慶應の併願者はあまりいない。教養教育と実学の違いの他、慶應SFCはそこまで英語力を徹底して鍛えるわけではない、という理由が考えられる。(P44)
早稲田と慶應は今や、全く学生の気質が半世紀前に比べさらに隔たった感が否めない。先日の“朝まで生テレビ”(2019・7月)≪激論!若手起業家大集合!ド~する?ニッポン≫というテーマでのパネリスト(主席者)のメンバーは、ほとんどが、慶應出身でありました。そのことが番組内でも、ちょっと言及されていたことが、以上の内容を如実に物語ってもいよう。早稲田出身者は、齢50を超えた夏野剛氏のみであった。その彼も、現在は慶應の教授の肩書で、母校の教授にはなってはいないという皮肉さが伝わってもきます。
彼女ら彼ら(純ジャパ)は非常に大変だ。
留学生や帰国子女にとっても、プレゼンテーションやディスカッションの準備、レポート課題などに追われる日々。とにかく忙しいということで「いそがしSILS」というあだ名もついている学部である。(P46)
ただ、こうした学生は、英語で読み、英語で書く日々に追われ、知的思考訓練の余裕すらなく、図書館でも読者三昧などの生活をおくる暇も余裕もない。いたってつまらない無機質な英語専門学校的学生生活をあっという間に過ごしてしまうことを暗示してもいます。研究者はもちろん、一般の大学生にも、<知的あそび・自主性・余裕>といったものがないと、頭から独創性など生まれてはこないと言われています。この点、山中伸弥教授はもちろん、ノーベル賞受賞者たちは、この点の重要性に、常日頃言及してもいます。
「ガムシャラに頑張っていると、講義内容はだいたいわかるようになりました。でも、ネイティブの講義が放つジョークが辛い。教室のみんなが一斉に笑い、自分だけが置いていかれる。パーティーでもそういうことがしばしばあります。だからといって、みんなから疎外されたりはしませんが、自分自身が最下層にいるんだなって思っちゃうんです」(純ジャパ、短期留学経験などもない2年生男子)(P47)
私も大学院時代、フランス人のプルースト研究の大家でもある専門講師による、フランス語でのゼミに出席してはいましたが、内容は半分も聞き取れてはいなかったと思う{※私の知識量のなさや仏語の聴力のなさも原因だったと思います}。しかし、後で、その講師の内容を、プリント(レジュメ)などで見返すと、すでに、プルースト研究の碩学、日本人教授の専門書で書かれている内容で、取りたてて貴重な内容ではなく、ただフランス語の耳を鍛えていた時間であったことが思いかえされてきます。
「英語ができれば人権がある(なんでも自由にやれる)という学部です。純ジャパは、英語のリーディング、リスニング、ライティングとすべてとる必要があるけど、帰国子女はリーディングとライティングはオープン科目でとる科目で、必須じゃないんです」(純ジャパの1年生男子)(P48)
以上から、帰国子女や留学生は、英語力は伸びる場ではない証拠となっていましょう。東大や国学院の国文科大学院学生が、コロンビア大学の日本文学科に留学するようなものです。彼ら(帰国子女や留学生)にきちんとした日本語のリーディングやライティングの科目を必須にしているのでなければ、片手落ちというカリキュラムということになりやしないでしょうか?彼らは、キャンパス外で、日常的に日本語をシャワーのように浴びて、“使える日本語”は身に付いてはいるようです。
2019年8月 6日 17:50