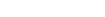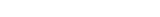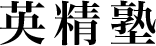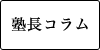カテゴリ
- おすすめの参考書
- 保護者の方へ (10)
- 2020年問題 (3)
- おすすめの教養書
月別 アーカイブ
- 2025年4月 (1)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (5)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (5)
- 2024年3月 (4)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (4)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (5)
- 2021年12月 (7)
- 2021年11月 (4)
- 2021年10月 (5)
- 2021年9月 (4)
- 2021年8月 (4)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (10)
- 2021年4月 (5)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (7)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (7)
- 2020年6月 (6)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (5)
- 2020年3月 (5)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (4)
- 2019年12月 (5)
- 2019年11月 (5)
- 2019年10月 (4)
- 2019年9月 (5)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (5)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (6)
- 2019年3月 (6)
- 2019年2月 (3)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (7)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (3)
- 2018年7月 (4)
最近のエントリー
コラム
数学落伍者の生き方の流儀
『余はいかにしてキリスト教徒となりしか』(内村鑑三)
『我等なぜキリスト教徒となりし乎』(安岡章太郎・井上洋治)
『余は如何にしてナショナリストとなりし乎』(福田和也)
以上の名著にちなみ、僭越ながら、私は、日ごろ書き損じている駄文、青春勉学記なるものを密かに書き溜めてもいるのだが、その副題こそ、次のようなものと決めている。
『余は如何にして数学落伍者となりし乎』(露木康仁)
数学落伍者は、落伍者なりに、それなりの公には言いづらい、心に秘めた個人的な大義名分というものがあるものである。
作家曽野綾子は「二次方程式がなくても生きてこられた」「二次方程式など社会へ出ても何の役にも立たないので、このようなものは追放すべきた」と発言し、その夫でもある三浦朱門は教育課程審議会会長を務められたこともあり、この発言が引きがねとなったかどうかは不明だが、その翌年、中学過程の“二次方程式の解の公式”は必須ではなくなった経緯がある。
また、近年、橋下徹元大阪府知事は「三角関数は生きてゆくために絶対に必要不可欠な知識じゃない」と発言したことで世間(ネット社会)をにぎわしたことが記憶に新しい。
英語学者で通訳者でもある鳥飼玖美子立教大学名誉教授は「自慢じゃないですが、私は算数から数学までまるでダメなんです。でも、けっして学校の教え方が悪かったからとは言いません。自分が悪かったと思いますね。」{『英語コンプレック粉砕宣言』(中公新書ラクレ)より}とも発言している。
三浦夫妻という、作家から文化人にまで上り詰めたご両者の、知的・文系的“保守派”というものでしょうか、ある意味、保守派として自民党の文教政策に影響力のある、ご二方は、著作物や発言など、日ごろ賛同するところ大ではありますが、やはり、どうも保守の文化人どまりで、保守の教養人とまで言いきれない側面がある。そこが、藤原正彦氏や渡部昇一氏との決定的な違いでもある。文化人とは、ある意味、政治色に染まった“教養人”とも言っていい。極論すれば、政治という魔物によって、知の判断部位が“下半身麻痺”となった種族とでも言ったら言い過ぎであろうか。
橋下徹氏に関しても、日ごろ、概ね、発言は過激なものながら、ある意味、自民党より、まっとうな保守の側面は有するが、やはり、大阪市の教育行政で、大阪市の学力調査最下位からの脱却を模索する手法として、教師の評価や教師同士の競い合いといった、新自由主義的手法を取り入れるなど、教育の側面では、経済的効率第一主義を貫こうとする弱点が垣間見えてくる。そうした手法が、教育現場では逆効果であることが分かっていらっしゃらないようだ。紅野謙介氏は、「「ゆとり」がほんとうに必要なのは教員である」とも語っておられる。この真実に橋下徹氏や教員更新制度を取り入れた安倍晋三などは、教育というももの根幹が全くわかってはいないようだ。橋下氏はお子さんが7人もいらっしゃる、しかも、その子育ては、全て妻まかせで「父親としては失格のパパだ」と公言までされている。安倍首相はお子さんがいらっしゃらない。こうした男族が、教育というもののかじ取りを誤らせるのである。
さすがに、英語教育改革の保守派でもある鳥飼氏は、謙虚である。自己の数学の弱点を他者、即ち、社会・学校・教師のせいにはせず、自己の責任と規定している点である。しかも、数学など必要ないとすら言ってはいない。政治的発言は一切しない英語学者でもある鳥飼氏の発言スタンスこそ、真の保守というものの証でもある。保守であるかどうか、それは憲法問題や日韓関係における発言ににじみ出るものでは決してない。
「勇ましいものはいつでも滑稽だ」(小林秀雄)
作家にしろ、政治家にしろ、英語学者にしろ、非数学のジャンルでは、人後に落ちぬほどその道を極めた方々でもある。非理系の領域に関しては、その分野の第一人者にまで上り詰めた方々である。
人間の機微を絶妙に描く文章力は、数学とは一切関係ないかもしれない。山本周五郎しかり、藤沢周平しかり、司馬遼太郎しかりである。また、人間のどろどろとした欲望うごめく政界でのし上がった田中角栄などは、人たらしの天才でもあった。彼は、高校数学などは無縁ではあったにしろ、数字の天才ではあった。その愛弟子、竹下登も同様である。また、高名なる英文学者にして博学なる知識人でもあった渡部昇一などは、数学にかかわりない種族のプライドともいえる<文系の流儀>を自著でとことん説いておられる。
もし、令和のデジタルの浮世において、数学という嗜みを手にしたもの、それは、理系のものは当然、国立大学へ進学する際、数学ⅡBまでを齧った人間を、まあ一流としよう。そうでない人間を、二流と規定しよう。ここでである。北斗の拳の原作者武論尊氏の著書『下流の生き方』の中の名言を引用するとしよう。
「上流に行きたいと思うから負けるんだよ。下流なら下流の意地で下流に生きてみろ」
この上流を学歴的基準で申し上げれば数学をある程度分かる、学んできた“一流”に、下流はこの文脈で数学とは疎遠であった“二流”に準えることができる。数学を捨てた部族は、こうした武論尊氏のような覚悟がなさすぎるのである。
数学がダメならダメの覚悟を持ち、徹底的に極論ながら、渡部昇一氏のような、非理系の王道を歩み、ぴか一の教養人・知識人・英文学者などになってやろうとする気概というものが、一般人にはないのである。
「一流は無理でも、“超二流”にはなれる」(野村克也)
これで成功した、野村の教え子がまさしく、宮本慎也であり、稲葉篤紀でもある。かれらは、ヤクルトに入団した時点で、2000本安打以上を打ち、名球会に入る逸材などと誰が予想したであろうか?古田敦也を加えると、野村の愛弟子が3人も名球会に入るなど、やはり指導者としては名監督中の名監督ともいえる所以である。
数学を捨てるには、それなりの覚悟を持って捨てて欲しいものである。芸大を目指す音楽家や画家の卵は、数学など眼中にないほど、自らの技能の鍛錬に日夜勤しむ。まるで、甲子園に出場し、その後プロのドラフトにかかることを夢見て学業二の次、三の次で、練習に明け暮れる高校球児が如きである。しかし、野球の名門校でも、文武両道を求められる学校もある。それこそが、文系であっても、数学を捨てないといった教育的理念と通底している。<言うは易し、行うは難し>でもある理想的“エリート”の道でもある。
ここで申し上げるが、この文武両道こそ、文理融合と見事に教育上の真理としてダブって見えてくるのである。
よく耳にする進学校で強調される文武両道は、ある意味、武がダメならいざという時、文でも生けていけるようにといった人生上の保険的謂いといったら語弊があるが、だいたいその程度で言われているに過ぎぬ。また、野村流にいえば、「アスリートである前に、立派な人間たれ」とも言える。長嶋・王クラスのアスリートなら武のみで人生が生きてもいける。しかし、野村級以下の素質の人間は文も身に着けなくてはならないということでもある。芸大を首席で卒業した音楽家や画家は、数学など一生無縁であってもかまわないといった文脈で相通じるものがある。
箱根駅伝に一切無縁で、人間科学部というスポーツに特科した学部を持たない、また、一般受験で江川卓を落とした慶應大学の姿勢に、文武両道のにおいを感じ取れる。また、文系でも、経済学部や商学部の入試で大方数学が必要とされてきた慶應大学の入試へのスタンスといったものも、文理融合の基本とさえいってもいいものである。早稲田大学が、政治経済学部で、中途半端に数学ⅠAのみを必須にしたところで、江戸幕府の慶喜の大政奉還{※辞官納地をしていない!}程度の“近代化”にしかなりはしない。実質は、西欧レベルの近代化などとは程遠い、つまり、中途半端な文理融合とさえ言ってもいいものである。
成毛眞氏の『日本人の9割に英語はいらない』(祥伝社)の題名を、敢えて拝借するならば、
『日本人の7割に数学はいらない』~但し、高校数学に関してである~といえそうである。
※弊塾のコラム2019年6月の『数学随想①~⑤』をお読み下されば、私の数学観がさらにご理解されることと思います。
『我等なぜキリスト教徒となりし乎』(安岡章太郎・井上洋治)
『余は如何にしてナショナリストとなりし乎』(福田和也)
以上の名著にちなみ、僭越ながら、私は、日ごろ書き損じている駄文、青春勉学記なるものを密かに書き溜めてもいるのだが、その副題こそ、次のようなものと決めている。
『余は如何にして数学落伍者となりし乎』(露木康仁)
数学落伍者は、落伍者なりに、それなりの公には言いづらい、心に秘めた個人的な大義名分というものがあるものである。
作家曽野綾子は「二次方程式がなくても生きてこられた」「二次方程式など社会へ出ても何の役にも立たないので、このようなものは追放すべきた」と発言し、その夫でもある三浦朱門は教育課程審議会会長を務められたこともあり、この発言が引きがねとなったかどうかは不明だが、その翌年、中学過程の“二次方程式の解の公式”は必須ではなくなった経緯がある。
また、近年、橋下徹元大阪府知事は「三角関数は生きてゆくために絶対に必要不可欠な知識じゃない」と発言したことで世間(ネット社会)をにぎわしたことが記憶に新しい。
英語学者で通訳者でもある鳥飼玖美子立教大学名誉教授は「自慢じゃないですが、私は算数から数学までまるでダメなんです。でも、けっして学校の教え方が悪かったからとは言いません。自分が悪かったと思いますね。」{『英語コンプレック粉砕宣言』(中公新書ラクレ)より}とも発言している。
三浦夫妻という、作家から文化人にまで上り詰めたご両者の、知的・文系的“保守派”というものでしょうか、ある意味、保守派として自民党の文教政策に影響力のある、ご二方は、著作物や発言など、日ごろ賛同するところ大ではありますが、やはり、どうも保守の文化人どまりで、保守の教養人とまで言いきれない側面がある。そこが、藤原正彦氏や渡部昇一氏との決定的な違いでもある。文化人とは、ある意味、政治色に染まった“教養人”とも言っていい。極論すれば、政治という魔物によって、知の判断部位が“下半身麻痺”となった種族とでも言ったら言い過ぎであろうか。
橋下徹氏に関しても、日ごろ、概ね、発言は過激なものながら、ある意味、自民党より、まっとうな保守の側面は有するが、やはり、大阪市の教育行政で、大阪市の学力調査最下位からの脱却を模索する手法として、教師の評価や教師同士の競い合いといった、新自由主義的手法を取り入れるなど、教育の側面では、経済的効率第一主義を貫こうとする弱点が垣間見えてくる。そうした手法が、教育現場では逆効果であることが分かっていらっしゃらないようだ。紅野謙介氏は、「「ゆとり」がほんとうに必要なのは教員である」とも語っておられる。この真実に橋下徹氏や教員更新制度を取り入れた安倍晋三などは、教育というももの根幹が全くわかってはいないようだ。橋下氏はお子さんが7人もいらっしゃる、しかも、その子育ては、全て妻まかせで「父親としては失格のパパだ」と公言までされている。安倍首相はお子さんがいらっしゃらない。こうした男族が、教育というもののかじ取りを誤らせるのである。
さすがに、英語教育改革の保守派でもある鳥飼氏は、謙虚である。自己の数学の弱点を他者、即ち、社会・学校・教師のせいにはせず、自己の責任と規定している点である。しかも、数学など必要ないとすら言ってはいない。政治的発言は一切しない英語学者でもある鳥飼氏の発言スタンスこそ、真の保守というものの証でもある。保守であるかどうか、それは憲法問題や日韓関係における発言ににじみ出るものでは決してない。
「勇ましいものはいつでも滑稽だ」(小林秀雄)
作家にしろ、政治家にしろ、英語学者にしろ、非数学のジャンルでは、人後に落ちぬほどその道を極めた方々でもある。非理系の領域に関しては、その分野の第一人者にまで上り詰めた方々である。
人間の機微を絶妙に描く文章力は、数学とは一切関係ないかもしれない。山本周五郎しかり、藤沢周平しかり、司馬遼太郎しかりである。また、人間のどろどろとした欲望うごめく政界でのし上がった田中角栄などは、人たらしの天才でもあった。彼は、高校数学などは無縁ではあったにしろ、数字の天才ではあった。その愛弟子、竹下登も同様である。また、高名なる英文学者にして博学なる知識人でもあった渡部昇一などは、数学にかかわりない種族のプライドともいえる<文系の流儀>を自著でとことん説いておられる。
もし、令和のデジタルの浮世において、数学という嗜みを手にしたもの、それは、理系のものは当然、国立大学へ進学する際、数学ⅡBまでを齧った人間を、まあ一流としよう。そうでない人間を、二流と規定しよう。ここでである。北斗の拳の原作者武論尊氏の著書『下流の生き方』の中の名言を引用するとしよう。
「上流に行きたいと思うから負けるんだよ。下流なら下流の意地で下流に生きてみろ」
この上流を学歴的基準で申し上げれば数学をある程度分かる、学んできた“一流”に、下流はこの文脈で数学とは疎遠であった“二流”に準えることができる。数学を捨てた部族は、こうした武論尊氏のような覚悟がなさすぎるのである。
数学がダメならダメの覚悟を持ち、徹底的に極論ながら、渡部昇一氏のような、非理系の王道を歩み、ぴか一の教養人・知識人・英文学者などになってやろうとする気概というものが、一般人にはないのである。
「一流は無理でも、“超二流”にはなれる」(野村克也)
これで成功した、野村の教え子がまさしく、宮本慎也であり、稲葉篤紀でもある。かれらは、ヤクルトに入団した時点で、2000本安打以上を打ち、名球会に入る逸材などと誰が予想したであろうか?古田敦也を加えると、野村の愛弟子が3人も名球会に入るなど、やはり指導者としては名監督中の名監督ともいえる所以である。
数学を捨てるには、それなりの覚悟を持って捨てて欲しいものである。芸大を目指す音楽家や画家の卵は、数学など眼中にないほど、自らの技能の鍛錬に日夜勤しむ。まるで、甲子園に出場し、その後プロのドラフトにかかることを夢見て学業二の次、三の次で、練習に明け暮れる高校球児が如きである。しかし、野球の名門校でも、文武両道を求められる学校もある。それこそが、文系であっても、数学を捨てないといった教育的理念と通底している。<言うは易し、行うは難し>でもある理想的“エリート”の道でもある。
ここで申し上げるが、この文武両道こそ、文理融合と見事に教育上の真理としてダブって見えてくるのである。
よく耳にする進学校で強調される文武両道は、ある意味、武がダメならいざという時、文でも生けていけるようにといった人生上の保険的謂いといったら語弊があるが、だいたいその程度で言われているに過ぎぬ。また、野村流にいえば、「アスリートである前に、立派な人間たれ」とも言える。長嶋・王クラスのアスリートなら武のみで人生が生きてもいける。しかし、野村級以下の素質の人間は文も身に着けなくてはならないということでもある。芸大を首席で卒業した音楽家や画家は、数学など一生無縁であってもかまわないといった文脈で相通じるものがある。
箱根駅伝に一切無縁で、人間科学部というスポーツに特科した学部を持たない、また、一般受験で江川卓を落とした慶應大学の姿勢に、文武両道のにおいを感じ取れる。また、文系でも、経済学部や商学部の入試で大方数学が必要とされてきた慶應大学の入試へのスタンスといったものも、文理融合の基本とさえいってもいいものである。早稲田大学が、政治経済学部で、中途半端に数学ⅠAのみを必須にしたところで、江戸幕府の慶喜の大政奉還{※辞官納地をしていない!}程度の“近代化”にしかなりはしない。実質は、西欧レベルの近代化などとは程遠い、つまり、中途半端な文理融合とさえ言ってもいいものである。
成毛眞氏の『日本人の9割に英語はいらない』(祥伝社)の題名を、敢えて拝借するならば、
『日本人の7割に数学はいらない』~但し、高校数学に関してである~といえそうである。
※弊塾のコラム2019年6月の『数学随想①~⑤』をお読み下されば、私の数学観がさらにご理解されることと思います。
2020年5月 4日 16:54